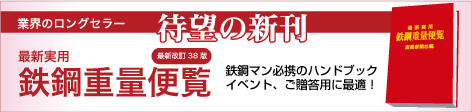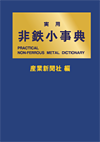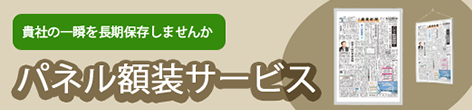2025年4月16日
100年企業に向けて 東京製鉄の挑戦/(1)/奈良暢明社長に聞く/挑戦と技術 競争力の源泉/価格発表で市場と対話 独自色
東京製鉄は老廃スクラップを用い、高品質製品の開発・生産・販売に取り組んできた。カーボンニュートラルに向けた動きが加速していることで、電炉鋼材への注目度が増している。2024年に創立90周年を迎えた長い歴史を持つ一方で国内に資源を循環させ、高い次元の鉄にするアップサイクルへの挑戦を続ける東京製鉄の奈良暢明社長に方針などを聞いた。
――改めて東鉄の社風、企業文化といえば。
「当社は1934年11月に東京都足立区で創立。それ以降、80年代までは異形棒鋼やH形鋼などの条鋼製品を中心に生産してきたが、91年に岡山工場でホットコイルを手掛け始め、国内鋼材需要の多くを占める鋼板製品への進出を果たし、90年代で酸洗コイル、溶融亜鉛めっきコイルへと進化を遂げている。2000年代は条鋼から鋼板への生産シフトを加速化し、関連する設備投資も行ってきている。07年に九州工場で厚板の生産をスタートし、09年には田原工場の稼働を開始した。近年は生産数量に占める鋼板の割合が条鋼を逆転している。企業文化で誇りに思っているのは大型直流電気炉、品種拡大に向けた圧延ラインなど『新たな世界に飛び込んでいく設備投資』。老廃(ヘビー)スクラップの国内循環にこだわり、それを使いこなす技術力は当社にとって生命線であり、独特の文化だと思う。製品販売価格(建値)、鉄スクラップ購入価格を公表するのも当社らしさと言える。電炉メーカーは装置産業だが、市況産業でもあるため、迅速に意思決定し、柔軟に行動しなければならず、少人数でシンプルな組織で、子会社を持たないのも特徴だ」
――品種拡大に挑戦してきた歴史でもある。
「新しいチャレンジであっても、それに当社の経営理念や伝統、文化を融合させることを大事にしている。東鉄らしさ、東鉄の在り方に沿っているかを自問自答しながら方針を考えている。例えば名古屋や尼崎、船橋に設置するサテライトヤードはまさにチャレンジと伝統の融合。工場敷地以外で鉄スクラップを集荷するという過去に例がない取り組みである一方、ポリシーである国内での資源循環を進める思いを込めている。サテライトヤードにおいても購入価格を公表しており、すでに地域のインデックス
の一つになっている。価格公表にこだわり、それを出し続けることによって、それぞれのエリアで価格影響力を強めていくという、経営理念を反映させている」
 ――国内外電炉メーカーの中での優位性は。
――国内外電炉メーカーの中での優位性は。
「国内で発生する貴重な資源でありながら、需給ギャップによって輸出されている鉄スクラップを国内に循環させ、『老廃スクラップから、より機能の高い製品に再生する鉄づくり』というアップサイクルを重要テーマに置いている。新断などの上級スクラップに頼らず、ヘビースクラップを使いこなして多品種を手掛けることは国内だけでなく、海外メーカーと比べても際立った特色。国内で一番多く発生するヘビースクラップは購入価格面でも最も標準的な電炉原料であり、これをアップサイクルすることに競争力の源泉がある」
――製品販売についても独自路線を歩む。
「毎月1回、製品販売価格を公表している。市場の現状を分析した当社視点からの価格を公表するのが当社の独自性で、マーケットと対話する機会をもらっている。また、対話が拡がることで取引のチャンスも増える。オープンなシステムを維持するために難しい判断を強いられる局面もあったが、足元のマーケットに対する当社の考え方を正確に伝え、理解してもらえるよう努めている」
――地球環境保全への想いを。
「資源循環型社会の実現に向けて取り組んでいるが、08年に当社が地球温暖化のレポートを公表して以来、CO2排出量が少ない電炉鋼材の供給を広げる動きを加速させている。この一環として、24年7月には低CO2鋼材『ほぼゼロ』の販売を開始した。需要家や加工業者による採用が増え、在庫する鋼材流通が拡がるなど、当社の考え方に共鳴していただき、感謝している。地球温暖化対策は顧客を含めたみんなのチャレンジと思っており、協働や連携によって地球温暖化に立ち向かう輪を広げていきたい」
――資源循環をさらに進めるための考えは。
「公共事業には、鋼材をはじめ多くの資機材が使われている。残念ながら、公共事業における当社鋼材の採用比率は低い。国や地方公共団体が手掛けた公共事業は潜在的に鉄の蓄積量が多く、民間企業と進めているスクラップコンバージョンと同様のスタイルも含め、国、地方公共団体が有する鉄を国内に循環させ、公共事業にもっと電炉鋼材を採用してもらえるよう働きかけていきたいと考えている」
 ――対象市場は国内のみ。
――対象市場は国内のみ。
「三井物産とともに米国電炉メーカーであるタムコ社の株式の保有していた時期もあるが、現時点で海外に拠点を置くことは考えていない。国内全4工場がフル稼働した場合、粗鋼ベースで年間600万トンの生産が可能となる。24年度の製品出荷数量は約300万トンとなる見込みで、鉄スクラップの輸出も高水準で推移している。当社は長期環境ビジョン『Tokyo Steel EcoVision2050』において、国内鉄スクラップ購入量(全社生産量に相当)を30年度で年間600万トンに引き上げる目標を掲げる。繰り返しになるが、鉄スクラップを国内に還流し、アップサイクルするという使命に集中し、追求しなければならないと感じている」
「年間ベースで国内鉄鋼需要が5000万トン程度となる一方で、普通鋼の鋼材輸入量が500万トンに至っている。さらに鉄スクラップ輸出量は600万トン台だ。鉄スクラップの国内循環を増やし、輸入材に対抗する価格を打ち出せば、この状況が緩和する可能性がある」
――少数の陣容だが、組織の考え方を。
「進むべき道に合わせて柔軟な組織を作る。カーボンニュートラルの流れが加速する中、電炉鋼材に対する問い合わせが増えており、これに応えるべく、技術部門を拡充している。営業や製造、総務の各部門においても中途採用を含めて拡充する。その一方で、省力化投資も推進する。当社の従業員数は約1110人。労働生産性と収益性をさらに追求できるよう人材の拡充、省力化の推進をともに実現する柔軟な組織を目指していきたい」
――4月から歌手の小林幸子さんをCSuO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)に任命し、初めて交通広告を展開した。
「『ほぼゼロ』を購入した顧客から『もっとPRした方が良い』と提案していただいて検討した結果、消費者に近いところで広く伝えることが重要だと判断し、交通広告の掲出を決めた。国民的スターである小林幸子さんに『ほぼゼロ』と当社を応援していただき、感謝している。『ほぼゼロ』を広めて頂けたら大変嬉しい」(濱坂浩司)

――改めて東鉄の社風、企業文化といえば。
「当社は1934年11月に東京都足立区で創立。それ以降、80年代までは異形棒鋼やH形鋼などの条鋼製品を中心に生産してきたが、91年に岡山工場でホットコイルを手掛け始め、国内鋼材需要の多くを占める鋼板製品への進出を果たし、90年代で酸洗コイル、溶融亜鉛めっきコイルへと進化を遂げている。2000年代は条鋼から鋼板への生産シフトを加速化し、関連する設備投資も行ってきている。07年に九州工場で厚板の生産をスタートし、09年には田原工場の稼働を開始した。近年は生産数量に占める鋼板の割合が条鋼を逆転している。企業文化で誇りに思っているのは大型直流電気炉、品種拡大に向けた圧延ラインなど『新たな世界に飛び込んでいく設備投資』。老廃(ヘビー)スクラップの国内循環にこだわり、それを使いこなす技術力は当社にとって生命線であり、独特の文化だと思う。製品販売価格(建値)、鉄スクラップ購入価格を公表するのも当社らしさと言える。電炉メーカーは装置産業だが、市況産業でもあるため、迅速に意思決定し、柔軟に行動しなければならず、少人数でシンプルな組織で、子会社を持たないのも特徴だ」
――品種拡大に挑戦してきた歴史でもある。
「新しいチャレンジであっても、それに当社の経営理念や伝統、文化を融合させることを大事にしている。東鉄らしさ、東鉄の在り方に沿っているかを自問自答しながら方針を考えている。例えば名古屋や尼崎、船橋に設置するサテライトヤードはまさにチャレンジと伝統の融合。工場敷地以外で鉄スクラップを集荷するという過去に例がない取り組みである一方、ポリシーである国内での資源循環を進める思いを込めている。サテライトヤードにおいても購入価格を公表しており、すでに地域のインデックス
の一つになっている。価格公表にこだわり、それを出し続けることによって、それぞれのエリアで価格影響力を強めていくという、経営理念を反映させている」
 ――国内外電炉メーカーの中での優位性は。
――国内外電炉メーカーの中での優位性は。「国内で発生する貴重な資源でありながら、需給ギャップによって輸出されている鉄スクラップを国内に循環させ、『老廃スクラップから、より機能の高い製品に再生する鉄づくり』というアップサイクルを重要テーマに置いている。新断などの上級スクラップに頼らず、ヘビースクラップを使いこなして多品種を手掛けることは国内だけでなく、海外メーカーと比べても際立った特色。国内で一番多く発生するヘビースクラップは購入価格面でも最も標準的な電炉原料であり、これをアップサイクルすることに競争力の源泉がある」
――製品販売についても独自路線を歩む。
「毎月1回、製品販売価格を公表している。市場の現状を分析した当社視点からの価格を公表するのが当社の独自性で、マーケットと対話する機会をもらっている。また、対話が拡がることで取引のチャンスも増える。オープンなシステムを維持するために難しい判断を強いられる局面もあったが、足元のマーケットに対する当社の考え方を正確に伝え、理解してもらえるよう努めている」
――地球環境保全への想いを。
「資源循環型社会の実現に向けて取り組んでいるが、08年に当社が地球温暖化のレポートを公表して以来、CO2排出量が少ない電炉鋼材の供給を広げる動きを加速させている。この一環として、24年7月には低CO2鋼材『ほぼゼロ』の販売を開始した。需要家や加工業者による採用が増え、在庫する鋼材流通が拡がるなど、当社の考え方に共鳴していただき、感謝している。地球温暖化対策は顧客を含めたみんなのチャレンジと思っており、協働や連携によって地球温暖化に立ち向かう輪を広げていきたい」
――資源循環をさらに進めるための考えは。
「公共事業には、鋼材をはじめ多くの資機材が使われている。残念ながら、公共事業における当社鋼材の採用比率は低い。国や地方公共団体が手掛けた公共事業は潜在的に鉄の蓄積量が多く、民間企業と進めているスクラップコンバージョンと同様のスタイルも含め、国、地方公共団体が有する鉄を国内に循環させ、公共事業にもっと電炉鋼材を採用してもらえるよう働きかけていきたいと考えている」
 ――対象市場は国内のみ。
――対象市場は国内のみ。「三井物産とともに米国電炉メーカーであるタムコ社の株式の保有していた時期もあるが、現時点で海外に拠点を置くことは考えていない。国内全4工場がフル稼働した場合、粗鋼ベースで年間600万トンの生産が可能となる。24年度の製品出荷数量は約300万トンとなる見込みで、鉄スクラップの輸出も高水準で推移している。当社は長期環境ビジョン『Tokyo Steel EcoVision2050』において、国内鉄スクラップ購入量(全社生産量に相当)を30年度で年間600万トンに引き上げる目標を掲げる。繰り返しになるが、鉄スクラップを国内に還流し、アップサイクルするという使命に集中し、追求しなければならないと感じている」
「年間ベースで国内鉄鋼需要が5000万トン程度となる一方で、普通鋼の鋼材輸入量が500万トンに至っている。さらに鉄スクラップ輸出量は600万トン台だ。鉄スクラップの国内循環を増やし、輸入材に対抗する価格を打ち出せば、この状況が緩和する可能性がある」
――少数の陣容だが、組織の考え方を。
「進むべき道に合わせて柔軟な組織を作る。カーボンニュートラルの流れが加速する中、電炉鋼材に対する問い合わせが増えており、これに応えるべく、技術部門を拡充している。営業や製造、総務の各部門においても中途採用を含めて拡充する。その一方で、省力化投資も推進する。当社の従業員数は約1110人。労働生産性と収益性をさらに追求できるよう人材の拡充、省力化の推進をともに実現する柔軟な組織を目指していきたい」
――4月から歌手の小林幸子さんをCSuO(チーフ・サステナビリティ・オフィサー)に任命し、初めて交通広告を展開した。
「『ほぼゼロ』を購入した顧客から『もっとPRした方が良い』と提案していただいて検討した結果、消費者に近いところで広く伝えることが重要だと判断し、交通広告の掲出を決めた。国民的スターである小林幸子さんに『ほぼゼロ』と当社を応援していただき、感謝している。『ほぼゼロ』を広めて頂けたら大変嬉しい」(濱坂浩司)


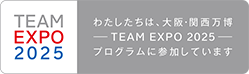












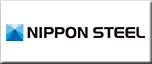


















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ