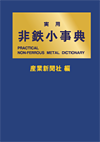2025年4月1日
新社長に聞く 三菱マテリアル 田中徹也氏 銅事業の戦略練り直し 設備投資の必要性 全社で判断
三菱マテリアルは今年度、2030年までの中期経営計画のフェーズ1が最終年度を迎える。フェーズ2策定の旗振り役としてきょう1日に就任した田中徹也新社長に、足元の事業環境や課題認識、収益拡大への施策などを聞いた。
――社長として期待されていることをどう考えているか。
「中経2030の第1フェーズが25年度で終了する。投資などはおおむね計画通り進んでいるが、利益が予定通りに上がっていない。中経策定時から事業環境の変化はあるが、施策に結果が伴っていないのは課題であり、26年度からのフェーズ2に向けどう修正するのかが新たな経営体制に期待されていることだと思っている」
――取り組むべき優先課題を。
「意思決定のスピードをこれまで以上に速める必要がある。昨今は経済状況の変化のスピードと度合いが従来に増して大きくなっており、それに対応しないといけない。具体的には、組織をなるべくフラットにしていくことを考えている。25年度から執行役の数を減らすことも迅速な意思決定につながると思う。現場力を磨くことにも力を注ぐ。製造現場は常に変化・進化しなければいけないが、それ以外の間接部門や営業部門も同じように現場力を磨き変革していく必要がある。それにより、各々の職場でイノベーションを起こしていくことが大事だと考えている」
「サステナビリティー経営も推進する。これは企業存続の土台をなすもので、例えば安全な職場という意味では労働災害ゼロを目指したい。DE&I(ダイバーシティー・エクイティー&インクルージョン)についても、当社は多様性がまだ不足しており、力を入れる。GHG(温室効果ガス)排出削減に向け、再エネ由来電力への切り替えに加え、再エネ事業を加速して使用電力をすべて賄うための取り組みもしっかり進める」
――事業環境の変化への対応は。
「銅製錬のTC/RC(溶錬費/精錬費)が大幅に低下しており、これは短期的でなくしばらく続くのではないかとみている。当社は鉱山投資と製錬事業を手掛け、銅加工事業があり、グループのルバタで銅製品も生産している。銅サプライチェーン(SC)全体を網羅しており、製錬の利益が非常に減る状況で、SCのどこに力を入れていくのか改めて戦略を練り直す必要があると考えている」
――フェーズ1の施策に収益が直結していないのはなぜか。
「フェーズ1は元々投資先行型の計画だったが、中国経済の減速や国内外の自動車産業の低迷など、経済環境が想定通りの動きになっていない。半導体業界もAI関連は順調に伸びているが、一般民生用はまだ復調に時間がかかるだろう。フェーズ2の議論はこれからだが、キャッシュインが減っているため、場合によっては投資も少しコントロールしていかねばならないかと考えている」
――個別の事業の中経施策の進捗と展望を聞きたい。資源事業は銅権益50万トン以上の目標を掲げる。現状はマントベルデ鉱山(チリ)が稼働して20万トン弱だが、目標は変わらないか。
「TC/RCの低下は鉱山側の利益増につながるため、製錬の減益分を稼ぐためにも鉱山権益を増やしていく方向性は従来と変わらない。ただ、優良な投資案件はなかなか見つかりにくい。目先は新たな鉱山投資より既存の投資先の拡張を進めることになると思う。現時点で権益目標は維持しているが、フェーズ2の戦略を議論する中で見直すということはあり得る」
――拡張計画を聞きたい。
「マントベルデの拡張投資が検討されている。基本的に拡張の方向だが、マントベルデの操業自体から生まれるキャッシュの活用はもちろん、スポンサーによる出資及び公的機関からの借入等といった資金調達の選択肢を見極めながら進めたい」
――製錬・資源循環事業はEスクラップ(廃電子基板類)リサイクル強化を進める。直島製錬所(香川県)は銅精鉱処理100万トン計画を86万トンに抑え、Eスクラップ増処理の方針に見直した。
「Eスクラップはオランダ子会社のMMMRが欧州中から集め、直島と小名浜製錬所(福島県)でリサイクルしている。MMMRのサンプリング能力を増強し欧州での集荷を強化する計画もある。日本全体の銅需要と製錬能力を比較すると、製錬能力の方が大きい。いたずらに鉱石処理量を増やしてもサステナブルではないとの判断から、Eスクラップに軸足をシフトした」
「いまは欧州のEスクラップを日本に問題なく持ってこられているが、昨今のブロック経済化の流れの中で、将来的には規制がかかるリスクも一定程度あると考えている。そうなると欧州で集めたものは欧州の同業とアライアンスを組んで処理するのも一つの選択肢になるのではないか。米国ではスクラップのみで銅や貴金属を造るイグザーバンプロジェクトに参加している。米国ではEスクラップが回収し切れていないため、ビジネスチャンスがあると思う」
――イグザーバンプロジェクトでは、インディアナ州にリサイクル製錬所を建設する計画がある。
「現在はテスト炉で大学などと一緒に実証実験やっている段階であり、着手はまだ。いずれは、米国で培った技術を日本やアジアの拠点にも展開していきたい」
――銅加工事業は収益性をいかに高めるかが課題だ。
「自動車・半導体産業の市場環境を受けて販売がいまひとつで利益が上がらない。一方で投資は予定通り行っているため苦しいが、経済環境が戻ってくれば確実に利益が出せる体制にはなると思っている。25年度はマーケティングと販路拡大に注力する。既存の販路はマーケットの回復を待たざるを得ず、新たな顧客の開拓をより積極的に行う。同時に、性能を高めた新合金開発も引き続き必要だ。性能が良ければ売れるわけではないと理解しているが、技術開発力で需要家が期待する以上の性能の合金を開発することも大事だと思う。『新たなマテリアルを創造する』というキーワードで、得意とする無酸素銅やマグネシウム入り銅合金に続く新たな合金開発に取り組みたい」
――ルバタとの連携について。
「銅加工で海外展開しようとすれば、ルバタの存在は大きい。ルバタは借入金の金利負担で経常損益が伸び悩むが、営業利益ベースでは安定して黒字が出ている」
――コストダウンのため投資の見直しもあるか。
「25年度はほかの事業も含めて全社的に設備投資を抑え、本当に必要な投資は事業ごとでなく全社で決めていく考えだ。将来の成長に必要な投資はもちろん行わなくてはいけないが、早めにリターンが得られるものを中心に実施したい」
――電子材料事業の角型シリコン基板やシール材の展望を。
「角型シリコンは三田工場(兵庫県)で量産体制の整備を進めており、販売増に寄与するだろう。半導体のドライエッチング装置向けのシール材は在庫調整局面にあるが、25年度後半くらいから回復するとみている。問題になっているPFAS(有機フッ素化合物)フリーのシール材にも着手している」
――加工事業の取り組みを。
「切削工具は最大の顧客が自動車業界で、市場環境は日本も欧州、アジアも減速気味。25年度も早々に状況が好転する状況にはないとみている。当社の強みである超硬合金とコーティングの技術力を生かして新製品を出し、顧客の生産性向上に寄与してシェアを高めたい。マーケットの伸びが小さくてもそれ以上に伸ばすという戦略になる」
「中国がタングステン輸出の審査を厳しくしたが、当社は数年前から中国調達比率を下げてきていた。スタルク買収のタイミングも良かった。スタルクはスクラップ原料使用比率が半分程度あり、それ以外はベトナムのマサングループから調達している部分が大きいため、当社グループ全体として中国調達比率が益々下がった。欧州では、MMMRのEスクラップ回収ルートで超硬合金の使用済み工具の回収も意外とある。それをスタルクに供給し、さらにリサイクル率を高める取り組みも進める」
「タングステン事業は、主にグループの日本新金属から炭化タングステンの供給を受けている。同社は超硬合金向けがメインだが、電子材料向けのターゲット用タングステンや触媒も生産。超硬合金向けよりも利益率が高く、結構な利益のポーションを占めている。日本新金属はそれらをほぼ国内でしか販売していないが、スタルクの販売ルートを使い欧州で売る、あるいはスタルクに製造移管して欧米に販売することなども検討する」
――工具は航空・宇宙分野など車以外で伸ばす方針だが、車向けの減少を補えるか。
「切削工具マーケットは全体としてシュリンクしていくだろう。30年位をピークに減ると想定していたが、EV化が減速気味なため数年後ろ倒しになるかもしれない。車向けの減少分を航空機向けなどで全て補うのは難しいだろう。ただ、航空機分野は耐熱合金やチタンなど削るのが難しい部品が多く、技術的にしっかりした超硬メーカーの製品でないと使えない。その意味では勝ち残れる領域ではないかと考える。米国ではケナメタル、欧州だとサンドビックなどの製品が多いが、当社の製品は全く見劣りせず、十分に入っていけると思っている」
――鉱山・土木用工具はどうか。
「南米向けにマイニング用の製品を拡販したい。MMCリョウテックがタイに新工場を建設しており、岩盤の削孔に使うロッドの増強を図る。従来は外部調達が多く、内製化によりリードタイムや価格面で顧客サービスを向上させる」
 ――加工事業のメキシコ拠点やスタルクのカナダ拠点で、米国の関税影響はあるか。
――加工事業のメキシコ拠点やスタルクのカナダ拠点で、米国の関税影響はあるか。
「切削工具などはあまり影響ないと認識しているが、メキシコに出ている日系自動車メーカーの操業度が下がるようだと、そこに売っている工具は減る可能性がある。逆に米国でオイルやガスの生産が増えれば、そこでも切削工具は多く使われるため、伸びてくるかもしれない」
――マサングループからヌイパオ鉱山(ベトナム)の権益を買い取る可能性は。
「鉱山を持てば休廃止後の環境維持にもお金がかかり、リスクがある。ヌイパオの山命もあまり長くないため、検討の遡上には上がったが、そこは取らないとなった」
――スタルクのカナダ工場はバージン材を使用しているが、北米のリサイクル拠点として活用する考えは。
「考えとしてある。スタルクのPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の中で、日本新金属とスタルクの工場でどのように製品をすみ分けするのか、リサイクルをどこで行うのかなどは検討項目になっている。北米で集めた使用済み工具は現在、米国の外部企業で中間処理してもらい、それを日本新金属に持ってきてリサイクルしている。中間処理はスタルクのカナダに切り替える方が合理的だと考える。経済のブロック化が進む中、なるべくエリア内で回収してリサイクルできた方が良いだろうという意味でもそう思う」
「リサイクルに関しては、日本新金属とスタルクで工程がかなり違う。コストはあまり変わらないと思うが、二酸化炭素排出量はスタルクの方が少ない。日本新金属でもリサイクル能力を引き上げていく計画があり、どこでリサイクルするか、どの方法で行うかは両社で話し合って進める必要がある」
――リチウムイオン電池(LiB)リサイクルの取り組みはどうか。
「スタルクはLiBリサイクルの研究開発に取り組み、当社も小名浜にLiBリサイクルのパイロットプラントを建設している。日本はまだEVがほとんど売れておらず、回収面での課題がある。一方、欧州は日本よりEVが浸透している。スタルクはドイツを中心とした自動車メーカーも加盟するコンソーシアムに入っており、そこでループが形成できる可能性もある。日本のパイロットプラントやスタルクの技術を見比べ、どこでリサイクル事業を行うのかは今後の判断になる」
――小名浜のパイロットプラントが25年に立ち上がり、28年度に事業化の目標を掲げるが、欧州が先行する可能性もあると。
「スタルクは実験段階だが、小名浜はパイロットプラントを建設しており、そのためのバックデータもある。パイロットレベルでは需要家から品質評価も受けており、進捗は日本の方が早い。28年度に向け、国内でコマーシャルプラントの土地候補も探している。ただ、使用済みLiBを国内でどのくらい集荷できそうかなどは確認する必要がある。その意味では、どちらが先に事業化できるか現時点では分からない」
――GHG削減の取り組みを。
「再エネを増やす取り組みのほか、製品のカーボンフットプリント(CFP)を主力製品からシステム化し、第三者認証取得を進めようとしている。しかし、顧客から製品のCFPについて現状はあまり聞かれないのも正直なところで、システム化は少しブレーキを踏んでいる感じだ。欧州はCSRD(企業サステナビリティ報告指令)で報告が求められる。このため切削工具などは二酸化炭素などの排出データを出し始めているが、その報告義務も少し後ろにずれそうだとの観測もある。米国でもGHG削減は少し減速するかもしれない。大きな流れは変わらないと思われ、当社は引き続きGHG排出削減に取り組んでいきたい」
(田島義史、鈴木大詩)
▽田中 徹也(たなか・てつや)氏=1986年東大工卒、三菱金属(現三菱マテリアル)入社、2019年執行役員、20年執行役常務・加工事業カンパニープレジデント、24年執行役常務・CSuO(チーフ・サステナビリティー・オフィサー)。1963年1月5日生まれ、千葉県出身。

――社長として期待されていることをどう考えているか。
「中経2030の第1フェーズが25年度で終了する。投資などはおおむね計画通り進んでいるが、利益が予定通りに上がっていない。中経策定時から事業環境の変化はあるが、施策に結果が伴っていないのは課題であり、26年度からのフェーズ2に向けどう修正するのかが新たな経営体制に期待されていることだと思っている」
――取り組むべき優先課題を。
「意思決定のスピードをこれまで以上に速める必要がある。昨今は経済状況の変化のスピードと度合いが従来に増して大きくなっており、それに対応しないといけない。具体的には、組織をなるべくフラットにしていくことを考えている。25年度から執行役の数を減らすことも迅速な意思決定につながると思う。現場力を磨くことにも力を注ぐ。製造現場は常に変化・進化しなければいけないが、それ以外の間接部門や営業部門も同じように現場力を磨き変革していく必要がある。それにより、各々の職場でイノベーションを起こしていくことが大事だと考えている」
「サステナビリティー経営も推進する。これは企業存続の土台をなすもので、例えば安全な職場という意味では労働災害ゼロを目指したい。DE&I(ダイバーシティー・エクイティー&インクルージョン)についても、当社は多様性がまだ不足しており、力を入れる。GHG(温室効果ガス)排出削減に向け、再エネ由来電力への切り替えに加え、再エネ事業を加速して使用電力をすべて賄うための取り組みもしっかり進める」
――事業環境の変化への対応は。
「銅製錬のTC/RC(溶錬費/精錬費)が大幅に低下しており、これは短期的でなくしばらく続くのではないかとみている。当社は鉱山投資と製錬事業を手掛け、銅加工事業があり、グループのルバタで銅製品も生産している。銅サプライチェーン(SC)全体を網羅しており、製錬の利益が非常に減る状況で、SCのどこに力を入れていくのか改めて戦略を練り直す必要があると考えている」
――フェーズ1の施策に収益が直結していないのはなぜか。
「フェーズ1は元々投資先行型の計画だったが、中国経済の減速や国内外の自動車産業の低迷など、経済環境が想定通りの動きになっていない。半導体業界もAI関連は順調に伸びているが、一般民生用はまだ復調に時間がかかるだろう。フェーズ2の議論はこれからだが、キャッシュインが減っているため、場合によっては投資も少しコントロールしていかねばならないかと考えている」
――個別の事業の中経施策の進捗と展望を聞きたい。資源事業は銅権益50万トン以上の目標を掲げる。現状はマントベルデ鉱山(チリ)が稼働して20万トン弱だが、目標は変わらないか。
「TC/RCの低下は鉱山側の利益増につながるため、製錬の減益分を稼ぐためにも鉱山権益を増やしていく方向性は従来と変わらない。ただ、優良な投資案件はなかなか見つかりにくい。目先は新たな鉱山投資より既存の投資先の拡張を進めることになると思う。現時点で権益目標は維持しているが、フェーズ2の戦略を議論する中で見直すということはあり得る」
――拡張計画を聞きたい。
「マントベルデの拡張投資が検討されている。基本的に拡張の方向だが、マントベルデの操業自体から生まれるキャッシュの活用はもちろん、スポンサーによる出資及び公的機関からの借入等といった資金調達の選択肢を見極めながら進めたい」
――製錬・資源循環事業はEスクラップ(廃電子基板類)リサイクル強化を進める。直島製錬所(香川県)は銅精鉱処理100万トン計画を86万トンに抑え、Eスクラップ増処理の方針に見直した。
「Eスクラップはオランダ子会社のMMMRが欧州中から集め、直島と小名浜製錬所(福島県)でリサイクルしている。MMMRのサンプリング能力を増強し欧州での集荷を強化する計画もある。日本全体の銅需要と製錬能力を比較すると、製錬能力の方が大きい。いたずらに鉱石処理量を増やしてもサステナブルではないとの判断から、Eスクラップに軸足をシフトした」
「いまは欧州のEスクラップを日本に問題なく持ってこられているが、昨今のブロック経済化の流れの中で、将来的には規制がかかるリスクも一定程度あると考えている。そうなると欧州で集めたものは欧州の同業とアライアンスを組んで処理するのも一つの選択肢になるのではないか。米国ではスクラップのみで銅や貴金属を造るイグザーバンプロジェクトに参加している。米国ではEスクラップが回収し切れていないため、ビジネスチャンスがあると思う」
――イグザーバンプロジェクトでは、インディアナ州にリサイクル製錬所を建設する計画がある。
「現在はテスト炉で大学などと一緒に実証実験やっている段階であり、着手はまだ。いずれは、米国で培った技術を日本やアジアの拠点にも展開していきたい」
――銅加工事業は収益性をいかに高めるかが課題だ。
「自動車・半導体産業の市場環境を受けて販売がいまひとつで利益が上がらない。一方で投資は予定通り行っているため苦しいが、経済環境が戻ってくれば確実に利益が出せる体制にはなると思っている。25年度はマーケティングと販路拡大に注力する。既存の販路はマーケットの回復を待たざるを得ず、新たな顧客の開拓をより積極的に行う。同時に、性能を高めた新合金開発も引き続き必要だ。性能が良ければ売れるわけではないと理解しているが、技術開発力で需要家が期待する以上の性能の合金を開発することも大事だと思う。『新たなマテリアルを創造する』というキーワードで、得意とする無酸素銅やマグネシウム入り銅合金に続く新たな合金開発に取り組みたい」
――ルバタとの連携について。
「銅加工で海外展開しようとすれば、ルバタの存在は大きい。ルバタは借入金の金利負担で経常損益が伸び悩むが、営業利益ベースでは安定して黒字が出ている」
――コストダウンのため投資の見直しもあるか。
「25年度はほかの事業も含めて全社的に設備投資を抑え、本当に必要な投資は事業ごとでなく全社で決めていく考えだ。将来の成長に必要な投資はもちろん行わなくてはいけないが、早めにリターンが得られるものを中心に実施したい」
――電子材料事業の角型シリコン基板やシール材の展望を。
「角型シリコンは三田工場(兵庫県)で量産体制の整備を進めており、販売増に寄与するだろう。半導体のドライエッチング装置向けのシール材は在庫調整局面にあるが、25年度後半くらいから回復するとみている。問題になっているPFAS(有機フッ素化合物)フリーのシール材にも着手している」
――加工事業の取り組みを。
「切削工具は最大の顧客が自動車業界で、市場環境は日本も欧州、アジアも減速気味。25年度も早々に状況が好転する状況にはないとみている。当社の強みである超硬合金とコーティングの技術力を生かして新製品を出し、顧客の生産性向上に寄与してシェアを高めたい。マーケットの伸びが小さくてもそれ以上に伸ばすという戦略になる」
「中国がタングステン輸出の審査を厳しくしたが、当社は数年前から中国調達比率を下げてきていた。スタルク買収のタイミングも良かった。スタルクはスクラップ原料使用比率が半分程度あり、それ以外はベトナムのマサングループから調達している部分が大きいため、当社グループ全体として中国調達比率が益々下がった。欧州では、MMMRのEスクラップ回収ルートで超硬合金の使用済み工具の回収も意外とある。それをスタルクに供給し、さらにリサイクル率を高める取り組みも進める」
「タングステン事業は、主にグループの日本新金属から炭化タングステンの供給を受けている。同社は超硬合金向けがメインだが、電子材料向けのターゲット用タングステンや触媒も生産。超硬合金向けよりも利益率が高く、結構な利益のポーションを占めている。日本新金属はそれらをほぼ国内でしか販売していないが、スタルクの販売ルートを使い欧州で売る、あるいはスタルクに製造移管して欧米に販売することなども検討する」
――工具は航空・宇宙分野など車以外で伸ばす方針だが、車向けの減少を補えるか。
「切削工具マーケットは全体としてシュリンクしていくだろう。30年位をピークに減ると想定していたが、EV化が減速気味なため数年後ろ倒しになるかもしれない。車向けの減少分を航空機向けなどで全て補うのは難しいだろう。ただ、航空機分野は耐熱合金やチタンなど削るのが難しい部品が多く、技術的にしっかりした超硬メーカーの製品でないと使えない。その意味では勝ち残れる領域ではないかと考える。米国ではケナメタル、欧州だとサンドビックなどの製品が多いが、当社の製品は全く見劣りせず、十分に入っていけると思っている」
――鉱山・土木用工具はどうか。
「南米向けにマイニング用の製品を拡販したい。MMCリョウテックがタイに新工場を建設しており、岩盤の削孔に使うロッドの増強を図る。従来は外部調達が多く、内製化によりリードタイムや価格面で顧客サービスを向上させる」
 ――加工事業のメキシコ拠点やスタルクのカナダ拠点で、米国の関税影響はあるか。
――加工事業のメキシコ拠点やスタルクのカナダ拠点で、米国の関税影響はあるか。「切削工具などはあまり影響ないと認識しているが、メキシコに出ている日系自動車メーカーの操業度が下がるようだと、そこに売っている工具は減る可能性がある。逆に米国でオイルやガスの生産が増えれば、そこでも切削工具は多く使われるため、伸びてくるかもしれない」
――マサングループからヌイパオ鉱山(ベトナム)の権益を買い取る可能性は。
「鉱山を持てば休廃止後の環境維持にもお金がかかり、リスクがある。ヌイパオの山命もあまり長くないため、検討の遡上には上がったが、そこは取らないとなった」
――スタルクのカナダ工場はバージン材を使用しているが、北米のリサイクル拠点として活用する考えは。
「考えとしてある。スタルクのPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の中で、日本新金属とスタルクの工場でどのように製品をすみ分けするのか、リサイクルをどこで行うのかなどは検討項目になっている。北米で集めた使用済み工具は現在、米国の外部企業で中間処理してもらい、それを日本新金属に持ってきてリサイクルしている。中間処理はスタルクのカナダに切り替える方が合理的だと考える。経済のブロック化が進む中、なるべくエリア内で回収してリサイクルできた方が良いだろうという意味でもそう思う」
「リサイクルに関しては、日本新金属とスタルクで工程がかなり違う。コストはあまり変わらないと思うが、二酸化炭素排出量はスタルクの方が少ない。日本新金属でもリサイクル能力を引き上げていく計画があり、どこでリサイクルするか、どの方法で行うかは両社で話し合って進める必要がある」
――リチウムイオン電池(LiB)リサイクルの取り組みはどうか。
「スタルクはLiBリサイクルの研究開発に取り組み、当社も小名浜にLiBリサイクルのパイロットプラントを建設している。日本はまだEVがほとんど売れておらず、回収面での課題がある。一方、欧州は日本よりEVが浸透している。スタルクはドイツを中心とした自動車メーカーも加盟するコンソーシアムに入っており、そこでループが形成できる可能性もある。日本のパイロットプラントやスタルクの技術を見比べ、どこでリサイクル事業を行うのかは今後の判断になる」
――小名浜のパイロットプラントが25年に立ち上がり、28年度に事業化の目標を掲げるが、欧州が先行する可能性もあると。
「スタルクは実験段階だが、小名浜はパイロットプラントを建設しており、そのためのバックデータもある。パイロットレベルでは需要家から品質評価も受けており、進捗は日本の方が早い。28年度に向け、国内でコマーシャルプラントの土地候補も探している。ただ、使用済みLiBを国内でどのくらい集荷できそうかなどは確認する必要がある。その意味では、どちらが先に事業化できるか現時点では分からない」
――GHG削減の取り組みを。
「再エネを増やす取り組みのほか、製品のカーボンフットプリント(CFP)を主力製品からシステム化し、第三者認証取得を進めようとしている。しかし、顧客から製品のCFPについて現状はあまり聞かれないのも正直なところで、システム化は少しブレーキを踏んでいる感じだ。欧州はCSRD(企業サステナビリティ報告指令)で報告が求められる。このため切削工具などは二酸化炭素などの排出データを出し始めているが、その報告義務も少し後ろにずれそうだとの観測もある。米国でもGHG削減は少し減速するかもしれない。大きな流れは変わらないと思われ、当社は引き続きGHG排出削減に取り組んでいきたい」
(田島義史、鈴木大詩)
▽田中 徹也(たなか・てつや)氏=1986年東大工卒、三菱金属(現三菱マテリアル)入社、2019年執行役員、20年執行役常務・加工事業カンパニープレジデント、24年執行役常務・CSuO(チーフ・サステナビリティー・オフィサー)。1963年1月5日生まれ、千葉県出身。














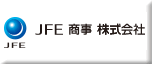
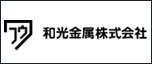
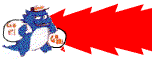
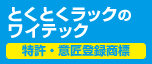















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ