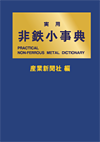2025年2月25日
財務・経営戦略を聞く /JFEHD副社長/寺畑雅史氏/量から質への転換加速/市場変化見極め成長戦略検討
――2024年度の鉄鋼事業(JFEスチール)のセグメント利益予想を260億円と前回予想から440億円下方修正した。海外グループ会社の減損の他、主な要因は。
「11月から1月にかけて製鉄所でトラブルが発生し、粗鋼生産で40万トン、50億円のマイナス影響を受けた。数量・構成差では数量でマイナスとなるが、販売調整の中で輸出汎用品を減らしたことによる構成のプラスとの差し引きで結果として50億円のマイナスとなる。高炉の操業自体は近年のCPS(サイバーフィジカルシステム)導入などDXの活用で安定しているが、今回は主に西日本製鉄所福山地区の原料搬送設備のトラブルによって減産した。昨年4月に本社にプラントエンジニアリング本部を設置し全社の設備更新の基準統一やトラブル発生時の対応力向上に取り組んできた中で大変残念なことだがすでに対策を講じ、一時的な影響にとどまる。グループ会社の利益は前回から170億円下方修正した。海外ではインドのJSWスチール、米国のCSIも市場が下振れした。海外市場の先行きをみて海外グループ会社の減損損失リスクを140億円織り込んでいる」
――JSWの業績回復やインド事業の成長の見通しは。
「JSWは製鉄所の拡張工事が終わり、10―12月は生産、販売量とも四半期の最高だったが、安価な中国材の輸入増で販売価格が低下した。インド政府が中国材に対し通商措置をとる姿勢をみせ、経済成長率もIMFが25年度に6・5%を予想しており、JSWの業績は回復してくるとみている。インドでは方向性電磁鋼板(GO)製造のtkESIの買収手続きを1月に完了し、25年度から収益に貢献してくる。GOは変電所向けなど政府関連の需要が多いが、そういった分野では中国材はあまり使われず価格の影響を受けないと見ている。データセンターの建設もGOの需要につながり、米国など世界的にGOの需要が増え、商品・事業として非常に有望だ。JSWとのGO製造販売会社のJ2ESは27年度の事業開始に向けて順調に進めている」
――需要が国内外とも低迷し、鋼材の輸出が減る一方で輸入が増え、事業環境が厳しさを増している。
「中国の鋼材輸出の増加が続いたために昨年、多くの国が中国材に対する通商措置に動き出している中で、日本も通商措置を含む議論を日本鉄鋼連盟が関係各所と連携して進めている。中国にとっては鋼材輸出が難しくなっていくことから、結果として粗鋼生産を抑えざるを得なくなるのではないか。中国の鉄鋼需要が回復に向かうようであればよいが、年明けも経済が大きく変化する様子はみえない。米新政権の通商政策の動向も含め、世界の鉄鋼ビジネスの中で先行き、事業環境の不安定な状態が続く見通しから今回、海外グループ会社の減損損失リスクを織り込んだ」
――鉄鋼事業の棚卸資産評価差等除く実力ベースのセグメント利益について2024年度予想を1220億円と前回から280億円下方修正した。24年度最終の中期経営計画目標2300億円を大きく下回ることに。
「前回予想で中計目標に達しない見通しを示し、数量減と海外グループ会社の減益を主な理由に挙げた。今回はトラブル要因で粗鋼生産がさらに減る予想となったが、安定して製造するための対策にあらためてしっかりと取り組む。原料価格が下がり局面なので平均販価は24年度下期に下がっているが、スプレッドは前回比、前年度比いずれもプラスとなり、販売価格改善の取り組みが成果を上げている。グループ会社はJFEシビルが物流倉庫関連などで堅調だが、JFEケミカルは化成品市況の下落や中国ビジネスの不振で悪化し、JFE条鋼は内需低迷の影響を受けている。海外グループ会社は先に挙げた米国やインドはじめ各地で事業環境が悪化した」
――JFEエンジニアリングとJFE商事の利益予想を前回から据え置いた。
「JFEエンジニアリングは200億円と据え置き、中計目標の350億円に届かないが、受注は廃棄物発電などのWaste to Resource分野や橋梁などの基幹インフラ分野が堅調で高水準を維持している。買収を決めた住友ケミカルエンジニアリングとJFEエンジニアリング、JFEプロジェクトワンなどの化学プラント事業の合計売上高は約600億円と化学プラント建設業界で国内3位となる。住友ケミカルエンジニアリングは海外にも拠点があり、国内外で事業を伸ばす。エンジの事業領域はM&Aのチャンスが多く、なお成長投資を進める方針だ。JFE商事は450億円の予想と前回並みで中計目標の400億円を上回る。ケリー・パイプやCEMCO、STUDCOなど米国の事業会社は市場がトランプ新政権の政策で上向くとみられ、収益を上げていく。電磁鋼板は各コイルセンターやJFE商事パワー・カナダ、25年度に稼働するセルビアの新加工・販売会社など広いネットワークで増える需要を捉える。エンジと商事の利益予想は合計650億円で25年度以降、さらに増える見通し。引き続きホールディングスの利益を支えてくれると期待している」
 ――25年度開始の新中計を策定中だが需要の前提をどう据え、成長戦略をどう描く。
――25年度開始の新中計を策定中だが需要の前提をどう据え、成長戦略をどう描く。
「国内需要は自動車と造船が牽引している状態だが、24年度の国内自動車生産は前年を下回る可能性があり、25年度も全体として大きな伸びは見込みにくい。造船は3年分の手持ち工事があるが人手不足などで建造ピッチが上がらない。土木建築は建設コスト上昇や人手不足の影響が続く。新中計は製造基盤の再強化、そして『量から質への転換』による高付加価値品比率のさらなる向上が重要テーマとなる。西日本製鉄所倉敷地区で無方向性電磁鋼板の製造能力を24年度上期に増強し、次の増強工事も26年度稼働を目指して取り組んでいる。福山地区のCGL(溶融亜鉛めっき鋼板製造設備)の増強も決め、量から質への転換を加速していく。粗鋼生産量は24年度予想を2200万トンに下方修正し、現中計の構造改革で前提にした2600万トン弱から1割以上落ちる。現在の事業環境を踏まえ、次期中計の数量規模を見極める必要がある。汎用品輸出は採算性をみながら一定程度を継続する」
――豪ブラックウォーター原料炭鉱山の権益取得の手続きを年度内に終える見通しだが、次の資源投資の計画は。
「原料炭、鉄鉱石ともによい案件を調査している。いちからの鉱山開発ではなく、開発されている鉱山の権益を取得する案件が増えている。原料の安定調達とともに収益を見込める権益の獲得に積極的に取り組んでいきたい」
――トランプ新政権の影響は。
「カナダとメキシコに対する関税引き上げの表明・延期、鉄鋼製品に対する関税引き上げの表明などがあったが、仮に関税引き上げが実行された際にまず懸念されるのは自動車産業が拠点を移すなど北米の製造業のサプライチェーンの変化だ。メキシコの24年の大型バス・トラック除いた自動車生産台数は399万台と過去最高。現地グループ会社のNJSMもメキシコの自動車メーカーや部品メーカーに供給しているが、彼らがメキシコから他国に生産を移すことになれば影響を受ける。関係国政府や需要産業の動きを注視しているが、当社として具体的に決まっている対応は現時点でない」
――日銀の利上げが続く見通し。財務面の影響は。
「資金需要が高いので財務のあり方を慎重に考えていく。有利子負債は1兆8000億円。変動金利1%の上昇で74億円のコスト増となるが、固定金利もいずれ上がるので影響は小さくはない。利上げによる需要への影響も懸念される」
――連結当期利益予想を下方修正したが、配当予想を据え置いた。
「海外グループ会社の減損損失や上期の台風影響、下期の製造トラブルなどいずれも一過性のマイナスであり、実力の損益をみて株主への安定配当を続ける。次期中計も安定配当の方針を変える考えはない」(植木 美知也)

「11月から1月にかけて製鉄所でトラブルが発生し、粗鋼生産で40万トン、50億円のマイナス影響を受けた。数量・構成差では数量でマイナスとなるが、販売調整の中で輸出汎用品を減らしたことによる構成のプラスとの差し引きで結果として50億円のマイナスとなる。高炉の操業自体は近年のCPS(サイバーフィジカルシステム)導入などDXの活用で安定しているが、今回は主に西日本製鉄所福山地区の原料搬送設備のトラブルによって減産した。昨年4月に本社にプラントエンジニアリング本部を設置し全社の設備更新の基準統一やトラブル発生時の対応力向上に取り組んできた中で大変残念なことだがすでに対策を講じ、一時的な影響にとどまる。グループ会社の利益は前回から170億円下方修正した。海外ではインドのJSWスチール、米国のCSIも市場が下振れした。海外市場の先行きをみて海外グループ会社の減損損失リスクを140億円織り込んでいる」
――JSWの業績回復やインド事業の成長の見通しは。
「JSWは製鉄所の拡張工事が終わり、10―12月は生産、販売量とも四半期の最高だったが、安価な中国材の輸入増で販売価格が低下した。インド政府が中国材に対し通商措置をとる姿勢をみせ、経済成長率もIMFが25年度に6・5%を予想しており、JSWの業績は回復してくるとみている。インドでは方向性電磁鋼板(GO)製造のtkESIの買収手続きを1月に完了し、25年度から収益に貢献してくる。GOは変電所向けなど政府関連の需要が多いが、そういった分野では中国材はあまり使われず価格の影響を受けないと見ている。データセンターの建設もGOの需要につながり、米国など世界的にGOの需要が増え、商品・事業として非常に有望だ。JSWとのGO製造販売会社のJ2ESは27年度の事業開始に向けて順調に進めている」
――需要が国内外とも低迷し、鋼材の輸出が減る一方で輸入が増え、事業環境が厳しさを増している。
「中国の鋼材輸出の増加が続いたために昨年、多くの国が中国材に対する通商措置に動き出している中で、日本も通商措置を含む議論を日本鉄鋼連盟が関係各所と連携して進めている。中国にとっては鋼材輸出が難しくなっていくことから、結果として粗鋼生産を抑えざるを得なくなるのではないか。中国の鉄鋼需要が回復に向かうようであればよいが、年明けも経済が大きく変化する様子はみえない。米新政権の通商政策の動向も含め、世界の鉄鋼ビジネスの中で先行き、事業環境の不安定な状態が続く見通しから今回、海外グループ会社の減損損失リスクを織り込んだ」
――鉄鋼事業の棚卸資産評価差等除く実力ベースのセグメント利益について2024年度予想を1220億円と前回から280億円下方修正した。24年度最終の中期経営計画目標2300億円を大きく下回ることに。
「前回予想で中計目標に達しない見通しを示し、数量減と海外グループ会社の減益を主な理由に挙げた。今回はトラブル要因で粗鋼生産がさらに減る予想となったが、安定して製造するための対策にあらためてしっかりと取り組む。原料価格が下がり局面なので平均販価は24年度下期に下がっているが、スプレッドは前回比、前年度比いずれもプラスとなり、販売価格改善の取り組みが成果を上げている。グループ会社はJFEシビルが物流倉庫関連などで堅調だが、JFEケミカルは化成品市況の下落や中国ビジネスの不振で悪化し、JFE条鋼は内需低迷の影響を受けている。海外グループ会社は先に挙げた米国やインドはじめ各地で事業環境が悪化した」
――JFEエンジニアリングとJFE商事の利益予想を前回から据え置いた。
「JFEエンジニアリングは200億円と据え置き、中計目標の350億円に届かないが、受注は廃棄物発電などのWaste to Resource分野や橋梁などの基幹インフラ分野が堅調で高水準を維持している。買収を決めた住友ケミカルエンジニアリングとJFEエンジニアリング、JFEプロジェクトワンなどの化学プラント事業の合計売上高は約600億円と化学プラント建設業界で国内3位となる。住友ケミカルエンジニアリングは海外にも拠点があり、国内外で事業を伸ばす。エンジの事業領域はM&Aのチャンスが多く、なお成長投資を進める方針だ。JFE商事は450億円の予想と前回並みで中計目標の400億円を上回る。ケリー・パイプやCEMCO、STUDCOなど米国の事業会社は市場がトランプ新政権の政策で上向くとみられ、収益を上げていく。電磁鋼板は各コイルセンターやJFE商事パワー・カナダ、25年度に稼働するセルビアの新加工・販売会社など広いネットワークで増える需要を捉える。エンジと商事の利益予想は合計650億円で25年度以降、さらに増える見通し。引き続きホールディングスの利益を支えてくれると期待している」
 ――25年度開始の新中計を策定中だが需要の前提をどう据え、成長戦略をどう描く。
――25年度開始の新中計を策定中だが需要の前提をどう据え、成長戦略をどう描く。「国内需要は自動車と造船が牽引している状態だが、24年度の国内自動車生産は前年を下回る可能性があり、25年度も全体として大きな伸びは見込みにくい。造船は3年分の手持ち工事があるが人手不足などで建造ピッチが上がらない。土木建築は建設コスト上昇や人手不足の影響が続く。新中計は製造基盤の再強化、そして『量から質への転換』による高付加価値品比率のさらなる向上が重要テーマとなる。西日本製鉄所倉敷地区で無方向性電磁鋼板の製造能力を24年度上期に増強し、次の増強工事も26年度稼働を目指して取り組んでいる。福山地区のCGL(溶融亜鉛めっき鋼板製造設備)の増強も決め、量から質への転換を加速していく。粗鋼生産量は24年度予想を2200万トンに下方修正し、現中計の構造改革で前提にした2600万トン弱から1割以上落ちる。現在の事業環境を踏まえ、次期中計の数量規模を見極める必要がある。汎用品輸出は採算性をみながら一定程度を継続する」
――豪ブラックウォーター原料炭鉱山の権益取得の手続きを年度内に終える見通しだが、次の資源投資の計画は。
「原料炭、鉄鉱石ともによい案件を調査している。いちからの鉱山開発ではなく、開発されている鉱山の権益を取得する案件が増えている。原料の安定調達とともに収益を見込める権益の獲得に積極的に取り組んでいきたい」
――トランプ新政権の影響は。
「カナダとメキシコに対する関税引き上げの表明・延期、鉄鋼製品に対する関税引き上げの表明などがあったが、仮に関税引き上げが実行された際にまず懸念されるのは自動車産業が拠点を移すなど北米の製造業のサプライチェーンの変化だ。メキシコの24年の大型バス・トラック除いた自動車生産台数は399万台と過去最高。現地グループ会社のNJSMもメキシコの自動車メーカーや部品メーカーに供給しているが、彼らがメキシコから他国に生産を移すことになれば影響を受ける。関係国政府や需要産業の動きを注視しているが、当社として具体的に決まっている対応は現時点でない」
――日銀の利上げが続く見通し。財務面の影響は。
「資金需要が高いので財務のあり方を慎重に考えていく。有利子負債は1兆8000億円。変動金利1%の上昇で74億円のコスト増となるが、固定金利もいずれ上がるので影響は小さくはない。利上げによる需要への影響も懸念される」
――連結当期利益予想を下方修正したが、配当予想を据え置いた。
「海外グループ会社の減損損失や上期の台風影響、下期の製造トラブルなどいずれも一過性のマイナスであり、実力の損益をみて株主への安定配当を続ける。次期中計も安定配当の方針を変える考えはない」(植木 美知也)














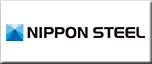
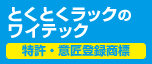
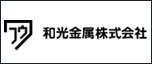
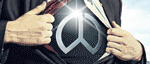















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ