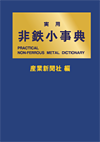2024年6月20日
商社の経営戦略―加速する脱炭素・市場開拓―/日鉄物産 中村真一社長/冷鉄源集荷・物流を強化/新エネ・高機能材分野に焦点
――2024年3月期の連結経常利益は前期比3%増の528億円となった。
「海外では鋼材需要が低迷し、価格が急落するなど未曾有の厳しい状況が続き、国内も人手不足や資材高騰によって建設分野を中心に内需の低迷が続いた。こうした中、成長戦略の実行による収益増加、国内外グループ会社の業績改善などによって経常利益は3 期連続で過去最高益となった。鉄鋼事業は国内システム建築の販売が順調で、産機・インフラ事業はチャイナ+1の潮流を捉えたタイのロジャナ工業団地の土地販売が極めて好調だった。食糧事業はインバウンド需要の回復を背景とした外食向け牛肉の販売増が収益を押し上げた。繊維事業は前期にあった一過性利益が剥落したが、インバウンド需要やコロナ禍の収束もあって実力損益は回復基調にある。一過性要因を除く実力損益は500億円超レベルに達しており、収益力は着実に向上している」
――セグメント別の利益は。
「鉄鋼は前期比1億円増の438億円、産機・インフラが17億円増の37億円、食糧が4億円増の29億円、繊維は8億円減の31億円だった」
――主力の鉄鋼事業はほぼ横ばいだった。
「輸出価格の下落、固定費の増加など39億円の減益要因を成長戦略の実行効果で吸収した。取り扱い数量は単体が23万トン増の1245万トン、子会社が8万トン減の421万トンで、連結合計は15万トン増の1666万トン。単体の国内販売価格が前期比で3%上昇する一方、輸出価格が13%低下。鋼材の平均単価は前期のトン15万4900円から15万3100円に低下した」
――財務体質は改善した。
「債権流動化の実施により有利子負債を4253億円から3400億円に圧縮した結果、ネットDEレシオは1・26倍から0・81倍に大きく改善した。自己資本を3144億円から3602億円に積み上げ、自己資本比率は27・5%から32・3%に上昇した」
――今期は経常利益500億円と減益を予想する。
「中国の鉄鋼輸出が増加する中、国際鉄鋼需給が緩んで、海外は原料市況と鋼材市況のデカップリングが鮮明になっている。国内においても鋼材需要が低迷し、人件費や物流コストなどが増加するなど厳しい事業環境が続くとみている。こうした中においても中長期経営計画で打ち出した成長戦略の着実な実行、日本製鉄の子会社化によるシナジーの追求、人財確保・育成の強化等に努め、500億円の経常利益を目標に掲げてスタートしたが、追加施策の実行・完遂による4期連続の最高益は視野に入れている」
――重点テーマは。
「鉄鋼事業における米州、インドなど海外事業の拡大、国内における薄板事業のグループ力強化、流通・加工最適化の推進等が足元の課題。日本製鉄の戦略商品の輸出力強化、冷鉄源の安定調達、NSカーボレックスの拡販手法の確立が短中期の重要な課題となる」
――本年10月にNS建材薄板を吸収合併する。
「国内の薄板事業における流通・加工機能の最適化によるグループ総合力の強化を加速する。NS建材薄板の合併は日鉄物産グループの再編であるが、日本製鉄グループとしての薄板建材事業戦略の一環でもあり、効果を最大限に広げていく」
――中長期経営計画(22-25年度)の進捗状況を。
「最終25年度の目標に掲げた経常利益450億円は超過達成した。日本製鉄との連携強化によるシナジーの発揮等によって、さらなる利益成長を図るため計画を見直した。数値目標は公表していないが、成長戦略を加速し、実力ベースの利益拡大に邁進していく」
――主要施策として「事業基盤強化」「成長戦略」「ESG経営の深化」をテーマに掲げている。
「事業基盤強化に向けて、付加価値生産性を引き上げるための人的資本の拡充、製造・販売拠点の再編・統合・撤退による課題事業の収益改善を推進しており、計画を上回るペースで進展している」
――製造・販売拠点の再編を加速している。
「日鉄物産メカニカル鋼管が酒井新から自動車用鋼管の加工・流通事業を継承した。一方、子会社の三橋鋼材の厚板加工事業を日本製鉄の子会社である日鉄神鋼シャーリングに譲渡。子会社のNS建材販売が日鉄建材の子会社であるエスケイ工事を吸収合併した」
――成長戦略について。
「成長分野・地域に経営資源を重点的に投入しながら、次世代の収益の柱の育成を進めており、こちらも計画を上回るペースで進んでいる。メキシコを含む海外事業の拡大や国内における薄板事業のグループ力強化、国内流通・加工最適化など、日本製鉄による子会社化効果もあってスピードを上げながら進展している」
――ESG経営の深化については。
「ステークホルダーの課題、当社グループの企業理念や役割、成長戦略を踏まえ、ESG経営に関する6つのマテリアリティを特定。各事業本部が重点的に取り組むテーマを選定し、具体的なアクションプランを作成。活動を推進するとともにサステナビリティ委員会において進捗状況のモニタリングを定期的に行っている。事業戦略と連動しながらPDCAサイクルを回していくことにより、着実に成果を上げている」
――投資は5年間で750億円の計画。
「当初計画で見込んでいた想定の水準で、成長戦略に資する事業投資を進めていく」
――脱炭素社会に対応する鉄鋼メーカー商社としての機能の拡充が求められている。
「日本製鉄グループの電炉向け冷鉄源ニーズが増加していくことは確実であり、商社機能として冷鉄源集荷力の強化、物流体制の整備を進めていきたい」
――電磁鋼板の加工・物流機能も期待されている。
「メキシコで電磁鋼板用のコイルセンターを建設中。世界第2位の自動車市場である北米市場におけるEV向けの電磁鋼板需要に対応するもので、高級電磁鋼板の精整・スリット加工機能を担う。来年4月の稼働開始に向けて建設工事を進めている」
――国内では、持分法適用会社の電機資材を子会社化する。
「電機資材の出資比率は日本製鉄グループが44・9%、うち日鉄物産は23・8%で、グループ以外の企業が55・1%。当社がグループ以外の企業から株式を追加取得し、出資比率を過半数に引き上げる。関係当局の認可を進めており、8月1日付で子会社化する予定。電機資材は袖ケ浦、堺に加工物流拠点を持ち、国内外にグループ会社がある。電磁鋼板の営業基盤とサプライチェーン強化策を加速させる」
――国内コイルセンター網の機能強化策を。
「苫小牧スチールセンター、日鉄物産名古屋コイルセンターの本社・名古屋工場と静岡工場、NSMコイルセンターの群馬、佐野、有明、君津、横浜、大阪(堺市と大阪市)、姫路、日鉄物産関東コイルセンターの13拠点を展開している。グループ内の機能集約・再編を進めてきたが、今後は日本製鉄の地域戦略に沿って必要な対策を講じていく」
――産機・インフラ、食糧については。
「産機・インフラ事業はタイやメキシコにおける工業団地事業の収益基盤強化が重点課題。食糧事業は、事業環境・需給変化の前触れ捕捉とリスク回避の実行、今後の成長戦略の検討・実行を進めていく」
 ――国内外の市場を開拓する機能も期待されている。
――国内外の市場を開拓する機能も期待されている。
「洋上風力発電所、EV関連など新エネルギー分野や高機能材分野をメーンターゲットとし、国内・海外という切り分けではなく、需要地あるいは顧客立地による新規開拓を推進する。国内では電力会社向け新エネルギー対応燃料貯蔵タンク向けなどチタンの需要開拓にも注力する」
――北米、インドは市場開拓を急ぐ必要がある。
「北米では、先ほど述べた通り、運転資金も含めれば過去最大の投資となる電磁鋼板用のコイルセンターをメキシコで建設中。メキシコではアグアスカリエンテス・スチール・コイルセンターが稼働している。米国ではケンタッキー・スチールセンターがケンタッキー州とテネシー州でコイルセンター事業を展開。今後も日本製鉄の海外戦略と同期化して市場開拓を進めていく」
――需要の伸びが期待されるインド市場対策は。
「ニムラナ・スチール・サービスセンターがラジャスタン州でコイルセンター機能を発揮しているが、チェンナイ近郊のスリシティーで第2工場を稼働させた。今後はEVをはじめとする現地の製造業向け需要に対応する電磁鋼板などハイエンド材の輸出拡大を狙っていく。現地の鉄鋼メーカーとは副原料などの取引を通じた関係強化も図っていく」
――中国は需要構造変化への対応を迫られている。
「上海、天津、深圳、東莞、蘇州でコイルセンター事業を展開しており、子会社化する電機資材が加工拠点を持つ。現地の日系需要家の動向、日本製鉄の戦略を見極めながら機能の集約・強化策を検討していく」
――ASEANについては。
「タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、シンガポール、バングラデシュなどでコイルセンター、線材加工事業などを幅広く展開している。タイを中心に各国拠点の横連携をさらに進化させ、地産地消化を促進し、地域需要を面で取り込んでいく。フィリピンは駐在員事務所を現地法人に格上げし、拡大が期待されるインフラ・エネルギー分野の現地需要を捕捉していく」
――人材戦略も重要なテーマとなる。
「最大の財産が『人』。人材の確保と能力発揮を最重要課題の一つとして取り組んでいる。事業規模を国内外で拡大しており、多様な人材を受け入れ、それぞれの事業領域で、個々人が最大限に力を発揮できる環境を整備していく」
――採用方針は。
「インターンシップなどの拡充を進めながら、将来の成長に向けた新卒採用、中長期経営計画に基づく中途採用を安定的に行っている。新卒採用と中途採用の比率を7対3から6対4に設定しており、今年は新卒50人、中途で35人程度を採用した。新卒の総合職採用における女性比率の目標を3割超に定めて重点的に取り組んでおり、近年は10-30%強で推移している」
――社内コミュニケーション強化策については。
「まずは年次別研修や若手対象の育成面談制度をはじめコミュニケーション活性化に取り組んでいる。教育研修の充実等の人材投資の拡大、処遇改善も進めている。また若手・中堅社員による選抜型キャリアデベロップメント研修を通じて、社員が自らのキャリア成長を図るために必要な仕組みや制度を経営陣に提案し、成果発表することも予定している」
――長期にわたって働いてもらう仕掛けも必要。
「社員が多様な経験を積めるよう、複数部門をローテーションする仕組みを検討している。企業としての持続的成長の機会を逃さないためには、様々な役割を担う社員が、広い視野と高い感性、そして何よりも成長への意欲を持つことが重要。そうした人材を育成するための施策を検討・実行していく」
――処遇を大幅に改善する。
「24年度は組合員一人あたり3万円、約10%のベースアップを実施する。賞与は3年連続過去最高益を達成した成果に報いるため労働組合の要求に満額回答した。総合職の初任給も26万円から30万円に引き上げる」
――「2024年問題」が深刻化しており、物流効率化も重要なテーマとなっている。
「運転手の待機時間ルール遵守、契約外付帯作業の廃止徹底に向けて、23年6月に行政より公表されたガイドラインに沿ってグループ企業の検証を行ったが、大きな問題がないことを確認している。グループ会社を含めた法規制への対応を強化するとともに、日本製鉄、日鉄物流等の日本製鉄グループ一貫物流連携の枠組みの中で、検討・協議を進めていく」
――日本製鉄の子会社となり、戦略的連携によるシナジーの発揮が期待されている。
「日本製鉄は将来にわたって日本の産業競争力を支える『総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカー』を目指している。日鉄物産は日本製鉄グループの中核商社としてサプライチェーンにおける流通の役割を担ってきたが、子会社になったことでより高い次元で情報や営業戦略を共有し、グループ内のノウハウやインフラを最大限に活用しながら競争力強化を図ることが可能になった。『商社機能の日本製鉄グループでの効率化・強化』『営業ノウハウ・インフラを一体活用した直接営業力の強化』『サプライチェーンのさらなる高度化、新たなビジネスモデルの構築』をテーマに掲げ、シナジーを最大限に発揮していく」
――次期中計に向けての課題と展望、日本製鉄グループの中核商社としての2030年のあり姿を聞きたい。
「日本製鉄とのシナジーの最大発揮と当社独自戦略の完遂によって、数年内の600億円超の実力利益の確保を目指す。それを達成した段階で1000億円規模の利益達成に向けたビジョンを描いていきたい。主軸の鉄鋼事業を中軸とし、グループ内で異彩を放つ産機・インフラ、食糧、繊維の収益性の高い3事業を展開する日本製鉄グループの中核商社としてプレゼンスを高めていく」
――統合以来最大の処遇改善を実施した。
「人材の確保と育成、社員の能力の最大発揮は経営の最重要課題の一つであり、『人への投資』を積極的に推進し、社員の成長に資する人事施策制度を引き続き検討していく。労使一体となって、将来の連結経常利益1000億円規模の達成に向けたビジョンを描いていく」(谷藤 真澄)

「海外では鋼材需要が低迷し、価格が急落するなど未曾有の厳しい状況が続き、国内も人手不足や資材高騰によって建設分野を中心に内需の低迷が続いた。こうした中、成長戦略の実行による収益増加、国内外グループ会社の業績改善などによって経常利益は3 期連続で過去最高益となった。鉄鋼事業は国内システム建築の販売が順調で、産機・インフラ事業はチャイナ+1の潮流を捉えたタイのロジャナ工業団地の土地販売が極めて好調だった。食糧事業はインバウンド需要の回復を背景とした外食向け牛肉の販売増が収益を押し上げた。繊維事業は前期にあった一過性利益が剥落したが、インバウンド需要やコロナ禍の収束もあって実力損益は回復基調にある。一過性要因を除く実力損益は500億円超レベルに達しており、収益力は着実に向上している」
――セグメント別の利益は。
「鉄鋼は前期比1億円増の438億円、産機・インフラが17億円増の37億円、食糧が4億円増の29億円、繊維は8億円減の31億円だった」
――主力の鉄鋼事業はほぼ横ばいだった。
「輸出価格の下落、固定費の増加など39億円の減益要因を成長戦略の実行効果で吸収した。取り扱い数量は単体が23万トン増の1245万トン、子会社が8万トン減の421万トンで、連結合計は15万トン増の1666万トン。単体の国内販売価格が前期比で3%上昇する一方、輸出価格が13%低下。鋼材の平均単価は前期のトン15万4900円から15万3100円に低下した」
――財務体質は改善した。
「債権流動化の実施により有利子負債を4253億円から3400億円に圧縮した結果、ネットDEレシオは1・26倍から0・81倍に大きく改善した。自己資本を3144億円から3602億円に積み上げ、自己資本比率は27・5%から32・3%に上昇した」
――今期は経常利益500億円と減益を予想する。
「中国の鉄鋼輸出が増加する中、国際鉄鋼需給が緩んで、海外は原料市況と鋼材市況のデカップリングが鮮明になっている。国内においても鋼材需要が低迷し、人件費や物流コストなどが増加するなど厳しい事業環境が続くとみている。こうした中においても中長期経営計画で打ち出した成長戦略の着実な実行、日本製鉄の子会社化によるシナジーの追求、人財確保・育成の強化等に努め、500億円の経常利益を目標に掲げてスタートしたが、追加施策の実行・完遂による4期連続の最高益は視野に入れている」
――重点テーマは。
「鉄鋼事業における米州、インドなど海外事業の拡大、国内における薄板事業のグループ力強化、流通・加工最適化の推進等が足元の課題。日本製鉄の戦略商品の輸出力強化、冷鉄源の安定調達、NSカーボレックスの拡販手法の確立が短中期の重要な課題となる」
――本年10月にNS建材薄板を吸収合併する。
「国内の薄板事業における流通・加工機能の最適化によるグループ総合力の強化を加速する。NS建材薄板の合併は日鉄物産グループの再編であるが、日本製鉄グループとしての薄板建材事業戦略の一環でもあり、効果を最大限に広げていく」
――中長期経営計画(22-25年度)の進捗状況を。
「最終25年度の目標に掲げた経常利益450億円は超過達成した。日本製鉄との連携強化によるシナジーの発揮等によって、さらなる利益成長を図るため計画を見直した。数値目標は公表していないが、成長戦略を加速し、実力ベースの利益拡大に邁進していく」
――主要施策として「事業基盤強化」「成長戦略」「ESG経営の深化」をテーマに掲げている。
「事業基盤強化に向けて、付加価値生産性を引き上げるための人的資本の拡充、製造・販売拠点の再編・統合・撤退による課題事業の収益改善を推進しており、計画を上回るペースで進展している」
――製造・販売拠点の再編を加速している。
「日鉄物産メカニカル鋼管が酒井新から自動車用鋼管の加工・流通事業を継承した。一方、子会社の三橋鋼材の厚板加工事業を日本製鉄の子会社である日鉄神鋼シャーリングに譲渡。子会社のNS建材販売が日鉄建材の子会社であるエスケイ工事を吸収合併した」
――成長戦略について。
「成長分野・地域に経営資源を重点的に投入しながら、次世代の収益の柱の育成を進めており、こちらも計画を上回るペースで進んでいる。メキシコを含む海外事業の拡大や国内における薄板事業のグループ力強化、国内流通・加工最適化など、日本製鉄による子会社化効果もあってスピードを上げながら進展している」
――ESG経営の深化については。
「ステークホルダーの課題、当社グループの企業理念や役割、成長戦略を踏まえ、ESG経営に関する6つのマテリアリティを特定。各事業本部が重点的に取り組むテーマを選定し、具体的なアクションプランを作成。活動を推進するとともにサステナビリティ委員会において進捗状況のモニタリングを定期的に行っている。事業戦略と連動しながらPDCAサイクルを回していくことにより、着実に成果を上げている」
――投資は5年間で750億円の計画。
「当初計画で見込んでいた想定の水準で、成長戦略に資する事業投資を進めていく」
――脱炭素社会に対応する鉄鋼メーカー商社としての機能の拡充が求められている。
「日本製鉄グループの電炉向け冷鉄源ニーズが増加していくことは確実であり、商社機能として冷鉄源集荷力の強化、物流体制の整備を進めていきたい」
――電磁鋼板の加工・物流機能も期待されている。
「メキシコで電磁鋼板用のコイルセンターを建設中。世界第2位の自動車市場である北米市場におけるEV向けの電磁鋼板需要に対応するもので、高級電磁鋼板の精整・スリット加工機能を担う。来年4月の稼働開始に向けて建設工事を進めている」
――国内では、持分法適用会社の電機資材を子会社化する。
「電機資材の出資比率は日本製鉄グループが44・9%、うち日鉄物産は23・8%で、グループ以外の企業が55・1%。当社がグループ以外の企業から株式を追加取得し、出資比率を過半数に引き上げる。関係当局の認可を進めており、8月1日付で子会社化する予定。電機資材は袖ケ浦、堺に加工物流拠点を持ち、国内外にグループ会社がある。電磁鋼板の営業基盤とサプライチェーン強化策を加速させる」
――国内コイルセンター網の機能強化策を。
「苫小牧スチールセンター、日鉄物産名古屋コイルセンターの本社・名古屋工場と静岡工場、NSMコイルセンターの群馬、佐野、有明、君津、横浜、大阪(堺市と大阪市)、姫路、日鉄物産関東コイルセンターの13拠点を展開している。グループ内の機能集約・再編を進めてきたが、今後は日本製鉄の地域戦略に沿って必要な対策を講じていく」
――産機・インフラ、食糧については。
「産機・インフラ事業はタイやメキシコにおける工業団地事業の収益基盤強化が重点課題。食糧事業は、事業環境・需給変化の前触れ捕捉とリスク回避の実行、今後の成長戦略の検討・実行を進めていく」
 ――国内外の市場を開拓する機能も期待されている。
――国内外の市場を開拓する機能も期待されている。「洋上風力発電所、EV関連など新エネルギー分野や高機能材分野をメーンターゲットとし、国内・海外という切り分けではなく、需要地あるいは顧客立地による新規開拓を推進する。国内では電力会社向け新エネルギー対応燃料貯蔵タンク向けなどチタンの需要開拓にも注力する」
――北米、インドは市場開拓を急ぐ必要がある。
「北米では、先ほど述べた通り、運転資金も含めれば過去最大の投資となる電磁鋼板用のコイルセンターをメキシコで建設中。メキシコではアグアスカリエンテス・スチール・コイルセンターが稼働している。米国ではケンタッキー・スチールセンターがケンタッキー州とテネシー州でコイルセンター事業を展開。今後も日本製鉄の海外戦略と同期化して市場開拓を進めていく」
――需要の伸びが期待されるインド市場対策は。
「ニムラナ・スチール・サービスセンターがラジャスタン州でコイルセンター機能を発揮しているが、チェンナイ近郊のスリシティーで第2工場を稼働させた。今後はEVをはじめとする現地の製造業向け需要に対応する電磁鋼板などハイエンド材の輸出拡大を狙っていく。現地の鉄鋼メーカーとは副原料などの取引を通じた関係強化も図っていく」
――中国は需要構造変化への対応を迫られている。
「上海、天津、深圳、東莞、蘇州でコイルセンター事業を展開しており、子会社化する電機資材が加工拠点を持つ。現地の日系需要家の動向、日本製鉄の戦略を見極めながら機能の集約・強化策を検討していく」
――ASEANについては。
「タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、シンガポール、バングラデシュなどでコイルセンター、線材加工事業などを幅広く展開している。タイを中心に各国拠点の横連携をさらに進化させ、地産地消化を促進し、地域需要を面で取り込んでいく。フィリピンは駐在員事務所を現地法人に格上げし、拡大が期待されるインフラ・エネルギー分野の現地需要を捕捉していく」
――人材戦略も重要なテーマとなる。
「最大の財産が『人』。人材の確保と能力発揮を最重要課題の一つとして取り組んでいる。事業規模を国内外で拡大しており、多様な人材を受け入れ、それぞれの事業領域で、個々人が最大限に力を発揮できる環境を整備していく」
――採用方針は。
「インターンシップなどの拡充を進めながら、将来の成長に向けた新卒採用、中長期経営計画に基づく中途採用を安定的に行っている。新卒採用と中途採用の比率を7対3から6対4に設定しており、今年は新卒50人、中途で35人程度を採用した。新卒の総合職採用における女性比率の目標を3割超に定めて重点的に取り組んでおり、近年は10-30%強で推移している」
――社内コミュニケーション強化策については。
「まずは年次別研修や若手対象の育成面談制度をはじめコミュニケーション活性化に取り組んでいる。教育研修の充実等の人材投資の拡大、処遇改善も進めている。また若手・中堅社員による選抜型キャリアデベロップメント研修を通じて、社員が自らのキャリア成長を図るために必要な仕組みや制度を経営陣に提案し、成果発表することも予定している」
――長期にわたって働いてもらう仕掛けも必要。
「社員が多様な経験を積めるよう、複数部門をローテーションする仕組みを検討している。企業としての持続的成長の機会を逃さないためには、様々な役割を担う社員が、広い視野と高い感性、そして何よりも成長への意欲を持つことが重要。そうした人材を育成するための施策を検討・実行していく」
――処遇を大幅に改善する。
「24年度は組合員一人あたり3万円、約10%のベースアップを実施する。賞与は3年連続過去最高益を達成した成果に報いるため労働組合の要求に満額回答した。総合職の初任給も26万円から30万円に引き上げる」
――「2024年問題」が深刻化しており、物流効率化も重要なテーマとなっている。
「運転手の待機時間ルール遵守、契約外付帯作業の廃止徹底に向けて、23年6月に行政より公表されたガイドラインに沿ってグループ企業の検証を行ったが、大きな問題がないことを確認している。グループ会社を含めた法規制への対応を強化するとともに、日本製鉄、日鉄物流等の日本製鉄グループ一貫物流連携の枠組みの中で、検討・協議を進めていく」
――日本製鉄の子会社となり、戦略的連携によるシナジーの発揮が期待されている。
「日本製鉄は将来にわたって日本の産業競争力を支える『総合力世界ナンバーワンの鉄鋼メーカー』を目指している。日鉄物産は日本製鉄グループの中核商社としてサプライチェーンにおける流通の役割を担ってきたが、子会社になったことでより高い次元で情報や営業戦略を共有し、グループ内のノウハウやインフラを最大限に活用しながら競争力強化を図ることが可能になった。『商社機能の日本製鉄グループでの効率化・強化』『営業ノウハウ・インフラを一体活用した直接営業力の強化』『サプライチェーンのさらなる高度化、新たなビジネスモデルの構築』をテーマに掲げ、シナジーを最大限に発揮していく」
――次期中計に向けての課題と展望、日本製鉄グループの中核商社としての2030年のあり姿を聞きたい。
「日本製鉄とのシナジーの最大発揮と当社独自戦略の完遂によって、数年内の600億円超の実力利益の確保を目指す。それを達成した段階で1000億円規模の利益達成に向けたビジョンを描いていきたい。主軸の鉄鋼事業を中軸とし、グループ内で異彩を放つ産機・インフラ、食糧、繊維の収益性の高い3事業を展開する日本製鉄グループの中核商社としてプレゼンスを高めていく」
――統合以来最大の処遇改善を実施した。
「人材の確保と育成、社員の能力の最大発揮は経営の最重要課題の一つであり、『人への投資』を積極的に推進し、社員の成長に資する人事施策制度を引き続き検討していく。労使一体となって、将来の連結経常利益1000億円規模の達成に向けたビジョンを描いていく」(谷藤 真澄)














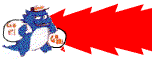
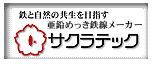
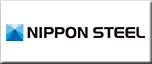
















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ