2024年6月19日
商社の経営戦略―加速する脱炭素・市場開拓―/阪和興業 中川洋一社長/金属資源リサイクル クローズドループ構築/グリーン鋼材、欧州で拡販強化
――2024年3月期の連結経常利益は前期比25%減の482億円だった。
「景気の先行き不透明感を背景に鋼材やスクラップの需要が減少し、鉄鋼や非鉄金属、原油などの商品相場が低迷したことから売上高は9%減の2兆4319億円にとどまった。その一方で販管費が9%増の701億円に膨らみ、営業利益は22%減の497億円に後退。プライマリーメタル関連事業の配当収入や持分法利益の減少なども重なり、経常利益は減少幅が拡大した。在庫・為替評価など一過性のマイナス要因があり、実力ベースの経常利益は500億円を超えている」
――主力の鉄鋼は経常利益が10%減の256億円だった。
「住宅着工戸数の減少などを背景に鋼材の取扱量が減少し、工事案件の見積もりミスで採算が悪化したことも響いた」
――鉄鋼の取り扱い数量は。
「連結合計が111万トン減の1348万トン。単体が60万トン減の930万トン、グループ会社は51万トン減の418万トン。国内が43万トン減の867万トン、海外は68万トン減の481万トンだった」
 ――今期は経常利益が600億円に回復する見通し。
――今期は経常利益が600億円に回復する見通し。
「経営環境が大きく改善するとは見ていない。プライマリーメタル、エネルギー・生活資材の更なる成長、食品の回復を見込み、投資の収益化を図り、リスクマネジメントを徹底することで、まずは600億円台を目指す」
――第10次中期経営計画(23-25年度)では経常利益700億円を目指している。
「前中計期間の経常利益は、20年度288億円、21年度627億円、22年度642億円で、30年ビジョンとして掲げた500億円も超過達成した。今中計のメーンテーマである『経営基盤の強化』『事業戦略の発展』『投資の収益化』を推進し、来期は最高益の更新を見込む」
――財務面ではネットDER1・0倍以下などの目標を掲げている。
「前期はコマーシャル・ペーパーの償還などを進め、有利子負債を155億円減の3654億円に圧縮し、ネットDERは1・0倍から0・8倍に改善した。前中計期間から利益剰余金を積み上げてきた結果、前期末の自己資本は480億円増の3512億円となり、自己資本比率も3・9ポイントアップの30・1%に上昇した」
――純利益は25%減の384億円だったが、一株当たりの期末配当を85円から100円(前年同期80円)に上方修正し、年間配当を185円(前期130円)に引き上げた。
「今中計では、株主還元強化策として、新たにDOE(株主資本配当率、配当総額÷期首株主資本)を指標に導入し、2・5%を下限に累進的配当を実施する方針を打ち出している。期首の株主資本が2708億円、発行済株式総数が4233万株で、年間配当185円はDOE2・7%。今期は中間期105円、期末105円の年間210円配当を予想しており、DOEは2・8%に上昇する」
――自己株式取得も実施する。
「前期は特別利益で、政策保有株式などの売却益48億円を計上した。そこで得たキャッシュの一部を株主への利益還元の一環として20億円、40万株を上限とする自己株式取得を決めた」
――連結純資産比率20%未満を目指す政策保有株式の売却は続けるのか。
「政策保有株保有残高の連結純資産比率は、23年3月末が21・7%、157銘柄だった。24年3月末は19・6%、129銘柄で、決議済みの未売却銘柄もある。ROE12%以上を目標に資本効率の向上に取り組んでおり、政策保有株式の売却についてはその保有意義や市場環境、収益状況を見ながら削減を進める」
――東商プライム上場企業はPBR1倍以上を求められている。
「株価は23年9月末が4745円、12月末が4995円で、本年3月末は5930円だった。足元は6500円前後で推移し、PBRは0・8倍程度まで上昇している。PBR1倍以上は、株価を9000円近くに引き上げる必要がある」
――日本のマイナス金利が解除された。
「キャッシュフローの改善を受けて、有利子負債の圧縮を進めている。金利上昇を見越して、利益率をより意識した経営を推進する」
 ――格付けの見直しは。
――格付けの見直しは。
「JCRは23年10月、『A-』から『A』に格上げされた。前期は経常利益500円の目標に未達だったが、自己資本比率が30%を超え、ネットDERも0・8倍に改善している。今期は『A-』に据え置かれたR&Iも格上げされるよう経営方針を丁寧に説明していく」
――経常利益1000億円への持続的成長に向けて、3年間800億円の投融資を計画する。
「前中計は3年間500億円の計画を大きく超える628億円の投融資を実行した。今中計はネットDER1・0倍以下を目標として財務規律を維持しながら、資産の入れ替えも進めつつ、配当後の連結基礎営業キャッシュフロー内で800億円規模の投融資を行う。初年度にあたる前期は国内グループ会社の自動・省力化など設備更新投資が中心で、新基幹システムを含めて上期累計が82億円、通期実績は156億円だった」
――意志決定ベースでは投融資を積極的に推進している。
「前期に意志決定したシンクスの買収や大和工業のインドネシア形鋼事業への出資は今期実施予定であり、鉄鋼に加えて、二次電池の資源確保、リサイクル、食品の事業拡大など幅広く、数多くの投融資案件を検討中で、3年間の累計は800億円を超える可能性もある。政策保有株など資産の入れ替えを進めつつ、リスクを見極めて優先順位もつけながら、攻めと守りをバランスよく実行していく」
――シンクスの買収について。
「木材加工機、鋼材加工設備を製造するシンクスを100%子会社化する。本年2月に株式譲渡契約を締結した。公正取引委員会の審査結果待ちで、おそらく上期中にはクロージングできるだろう。シンクスは高機能で、特徴ある加工設備をラインアップしている。人手不足や物流問題で設備の自動化、省力化ニーズが高まる中、シンクスの買収で不足していた技術面やメンテナンス機能をまとめて入手し、産業機械ビジネスを大きく発展させる。住宅建材分野における鋼材・木材の拡販でもシナジーを追求していく」
――脱炭素化への商社機能強化策として、日本最大の金属リサイクル事業を目指している。
「昭和メタル、正起金属加工、阪和メタルズ、日興金属がレアメタル、アルミ缶、アルミサッシ、ステンレス、銅線などのリサイクル事業を全国各地で展開している。二次電池や太陽光電池のリサイクルの事業化も視野に入れつつ、販売先を含めたクローズドループの構築を進めている」
――鉄スクラップの調達力を強化する。
「国内ではグループ会社、納入先からのリターンスクラップ回収・調達量の拡大を急いでいる。製鋼原料部が手掛けるビル解体や風力発電設備など大型構造物の解体事業からの鉄・非鉄スクラップの調達量も増やしていく」
――直接還元鉄ソースについては。
「東南アジア等における直接還元鉄プラントからのHBIの調達を広げて、日本の鉄鋼メーカーに供給する準備を進めている」
――海外でも金属リサイクル事業を強化する。
「オランダでは三菱マテリアルとEスクラップのリサイクル事業を拡充している。欧州、東南アジアで集荷・回収機能を大きく広げていく」
――祖業でもある船舶解体ビジネスへの関心は。
「鉄・非鉄スクラップを幅広く扱い、販売先を確保しているので、船舶解体由来のリサイクルは伸ばす余地がある。先行してバングラデシュで非鉄スクラップの調達網を広げている」
――リチウムイオンバッテリーのリサイクルに本格参入する。
「日本では電池スクラップの発生まで時間がまだかかりそうだが、米国や韓国では廃バッテリーや電池工場からの発生品が流通し始めているので、両国で先行して手を打っていく。韓国のSEBITCHEMと提携し、リチウムイオンバッテリーのリサイクル技術を活用し、廃材や廃バッテリーの集荷・供給、リサイクル分野で当社らしいクローズドループを形成していく」
――EV化の流れに変化が見られる。
「欧米ではEV化の勢いがスローダウンしているが、出遅れていた日系自動車メーカーにとっては、遅れを取り戻すチャンスとも言える。本田技研工業との二次電池用レアメタルの安定調達に向けた戦略的パートナーシップ契約も動き出す。米国は大統領選の結果でEV化の流れが停滞する可能性はあるが、長期的な大きな流れは変わらない。一時的な資源価格の下落は投資コストの低下などビジネスチャンスにつながる。正極材をメーンに資源の確保を続けてきたが、負極材、電池のリサイクルを含めて投資機会を窺っていく」
――バイオマス燃料ビジネスも強化する。
「東南アジアで調達するPKS(パーム椰子殻)、木質ペレットを国内の電力会社へ長期契約で納入する事業が順調に拡大している。PKS輸入は国内トップのシェアを伸ばしている。安定供給とフレート対策を目的とする専用船は、3隻目が3月に進水式を終え、年内に就航する」
 ――重量物の鉄鋼製品は、物流の効率化が求められている。
――重量物の鉄鋼製品は、物流の効率化が求められている。
「西日本はグループ会社の在庫・物流拠点を結び、配送効率化を追求している。大型形鋼は西日本からの輸送が課題だが、関東については習志野の阪和流通センター東京の水深12メートルの岸壁を有効に活用し、田中鉄鋼販売、阪和ダイサンの在庫・流通機能を活用することで全体の輸送効率を引き上げていく」
――国内では洋上風力発電ビジネスがこれから本格化する。
「風力発電関連ビジネスには国内・海外ともに力を入れていく。まず洋上風力発電のタワー/モノパイル向け母材の厚板で、国内・海外での拡販を進める。国内はグループ会社の加工・物流・製作機能を結びながら、付帯設備を含めた風力発電所向けのサプライチェーンを構築していく」
――グリーン鋼材の市場開拓について。
「プレミアムが認められる市場の形成が必要であるが、販売を強化していく」
――欧州では、ロンドン支店を英国現地法人化した。
「欧州・中東・アフリカ総代表を務める竹迫常務をロンドンに常駐させ、オランダのアムステルダムにも営業担当の佐原理事を新たに配置した。地政学的リスクやADなどによるサプライチェーンの分断も視野に入れつつ、グリーン鋼材の輸入販売に加えて、現地材の調達先を増やしながら欧州の市場開拓を進めていく」
――インドネシアでは既存の棒鋼・線材、鋼板に、形鋼のメーカー機能が加わる。
「現地の大手民営鉄鋼メーカー、GRP社が形鋼事業を分社化し、大和工業80%、阪和興業15%で株式を譲り受ける。5月末に株式譲渡が完了した。電炉・製鋼能力100万トン、圧延能力90万トンの大型プロジェクトになる」
――インドネシアは中国・徳龍鋼鉄との合弁、徳信鋼鉄が第3高炉の操業を開始した。
「スラウェシ島にある徳信鋼鉄は年産700万トン規模に拡大し、ビレット、丸棒、線材、スラブ、ホットコイルの供給体制を整えた。インドネシアは一人当たりの鉄鋼消費量が60キロと発展途上で、首都移転計画に伴う電力、道路、港湾など社会インフラ整備が急務となっており、鉄塔や土木・建築関連需要が拡大を続ける。阪和インドネシアはローカル社員を含め240人規模になり、販売力を強化しており、棒鋼・線材、鋼板、形鋼の現地メーカー機能を拡大することでビジネスチャンスが大きく広がる」
――中国の青山実業グループとの現地ビジネスも拡大している。
「世界最大のステンレスメーカーとなった青山実業グループがスラウェシ島で展開するニッケル銑鉄、ステンレス精錬・圧延プロジェクトに参画し、原料調達から製品販売で協力している。中国最大のリサイクル企業であるGEM、世界最大の電池メーカーであるCATL子会社や青山実業との合弁事業で、リチウムイオン電池向けの高純度ニッケル・コバルト化合物を一貫生産するQMBニューエナジー・マテリアルズが本格稼働を開始しており、『東南アジアに第二の阪和』戦略をさらに拡充していく」(谷藤 真澄)

「景気の先行き不透明感を背景に鋼材やスクラップの需要が減少し、鉄鋼や非鉄金属、原油などの商品相場が低迷したことから売上高は9%減の2兆4319億円にとどまった。その一方で販管費が9%増の701億円に膨らみ、営業利益は22%減の497億円に後退。プライマリーメタル関連事業の配当収入や持分法利益の減少なども重なり、経常利益は減少幅が拡大した。在庫・為替評価など一過性のマイナス要因があり、実力ベースの経常利益は500億円を超えている」
――主力の鉄鋼は経常利益が10%減の256億円だった。
「住宅着工戸数の減少などを背景に鋼材の取扱量が減少し、工事案件の見積もりミスで採算が悪化したことも響いた」
――鉄鋼の取り扱い数量は。
「連結合計が111万トン減の1348万トン。単体が60万トン減の930万トン、グループ会社は51万トン減の418万トン。国内が43万トン減の867万トン、海外は68万トン減の481万トンだった」
 ――今期は経常利益が600億円に回復する見通し。
――今期は経常利益が600億円に回復する見通し。「経営環境が大きく改善するとは見ていない。プライマリーメタル、エネルギー・生活資材の更なる成長、食品の回復を見込み、投資の収益化を図り、リスクマネジメントを徹底することで、まずは600億円台を目指す」
――第10次中期経営計画(23-25年度)では経常利益700億円を目指している。
「前中計期間の経常利益は、20年度288億円、21年度627億円、22年度642億円で、30年ビジョンとして掲げた500億円も超過達成した。今中計のメーンテーマである『経営基盤の強化』『事業戦略の発展』『投資の収益化』を推進し、来期は最高益の更新を見込む」
――財務面ではネットDER1・0倍以下などの目標を掲げている。
「前期はコマーシャル・ペーパーの償還などを進め、有利子負債を155億円減の3654億円に圧縮し、ネットDERは1・0倍から0・8倍に改善した。前中計期間から利益剰余金を積み上げてきた結果、前期末の自己資本は480億円増の3512億円となり、自己資本比率も3・9ポイントアップの30・1%に上昇した」
――純利益は25%減の384億円だったが、一株当たりの期末配当を85円から100円(前年同期80円)に上方修正し、年間配当を185円(前期130円)に引き上げた。
「今中計では、株主還元強化策として、新たにDOE(株主資本配当率、配当総額÷期首株主資本)を指標に導入し、2・5%を下限に累進的配当を実施する方針を打ち出している。期首の株主資本が2708億円、発行済株式総数が4233万株で、年間配当185円はDOE2・7%。今期は中間期105円、期末105円の年間210円配当を予想しており、DOEは2・8%に上昇する」
――自己株式取得も実施する。
「前期は特別利益で、政策保有株式などの売却益48億円を計上した。そこで得たキャッシュの一部を株主への利益還元の一環として20億円、40万株を上限とする自己株式取得を決めた」
――連結純資産比率20%未満を目指す政策保有株式の売却は続けるのか。
「政策保有株保有残高の連結純資産比率は、23年3月末が21・7%、157銘柄だった。24年3月末は19・6%、129銘柄で、決議済みの未売却銘柄もある。ROE12%以上を目標に資本効率の向上に取り組んでおり、政策保有株式の売却についてはその保有意義や市場環境、収益状況を見ながら削減を進める」
――東商プライム上場企業はPBR1倍以上を求められている。
「株価は23年9月末が4745円、12月末が4995円で、本年3月末は5930円だった。足元は6500円前後で推移し、PBRは0・8倍程度まで上昇している。PBR1倍以上は、株価を9000円近くに引き上げる必要がある」
――日本のマイナス金利が解除された。
「キャッシュフローの改善を受けて、有利子負債の圧縮を進めている。金利上昇を見越して、利益率をより意識した経営を推進する」
 ――格付けの見直しは。
――格付けの見直しは。「JCRは23年10月、『A-』から『A』に格上げされた。前期は経常利益500円の目標に未達だったが、自己資本比率が30%を超え、ネットDERも0・8倍に改善している。今期は『A-』に据え置かれたR&Iも格上げされるよう経営方針を丁寧に説明していく」
――経常利益1000億円への持続的成長に向けて、3年間800億円の投融資を計画する。
「前中計は3年間500億円の計画を大きく超える628億円の投融資を実行した。今中計はネットDER1・0倍以下を目標として財務規律を維持しながら、資産の入れ替えも進めつつ、配当後の連結基礎営業キャッシュフロー内で800億円規模の投融資を行う。初年度にあたる前期は国内グループ会社の自動・省力化など設備更新投資が中心で、新基幹システムを含めて上期累計が82億円、通期実績は156億円だった」
――意志決定ベースでは投融資を積極的に推進している。
「前期に意志決定したシンクスの買収や大和工業のインドネシア形鋼事業への出資は今期実施予定であり、鉄鋼に加えて、二次電池の資源確保、リサイクル、食品の事業拡大など幅広く、数多くの投融資案件を検討中で、3年間の累計は800億円を超える可能性もある。政策保有株など資産の入れ替えを進めつつ、リスクを見極めて優先順位もつけながら、攻めと守りをバランスよく実行していく」
――シンクスの買収について。
「木材加工機、鋼材加工設備を製造するシンクスを100%子会社化する。本年2月に株式譲渡契約を締結した。公正取引委員会の審査結果待ちで、おそらく上期中にはクロージングできるだろう。シンクスは高機能で、特徴ある加工設備をラインアップしている。人手不足や物流問題で設備の自動化、省力化ニーズが高まる中、シンクスの買収で不足していた技術面やメンテナンス機能をまとめて入手し、産業機械ビジネスを大きく発展させる。住宅建材分野における鋼材・木材の拡販でもシナジーを追求していく」
――脱炭素化への商社機能強化策として、日本最大の金属リサイクル事業を目指している。
「昭和メタル、正起金属加工、阪和メタルズ、日興金属がレアメタル、アルミ缶、アルミサッシ、ステンレス、銅線などのリサイクル事業を全国各地で展開している。二次電池や太陽光電池のリサイクルの事業化も視野に入れつつ、販売先を含めたクローズドループの構築を進めている」
――鉄スクラップの調達力を強化する。
「国内ではグループ会社、納入先からのリターンスクラップ回収・調達量の拡大を急いでいる。製鋼原料部が手掛けるビル解体や風力発電設備など大型構造物の解体事業からの鉄・非鉄スクラップの調達量も増やしていく」
――直接還元鉄ソースについては。
「東南アジア等における直接還元鉄プラントからのHBIの調達を広げて、日本の鉄鋼メーカーに供給する準備を進めている」
――海外でも金属リサイクル事業を強化する。
「オランダでは三菱マテリアルとEスクラップのリサイクル事業を拡充している。欧州、東南アジアで集荷・回収機能を大きく広げていく」
――祖業でもある船舶解体ビジネスへの関心は。
「鉄・非鉄スクラップを幅広く扱い、販売先を確保しているので、船舶解体由来のリサイクルは伸ばす余地がある。先行してバングラデシュで非鉄スクラップの調達網を広げている」
――リチウムイオンバッテリーのリサイクルに本格参入する。
「日本では電池スクラップの発生まで時間がまだかかりそうだが、米国や韓国では廃バッテリーや電池工場からの発生品が流通し始めているので、両国で先行して手を打っていく。韓国のSEBITCHEMと提携し、リチウムイオンバッテリーのリサイクル技術を活用し、廃材や廃バッテリーの集荷・供給、リサイクル分野で当社らしいクローズドループを形成していく」
――EV化の流れに変化が見られる。
「欧米ではEV化の勢いがスローダウンしているが、出遅れていた日系自動車メーカーにとっては、遅れを取り戻すチャンスとも言える。本田技研工業との二次電池用レアメタルの安定調達に向けた戦略的パートナーシップ契約も動き出す。米国は大統領選の結果でEV化の流れが停滞する可能性はあるが、長期的な大きな流れは変わらない。一時的な資源価格の下落は投資コストの低下などビジネスチャンスにつながる。正極材をメーンに資源の確保を続けてきたが、負極材、電池のリサイクルを含めて投資機会を窺っていく」
――バイオマス燃料ビジネスも強化する。
「東南アジアで調達するPKS(パーム椰子殻)、木質ペレットを国内の電力会社へ長期契約で納入する事業が順調に拡大している。PKS輸入は国内トップのシェアを伸ばしている。安定供給とフレート対策を目的とする専用船は、3隻目が3月に進水式を終え、年内に就航する」
 ――重量物の鉄鋼製品は、物流の効率化が求められている。
――重量物の鉄鋼製品は、物流の効率化が求められている。「西日本はグループ会社の在庫・物流拠点を結び、配送効率化を追求している。大型形鋼は西日本からの輸送が課題だが、関東については習志野の阪和流通センター東京の水深12メートルの岸壁を有効に活用し、田中鉄鋼販売、阪和ダイサンの在庫・流通機能を活用することで全体の輸送効率を引き上げていく」
――国内では洋上風力発電ビジネスがこれから本格化する。
「風力発電関連ビジネスには国内・海外ともに力を入れていく。まず洋上風力発電のタワー/モノパイル向け母材の厚板で、国内・海外での拡販を進める。国内はグループ会社の加工・物流・製作機能を結びながら、付帯設備を含めた風力発電所向けのサプライチェーンを構築していく」
――グリーン鋼材の市場開拓について。
「プレミアムが認められる市場の形成が必要であるが、販売を強化していく」
――欧州では、ロンドン支店を英国現地法人化した。
「欧州・中東・アフリカ総代表を務める竹迫常務をロンドンに常駐させ、オランダのアムステルダムにも営業担当の佐原理事を新たに配置した。地政学的リスクやADなどによるサプライチェーンの分断も視野に入れつつ、グリーン鋼材の輸入販売に加えて、現地材の調達先を増やしながら欧州の市場開拓を進めていく」
――インドネシアでは既存の棒鋼・線材、鋼板に、形鋼のメーカー機能が加わる。
「現地の大手民営鉄鋼メーカー、GRP社が形鋼事業を分社化し、大和工業80%、阪和興業15%で株式を譲り受ける。5月末に株式譲渡が完了した。電炉・製鋼能力100万トン、圧延能力90万トンの大型プロジェクトになる」
――インドネシアは中国・徳龍鋼鉄との合弁、徳信鋼鉄が第3高炉の操業を開始した。
「スラウェシ島にある徳信鋼鉄は年産700万トン規模に拡大し、ビレット、丸棒、線材、スラブ、ホットコイルの供給体制を整えた。インドネシアは一人当たりの鉄鋼消費量が60キロと発展途上で、首都移転計画に伴う電力、道路、港湾など社会インフラ整備が急務となっており、鉄塔や土木・建築関連需要が拡大を続ける。阪和インドネシアはローカル社員を含め240人規模になり、販売力を強化しており、棒鋼・線材、鋼板、形鋼の現地メーカー機能を拡大することでビジネスチャンスが大きく広がる」
――中国の青山実業グループとの現地ビジネスも拡大している。
「世界最大のステンレスメーカーとなった青山実業グループがスラウェシ島で展開するニッケル銑鉄、ステンレス精錬・圧延プロジェクトに参画し、原料調達から製品販売で協力している。中国最大のリサイクル企業であるGEM、世界最大の電池メーカーであるCATL子会社や青山実業との合弁事業で、リチウムイオン電池向けの高純度ニッケル・コバルト化合物を一貫生産するQMBニューエナジー・マテリアルズが本格稼働を開始しており、『東南アジアに第二の阪和』戦略をさらに拡充していく」(谷藤 真澄)














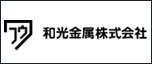
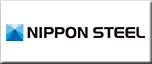

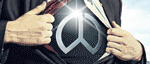















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















