2024年6月18日
商社の経営戦略―加速する脱炭素・市場開拓―/伊藤忠丸紅鉄鋼 石谷誠社長/電磁鋼板の加工・流通強化/インド機能拡充、車需要捉える
――第7次中期経営計画(2021-23年度)は連結純利益目標200億円を掲げ、21年度626億円、22年度955億円、23年度803億円と超過達成した。実力ベースの利益など定量面の総括から。
「利益水準は、新型コロナウイルス前後の需給ギャップ、円安に下支えられた追風参考記録であり、鋼材市況や為替などアップサイドの要因を除いた実力は400億円と分析している。アップサイドの要因を除き主な事業収益力を勘案した純利益を基礎収益力と定義しているが、2001年の発足後20年間の平均が200億円。米国の建材事業に代表される事業ポートフォリオを強みとし、既存事業の収益改善や追加投資効果も引き出しながら、この3年間で200億円を積み上げることができた」
――3年間の連結純利益は平均800億円で、400億円を実力とするのは慎重過ぎないか。
「為替は発足後20年間の平均が1ドル110円、直近2年間は140円台で、北米など海外の鋼材・鋼管市況も歴史的高水準にあった。利益は海外事業や外貨建取引の割合が多いため、円安と海外市況の影響が大きい。数多くの要素を組み合わせて実力値を分析している」
――定性面では「備える、高める、鍛える」の施策に取り組んだ。
「コロナ禍からの回復時期であったため、企業としての耐性を引き上げ、復元力を高めることに注力してきた。『備える』は、収益基盤の再強化をメーンテーマに掲げ、『収益力強化委員会』がトン当たりの原価や販管費などの分析を行い、資産効率や資金効率の改善を推進してきた。その結果、本社、グループ会社全体に新たな視点でのコスト意識が浸透。成長が見込めない分野からのイグジット、低収益事業における設備統廃合や生産性の向上に取り組み、約100社ある事業会社の黒字化比率が前中計の80%台から92%まで上昇。連結ベースの基礎収益力を400億円まで引き上げることができた」
――「鍛える」については。
「人的資源の底上げをメーンテーマに個々人のスキル向上、多様なプロ集団の形成に取り組み、社員の働き甲斐と会社の発展の好循環を目指してきた。デジタル研修の一環として、ITツールを活用した業務効率化を競い合う社内コンテスト『BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)CUP』を3年間継続したことで、各本部・部署における自律型のBPR活動が軌道に乗った。今後は社内・グループ内の横展開、さらに取引先の業務効率化へと効果を広げていく」
――「高める」は。
「北米の建材事業、鋼管事業への収益依存度が高いが、収益基盤をさらに強化するため、地産地消分野での投資を行った。また、『次世代ビジネス検討プロジェクト』を立ち上げて、洋上風力発電や太陽光、地熱などカーボンニュートラル関連の需要捕捉、市場開拓に努めてきたが、緒に就いたばかりで次期中計の継続課題となる」
――投融資の実績を。
「コロナ禍が広がり続けていたため年間300億円の想定でスタートし、3年間の実績は約470億円だった。カナダの鋼管問屋トライマークの出資比率を50%から100%に引き上げた。米国では、USスチールとワージントン・インダストリーズの薄板サービスセンター合弁事業からミシガン州のジャクソン工場を買収し、MISAスペシャルティ・プロセシングを新設した。英国では建材向け鋼材の加工・販売ネットワークを全国展開するバークレイ・アンド・マシソンを買収。国内では一部出資するモーターコア用の精密金型やコアを製造する黒田精工とともに、紅忠コイルセンター関東の常陸事業所内にモーターコア製造合弁の紅忠黒田ラミネーションを設立した」
――本年度の経営課題は。
「経営環境は悪化すると想定しており、成長戦略投資を先行させるため、収益面で本年度は端境期となるが、2030年に向けて基礎収益力の強化に注力する」
――2030年以降を見据えた長期ビジョンを策定した。
「新たな時代を担う経営幹部層の早期育成を本格化し、圧倒的な存在感がある利益規模の、自立した会社に成長すべく、『2030年代を目処に、鉄鋼流通におけるグローバルトップ』となることを目指す」
――第8次中期計画(24ー26年度)をスタートした。
「長期ビジョン実現に向けてのロードマップを確実に軌道に乗せるため、第8次中計の3年間で基礎収益力をさらに200億円規模で上積みする。決して容易ではなく、これまでのトレードビジネスの延長では実現不可能であり、ビジネスモデルを大きく転換させていく。当社が得意とするトレードで培った知見と人脈を活かして、戦略的な投資を通じ収益拡大を図っていく」
――基本方針を。
「キャッチフレーズは『トレードXインベストメント-Powering the future toward 2030-』。トレードから投資への単純な転換ではなく、トレードと投資を掛け合わせる、あるいはトレードからの投資案件を発掘する、との意味を込めている。トレードで培ってきた知見と顧客基盤をもとに、多くのチャンスを創出した上で、厳選して実行していく」
――社員も新たなステージにシフトする。
「目の前の商売にとどまらず、目線を上げて取引先の経営層と信頼関係を構築し、市場環境や需要構造に関する議論を行いながら、事業出資、合弁事業などの機会を発掘し、創出していく。長期ビジョンと第8次中計の目標を全世界のグループ社員と共有し、ベクトルを一致させて高みを目指していく」
――高収益が続き、内部留保は5000億円を超え、格付けが「A+」に格上げされ、自己資本比率も30%台に乗せたが、総資産利益率(ROA)は4%台にとどまる。
「投融資の枠を設けず、多くの案件を発掘、創出し、『鉄鋼流通におけるグローバルトップ』を実現するための成長投資を積極展開していく」
 ――定性面の重点課題は。
――定性面の重点課題は。
「『基礎収益力の強化』、『DXやGXをリードするトレード機能の強化』、『次世代の経営を担う人材の育成』の三つが柱となる」
――基礎収益力強化について。
「成長投資を確実に推進するため、各営業本部に4月1日付で『開発室』を新設し、それぞれ専任者を配置。併せて各営業本部、海外現地法人の投資案件の発掘をバックアップする『投資推進チーム』を事業総括部に設置した。この新設チームにM&Aの専門性を持った社外人材を迎え入れて事業投資センスを磨き上げ、投資案件の精査と仕立てのレベルアップに加え、買収後の支援モデルも確立し、基礎収益力を引き上げていく」
――ターゲット分野を。
「大きく四つあって、一つ目が鉄鋼流通事業、つまり同業者。二つ目が建材など川下の取引先。三つ目がサプライチェーンの機能補完につながる事業、四つ目がカーボンニュートラル関連。いずれも国内外でビジネスチャンスを追求していく」
――重点地域は。
「北米、欧州、豪州、日本の先進国に加えて、インド、中東、アフリカなど成長市場でも案件を発掘していく」
――国内の流通事業強化のスタンスを。
「シェアや数量を追い求めるのではなく、同業他社とも協力しながら、加工・流通の効率性を抜本的に改善し、勝ち残っていく」
――経営人材育成については。
「創業20周年を過ぎてMISI入社の社員が約8割を占め、国内外の事業会社は100社を超え、本社・グループ会社の経営人材育成が大きな課題になっている。一般的に新卒者の離職者は3年内で3割とされる中、MISIは数%にとどまっているが、意欲ある優秀な人材が流出するケースはある。商社ビジネスの醍醐味や将来機会を理解してもらうため、経営陣を含め世代を超えた交流の機会を増やしている。またストレッチ・アサインメント制度を導入し、海外事業会社の社長ポジション、海外現地法人など17拠点の責任者のポジションを若手育成ポストに選定。課長になる前の30歳台の社員を派遣し、経験とセンスを身につけさせている。私達の世代は30歳台に海外コイルセンターの社長に就任し、大変な苦労を重ねたが、とても貴重な経験になっている。有望な若手がいれば、20歳台後半でもチャンスを与えていく」
――留学制度も拡充する。
「世界で戦える人材を育成していく。課長級以上の役職者を全員、短期のビジネススクールに派遣する。国内に限らず、米国のハーバード大学、ノースウエスタン大学、ペンシルベニア大学、スイスのIMDなど世界トップクラスの学校へ送り込んでいく。若手に配慮し、シンガポールのINSEADも対象に加えた」
――商社の脱炭素対応機能として、電磁鋼板の加工・流通事業強化が求められている。
「世界的なモーターコアメーカーであるイタリアのユーロ・グループと中国にEV駆動用のモーターコア合弁事業を運営しており、メキシコにあるユーロの加工・物流事業に一部出資するなど協業を広げている。日本ではモーターコア製造合弁の紅忠黒田ラミネーションを設立した。ユーロ・グループ、黒田精工との三者アライアンスを強化しながら、伸びるEV関連需要をしっかり捕捉していく。中国では大連藤洋、嘉興紅忠が電磁鋼板を加工している。インドではデリー近郊で無方向性電磁鋼板のモーターコア製造事業を行っている。インド、北米は需要の伸びを見極めながら次の手を打っていく」
――自動車はハイテン鋼板、アルミパネルの需要も伸びていく。
「米国ではミシガンRSDCがハイテン、車体用アルミ材をGM向けに供給しており、大型ピックアップEV車用のアルミブランク材が増えている。中国では武漢紅忠のアルミブランク加工機能が評価されている」
――昨年4月に設立した「インキュベーション室」の取り組みを。
「脱炭素社会・デジタル社会において取引先が求めるサービスを提供していく。物流や人手不足などの問題を抱える国内の鋼材流通にいて新たな機能を発揮するための試行錯誤を重ねている。事業会社に物流管理統括者を置いて、物流事業者との契約内容の点検、待機時間や荷役作業時間など実態の見える化を推進。輸送効率を高めるための荷主と輸送業者がデジタルでつながるプラットフォームを開発し、鋼管問屋のニッコーなどで実証試験を続けている」
――グリーンスチールの拡販もテーマ。
「プレミアムの理解活動、拡販に取り組んでいる。来年5月に本社を東京ミッドタウン八重洲に移転するが、新調するオフィス家具類にグリーンスチールの使用を検討している」
――洋上風力発電プロジェクトが国内でも本格化する。
「先行する中国のプロジェクトに参画し、ノウハウを積み重ねている。鋼材、部材加工、組み立て、物流、設置など大型プロジェクトとなるので鉄鋼総合商社としての機能を発揮できる。株主会社、鉄鋼メーカーとともに積極的に関与していく」
――インドなど海外の市場開拓機能も期待されている。
「アジア・大洋州支配人補佐として、インド総代表のポジションを新設した。現地の需要家など取引先のトップと直接、面談して情報交換し、ニーズを収集することでタイムリーに商社機能を発揮していく。インド国内では、独自のモーターコア製造事業に加えて、JSWスチールとはプネ、チェンナイ、デリー、アーメダバードの4拠点で自動車対応の薄板、電磁鋼板のコイルセンターを展開。マグナム・ストリップ&チューブとは二輪・四輪用のメカニカルチューブ製造拠点やコイルセンターを共同で運営。カパロ・エンジニアリングとは自動車用TWBの合弁事業を運営している。総代表の機能を引き出しながら、事業を広げていく」
――北米は建材、鋼管、薄板の安定した収益基盤を拡充する。
「建材は、建築用スチールフレームで全米4割強のシェアを握るクラークウエスタン・ディートリック・ビルディングシステムズ(CDBS)、住宅の屋根・壁用アルミ・スチールサイディングを得意とするクオリティ・エッジを通して市場を深耕していく。鋼管は、マルベニ・イトチュウ・チューブラーズ・アメリカがヒューストンに本社を構え、油井管、ラインパイプ、特殊管のマスターディストリビューター機能を担い、油井管問屋のスーナー、CTAP、カナダのトライマークの100%子会社が北米市場をカバーしている。薄板は、MISAメタルプロセシングがポートランド、ルイビル、フォレストの3拠点を展開し、ゼネラルモータース向けのパネル加工機能を担うRSDCミシガンも業容を拡大している。MISAスペシャルティ・プロセシングを加えて、自動車対応の薄板サービスセンターは5拠点となった。厚板溶断のMISAメタル・ファブリケーティングがルイビルにある。日本製鉄、JFEスチールの現地事業展開、大統領選挙の行方などをにらみながら、強い事業基盤をさらに強化していく。メキシコはアグアスカリエンテス州、グアナファト州に薄板サービスセンターがあり、丸一鋼管と自動車部品事業も展開している」
――中東、アフリカ市場へのアプローチは。
「中東、アフリカは重要エリア。欧州会社社長が欧阿支配人を兼務し、得意とするトレード機能を発揮しながら市場開拓を進めていく。欧州は脱炭素関連規制も見据えて、新たなアプローチを展開する。英国とUAEに鋼管問屋があり、スペインでは油井管のネジ切り加工を行っている。UAEにはJFEスチールとの大径管製造合弁事業もある。英国のバークレイ・アンド・マシソンの買収効果を引き出しながら、次の一手を検討していく」
――豪州は脱炭素関連ビジネスの広がりが期待される。
「厚板切断加工のトータル・スチール・オブ・オーストラリア、鋼管販売のマルベニ・イトチュウ・チューブラーズ・オセアニア、現地法人の3社が事業を展開しており、それぞれ10億-30億円規模の利益を安定的に稼いでいる。人口密度は低く、成熟国ではあるが、金属・エネルギー資源国としての成長が期待でき、水素・ガス、CCUSなどのプロジェクトも数多く計画されており、株主会社と情報交換しながらビジネスチャンスを開拓していく」(谷藤 真澄)

「利益水準は、新型コロナウイルス前後の需給ギャップ、円安に下支えられた追風参考記録であり、鋼材市況や為替などアップサイドの要因を除いた実力は400億円と分析している。アップサイドの要因を除き主な事業収益力を勘案した純利益を基礎収益力と定義しているが、2001年の発足後20年間の平均が200億円。米国の建材事業に代表される事業ポートフォリオを強みとし、既存事業の収益改善や追加投資効果も引き出しながら、この3年間で200億円を積み上げることができた」
――3年間の連結純利益は平均800億円で、400億円を実力とするのは慎重過ぎないか。
「為替は発足後20年間の平均が1ドル110円、直近2年間は140円台で、北米など海外の鋼材・鋼管市況も歴史的高水準にあった。利益は海外事業や外貨建取引の割合が多いため、円安と海外市況の影響が大きい。数多くの要素を組み合わせて実力値を分析している」
――定性面では「備える、高める、鍛える」の施策に取り組んだ。
「コロナ禍からの回復時期であったため、企業としての耐性を引き上げ、復元力を高めることに注力してきた。『備える』は、収益基盤の再強化をメーンテーマに掲げ、『収益力強化委員会』がトン当たりの原価や販管費などの分析を行い、資産効率や資金効率の改善を推進してきた。その結果、本社、グループ会社全体に新たな視点でのコスト意識が浸透。成長が見込めない分野からのイグジット、低収益事業における設備統廃合や生産性の向上に取り組み、約100社ある事業会社の黒字化比率が前中計の80%台から92%まで上昇。連結ベースの基礎収益力を400億円まで引き上げることができた」
――「鍛える」については。
「人的資源の底上げをメーンテーマに個々人のスキル向上、多様なプロ集団の形成に取り組み、社員の働き甲斐と会社の発展の好循環を目指してきた。デジタル研修の一環として、ITツールを活用した業務効率化を競い合う社内コンテスト『BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)CUP』を3年間継続したことで、各本部・部署における自律型のBPR活動が軌道に乗った。今後は社内・グループ内の横展開、さらに取引先の業務効率化へと効果を広げていく」
――「高める」は。
「北米の建材事業、鋼管事業への収益依存度が高いが、収益基盤をさらに強化するため、地産地消分野での投資を行った。また、『次世代ビジネス検討プロジェクト』を立ち上げて、洋上風力発電や太陽光、地熱などカーボンニュートラル関連の需要捕捉、市場開拓に努めてきたが、緒に就いたばかりで次期中計の継続課題となる」
――投融資の実績を。
「コロナ禍が広がり続けていたため年間300億円の想定でスタートし、3年間の実績は約470億円だった。カナダの鋼管問屋トライマークの出資比率を50%から100%に引き上げた。米国では、USスチールとワージントン・インダストリーズの薄板サービスセンター合弁事業からミシガン州のジャクソン工場を買収し、MISAスペシャルティ・プロセシングを新設した。英国では建材向け鋼材の加工・販売ネットワークを全国展開するバークレイ・アンド・マシソンを買収。国内では一部出資するモーターコア用の精密金型やコアを製造する黒田精工とともに、紅忠コイルセンター関東の常陸事業所内にモーターコア製造合弁の紅忠黒田ラミネーションを設立した」
――本年度の経営課題は。
「経営環境は悪化すると想定しており、成長戦略投資を先行させるため、収益面で本年度は端境期となるが、2030年に向けて基礎収益力の強化に注力する」
――2030年以降を見据えた長期ビジョンを策定した。
「新たな時代を担う経営幹部層の早期育成を本格化し、圧倒的な存在感がある利益規模の、自立した会社に成長すべく、『2030年代を目処に、鉄鋼流通におけるグローバルトップ』となることを目指す」
――第8次中期計画(24ー26年度)をスタートした。
「長期ビジョン実現に向けてのロードマップを確実に軌道に乗せるため、第8次中計の3年間で基礎収益力をさらに200億円規模で上積みする。決して容易ではなく、これまでのトレードビジネスの延長では実現不可能であり、ビジネスモデルを大きく転換させていく。当社が得意とするトレードで培った知見と人脈を活かして、戦略的な投資を通じ収益拡大を図っていく」
――基本方針を。
「キャッチフレーズは『トレードXインベストメント-Powering the future toward 2030-』。トレードから投資への単純な転換ではなく、トレードと投資を掛け合わせる、あるいはトレードからの投資案件を発掘する、との意味を込めている。トレードで培ってきた知見と顧客基盤をもとに、多くのチャンスを創出した上で、厳選して実行していく」
――社員も新たなステージにシフトする。
「目の前の商売にとどまらず、目線を上げて取引先の経営層と信頼関係を構築し、市場環境や需要構造に関する議論を行いながら、事業出資、合弁事業などの機会を発掘し、創出していく。長期ビジョンと第8次中計の目標を全世界のグループ社員と共有し、ベクトルを一致させて高みを目指していく」
――高収益が続き、内部留保は5000億円を超え、格付けが「A+」に格上げされ、自己資本比率も30%台に乗せたが、総資産利益率(ROA)は4%台にとどまる。
「投融資の枠を設けず、多くの案件を発掘、創出し、『鉄鋼流通におけるグローバルトップ』を実現するための成長投資を積極展開していく」
 ――定性面の重点課題は。
――定性面の重点課題は。「『基礎収益力の強化』、『DXやGXをリードするトレード機能の強化』、『次世代の経営を担う人材の育成』の三つが柱となる」
――基礎収益力強化について。
「成長投資を確実に推進するため、各営業本部に4月1日付で『開発室』を新設し、それぞれ専任者を配置。併せて各営業本部、海外現地法人の投資案件の発掘をバックアップする『投資推進チーム』を事業総括部に設置した。この新設チームにM&Aの専門性を持った社外人材を迎え入れて事業投資センスを磨き上げ、投資案件の精査と仕立てのレベルアップに加え、買収後の支援モデルも確立し、基礎収益力を引き上げていく」
――ターゲット分野を。
「大きく四つあって、一つ目が鉄鋼流通事業、つまり同業者。二つ目が建材など川下の取引先。三つ目がサプライチェーンの機能補完につながる事業、四つ目がカーボンニュートラル関連。いずれも国内外でビジネスチャンスを追求していく」
――重点地域は。
「北米、欧州、豪州、日本の先進国に加えて、インド、中東、アフリカなど成長市場でも案件を発掘していく」
――国内の流通事業強化のスタンスを。
「シェアや数量を追い求めるのではなく、同業他社とも協力しながら、加工・流通の効率性を抜本的に改善し、勝ち残っていく」
――経営人材育成については。
「創業20周年を過ぎてMISI入社の社員が約8割を占め、国内外の事業会社は100社を超え、本社・グループ会社の経営人材育成が大きな課題になっている。一般的に新卒者の離職者は3年内で3割とされる中、MISIは数%にとどまっているが、意欲ある優秀な人材が流出するケースはある。商社ビジネスの醍醐味や将来機会を理解してもらうため、経営陣を含め世代を超えた交流の機会を増やしている。またストレッチ・アサインメント制度を導入し、海外事業会社の社長ポジション、海外現地法人など17拠点の責任者のポジションを若手育成ポストに選定。課長になる前の30歳台の社員を派遣し、経験とセンスを身につけさせている。私達の世代は30歳台に海外コイルセンターの社長に就任し、大変な苦労を重ねたが、とても貴重な経験になっている。有望な若手がいれば、20歳台後半でもチャンスを与えていく」
――留学制度も拡充する。
「世界で戦える人材を育成していく。課長級以上の役職者を全員、短期のビジネススクールに派遣する。国内に限らず、米国のハーバード大学、ノースウエスタン大学、ペンシルベニア大学、スイスのIMDなど世界トップクラスの学校へ送り込んでいく。若手に配慮し、シンガポールのINSEADも対象に加えた」
――商社の脱炭素対応機能として、電磁鋼板の加工・流通事業強化が求められている。
「世界的なモーターコアメーカーであるイタリアのユーロ・グループと中国にEV駆動用のモーターコア合弁事業を運営しており、メキシコにあるユーロの加工・物流事業に一部出資するなど協業を広げている。日本ではモーターコア製造合弁の紅忠黒田ラミネーションを設立した。ユーロ・グループ、黒田精工との三者アライアンスを強化しながら、伸びるEV関連需要をしっかり捕捉していく。中国では大連藤洋、嘉興紅忠が電磁鋼板を加工している。インドではデリー近郊で無方向性電磁鋼板のモーターコア製造事業を行っている。インド、北米は需要の伸びを見極めながら次の手を打っていく」
――自動車はハイテン鋼板、アルミパネルの需要も伸びていく。
「米国ではミシガンRSDCがハイテン、車体用アルミ材をGM向けに供給しており、大型ピックアップEV車用のアルミブランク材が増えている。中国では武漢紅忠のアルミブランク加工機能が評価されている」
――昨年4月に設立した「インキュベーション室」の取り組みを。
「脱炭素社会・デジタル社会において取引先が求めるサービスを提供していく。物流や人手不足などの問題を抱える国内の鋼材流通にいて新たな機能を発揮するための試行錯誤を重ねている。事業会社に物流管理統括者を置いて、物流事業者との契約内容の点検、待機時間や荷役作業時間など実態の見える化を推進。輸送効率を高めるための荷主と輸送業者がデジタルでつながるプラットフォームを開発し、鋼管問屋のニッコーなどで実証試験を続けている」
――グリーンスチールの拡販もテーマ。
「プレミアムの理解活動、拡販に取り組んでいる。来年5月に本社を東京ミッドタウン八重洲に移転するが、新調するオフィス家具類にグリーンスチールの使用を検討している」
――洋上風力発電プロジェクトが国内でも本格化する。
「先行する中国のプロジェクトに参画し、ノウハウを積み重ねている。鋼材、部材加工、組み立て、物流、設置など大型プロジェクトとなるので鉄鋼総合商社としての機能を発揮できる。株主会社、鉄鋼メーカーとともに積極的に関与していく」
――インドなど海外の市場開拓機能も期待されている。
「アジア・大洋州支配人補佐として、インド総代表のポジションを新設した。現地の需要家など取引先のトップと直接、面談して情報交換し、ニーズを収集することでタイムリーに商社機能を発揮していく。インド国内では、独自のモーターコア製造事業に加えて、JSWスチールとはプネ、チェンナイ、デリー、アーメダバードの4拠点で自動車対応の薄板、電磁鋼板のコイルセンターを展開。マグナム・ストリップ&チューブとは二輪・四輪用のメカニカルチューブ製造拠点やコイルセンターを共同で運営。カパロ・エンジニアリングとは自動車用TWBの合弁事業を運営している。総代表の機能を引き出しながら、事業を広げていく」
――北米は建材、鋼管、薄板の安定した収益基盤を拡充する。
「建材は、建築用スチールフレームで全米4割強のシェアを握るクラークウエスタン・ディートリック・ビルディングシステムズ(CDBS)、住宅の屋根・壁用アルミ・スチールサイディングを得意とするクオリティ・エッジを通して市場を深耕していく。鋼管は、マルベニ・イトチュウ・チューブラーズ・アメリカがヒューストンに本社を構え、油井管、ラインパイプ、特殊管のマスターディストリビューター機能を担い、油井管問屋のスーナー、CTAP、カナダのトライマークの100%子会社が北米市場をカバーしている。薄板は、MISAメタルプロセシングがポートランド、ルイビル、フォレストの3拠点を展開し、ゼネラルモータース向けのパネル加工機能を担うRSDCミシガンも業容を拡大している。MISAスペシャルティ・プロセシングを加えて、自動車対応の薄板サービスセンターは5拠点となった。厚板溶断のMISAメタル・ファブリケーティングがルイビルにある。日本製鉄、JFEスチールの現地事業展開、大統領選挙の行方などをにらみながら、強い事業基盤をさらに強化していく。メキシコはアグアスカリエンテス州、グアナファト州に薄板サービスセンターがあり、丸一鋼管と自動車部品事業も展開している」
――中東、アフリカ市場へのアプローチは。
「中東、アフリカは重要エリア。欧州会社社長が欧阿支配人を兼務し、得意とするトレード機能を発揮しながら市場開拓を進めていく。欧州は脱炭素関連規制も見据えて、新たなアプローチを展開する。英国とUAEに鋼管問屋があり、スペインでは油井管のネジ切り加工を行っている。UAEにはJFEスチールとの大径管製造合弁事業もある。英国のバークレイ・アンド・マシソンの買収効果を引き出しながら、次の一手を検討していく」
――豪州は脱炭素関連ビジネスの広がりが期待される。
「厚板切断加工のトータル・スチール・オブ・オーストラリア、鋼管販売のマルベニ・イトチュウ・チューブラーズ・オセアニア、現地法人の3社が事業を展開しており、それぞれ10億-30億円規模の利益を安定的に稼いでいる。人口密度は低く、成熟国ではあるが、金属・エネルギー資源国としての成長が期待でき、水素・ガス、CCUSなどのプロジェクトも数多く計画されており、株主会社と情報交換しながらビジネスチャンスを開拓していく」(谷藤 真澄)














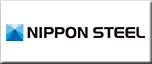
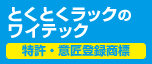
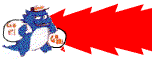
















 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ


















