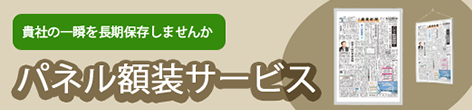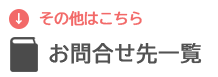1
2024.1.15
2019年3月13日
インタビュー 時代の架け橋 2050年に向けて 2019年、新時代へ 三井物産・飯島彰己会長(上) 平成元年 激動の時代、幕開け ゴーンショック 鉄鋼再編の引き金に
日本は新たな時代を迎える。「平成」の約30年間は、バブル景気崩壊、アジア通貨危機、中国の急成長、米リーマン・ショック、東日本大震災、米トランプ大統領の誕生、Brexitなどが続く激動の時代だった。新たな時代は、IoTやビッグデータなど高度ITを活用したビジネスが一気に普及し、自動車のEV化など産業構造転換も加速する。鉄鋼・非鉄業界は、マルチマテリアル、脱炭素社会、発展途上国の自国産化などの変化に対応しつつ、新たなビジネスモデルを創出し、自ら構造転換していくことを迫られている。特別企画「時代の架け橋―2050年に向けて―」では、歴史の大きな節目にあたって「平成」の30年間を振り返りつつ、足元の課題を整理し、30年後の2050年に向けての展望を探る。初回は三井物産の飯島彰己代表取締役会長とともに商社、鉄鋼・非鉄業界の窓から見る「時代の架け橋」を渡る。
平成を振り返って(1)(1989―2002年)
89―94年/国内低迷、海外に活路
――鉄鋼・非鉄畑を長く歩み、社長、会長時代を通して、世界の経済・社会情勢を俯瞰してきた。平成元年(1989年)当時を振り返ると。
「まさに激動の時代の幕開けとなった。6月に天安門事件が起こり、11月にはベルリンの壁が崩壊した。日本では日経平均株価が12月29日に3万8957円の史上最高値をつけ、平成はバブルの絶頂と崩壊の混乱の中でスタートした。30年間を振り返るにあたって、89年から94年を『国内が低迷し、海外に活路を求めた時代』と整理してみた。日本は、70年代の二度のオイルショックで高度経済成長が終焉。製造業は国際競争力を強化し、輸出による成長に挑むが、85年のプラザ合意で海外の現地生産にシフトしていった。そして91年にバブルが崩壊し、内需が一段と縮小。日本企業は海外に活路を求めることになった」
――三井物産の鉄鋼製品ビジネスは海外進出を本格化させた。
「米国では、日産自動車対応の薄板コイルセンター、マイテックを現地企業と合弁で87年に設立し、ネットワークを広げていた。90年を前後して新日本製鉄のIN/テック・コート、日新製鋼のウィーリング・ニッシンが現地生産を開始し、われわれは加工・物流網を活用して販売量を伸ばしていった。東南アジアでもコイルセンターを開設するとともに、タイのサイアム・ヤマト・スチール、ベトナムのビナ・キョウエイ・スチールなどの現地製造事業にも出資参画していった」
――金属資源ビジネスも海外の権益取得を本格化した。
「製鉄原料の安定調達を目指し、すでに豪州のローブリバー、マウントニューマン、モウラなどの鉄鉱石・石炭権益を保有し、ブラジルでもMBR(現ヴァーレ)の鉄鉱石権益を取得していた。90年以降、資源価格は低迷することになるが、ゴールズワーシー、ヤンディ、ケストレル、ベンガラと豪州の資源権益を取得し続けた」
95―02年/冬の時代
――95年以降の時代認識は。
「バブル崩壊後で最も厳しい、いわば『冬の時代』という認識だ。国内では山一證券の自主廃業、北海道拓殖銀行の破綻などが続き、海外でも97年に発生したアジア通貨危機がロシアのルーブル危機に飛び火し、世界的な不況に陥った」
――鉄鋼業界にとっては厳冬期となった。
「内需低迷が続き、アジア需要も減退する中、日本の鉄鋼業界は対米輸出を積極化した。その結果、日本製鋼材に対するアンチダンピング提訴が激増し、鉄鋼貿易摩擦が再燃。対米輸出に依存するビジネスモデルの転換の契機となった。さらに99年のいわゆるゴーンショックがトリガーとなって鋼材価格が下落。JFEグループ、伊藤忠丸紅鉄鋼、メタルワンなど企業の統合計画が相次ぎ発表された。新日本製鉄、住友金属工業、神戸製鋼所は3社資本提携に踏み込んだ」
――海外でも再編が続いた。
「ドイツのティッセンとクルップが97年に統合。99年にはブリティッシュ・スチールとオランダのホーゴベンスが合併してコーラスが誕生。02年にはアルセロールが誕生した」
――金属資源業界も再編が進んだ。
「リオ・ティントが00年にノースを買収し、BHPとビリトンが01年に合併し、資源メジャーの合従連衡が始まった」
――三井物産の鉄鋼製品ビジネスは、中国事業の基盤を築いた。
「中国では上海宝山製鉄所の第1高炉が火入れされた85年から熱延鋼板、冷延鋼板の輸出を担い、92年には総合合作協定を結んでいた。02年には両社のコイルセンター事業を統合し、中国国内の物流・加工網を整備。その後、急拡大する中国の鉄鋼需要を捕捉する事業基盤を整えた」
――金属資源ビジネスは事業投資にシフトした。
「鉄鋼原料の安定供給を目的とするトレードビジネスから、原料安定供給の担い手へと転換し、事業利益拡大に注力し始めた。鉄鉱石は96年にインドのセサゴア、97年にブラジルのカエミに出資し、チリのコジャワシ銅山にも投資をした。商社金属資源ビジネスの転換点となった。競争力ある価格で購入したセサゴアは10年後に約1000億円で売却し、カエミへの投資は、その後のCVRD、ヴァーレへと続く大規模なビジネスへと成長していく」
(谷藤 真澄)
平成を振り返って(1)(1989―2002年)
89―94年/国内低迷、海外に活路
――鉄鋼・非鉄畑を長く歩み、社長、会長時代を通して、世界の経済・社会情勢を俯瞰してきた。平成元年(1989年)当時を振り返ると。
「まさに激動の時代の幕開けとなった。6月に天安門事件が起こり、11月にはベルリンの壁が崩壊した。日本では日経平均株価が12月29日に3万8957円の史上最高値をつけ、平成はバブルの絶頂と崩壊の混乱の中でスタートした。30年間を振り返るにあたって、89年から94年を『国内が低迷し、海外に活路を求めた時代』と整理してみた。日本は、70年代の二度のオイルショックで高度経済成長が終焉。製造業は国際競争力を強化し、輸出による成長に挑むが、85年のプラザ合意で海外の現地生産にシフトしていった。そして91年にバブルが崩壊し、内需が一段と縮小。日本企業は海外に活路を求めることになった」
――三井物産の鉄鋼製品ビジネスは海外進出を本格化させた。
「米国では、日産自動車対応の薄板コイルセンター、マイテックを現地企業と合弁で87年に設立し、ネットワークを広げていた。90年を前後して新日本製鉄のIN/テック・コート、日新製鋼のウィーリング・ニッシンが現地生産を開始し、われわれは加工・物流網を活用して販売量を伸ばしていった。東南アジアでもコイルセンターを開設するとともに、タイのサイアム・ヤマト・スチール、ベトナムのビナ・キョウエイ・スチールなどの現地製造事業にも出資参画していった」
――金属資源ビジネスも海外の権益取得を本格化した。
「製鉄原料の安定調達を目指し、すでに豪州のローブリバー、マウントニューマン、モウラなどの鉄鉱石・石炭権益を保有し、ブラジルでもMBR(現ヴァーレ)の鉄鉱石権益を取得していた。90年以降、資源価格は低迷することになるが、ゴールズワーシー、ヤンディ、ケストレル、ベンガラと豪州の資源権益を取得し続けた」
95―02年/冬の時代
――95年以降の時代認識は。
「バブル崩壊後で最も厳しい、いわば『冬の時代』という認識だ。国内では山一證券の自主廃業、北海道拓殖銀行の破綻などが続き、海外でも97年に発生したアジア通貨危機がロシアのルーブル危機に飛び火し、世界的な不況に陥った」
――鉄鋼業界にとっては厳冬期となった。
「内需低迷が続き、アジア需要も減退する中、日本の鉄鋼業界は対米輸出を積極化した。その結果、日本製鋼材に対するアンチダンピング提訴が激増し、鉄鋼貿易摩擦が再燃。対米輸出に依存するビジネスモデルの転換の契機となった。さらに99年のいわゆるゴーンショックがトリガーとなって鋼材価格が下落。JFEグループ、伊藤忠丸紅鉄鋼、メタルワンなど企業の統合計画が相次ぎ発表された。新日本製鉄、住友金属工業、神戸製鋼所は3社資本提携に踏み込んだ」
――海外でも再編が続いた。
「ドイツのティッセンとクルップが97年に統合。99年にはブリティッシュ・スチールとオランダのホーゴベンスが合併してコーラスが誕生。02年にはアルセロールが誕生した」
――金属資源業界も再編が進んだ。
「リオ・ティントが00年にノースを買収し、BHPとビリトンが01年に合併し、資源メジャーの合従連衡が始まった」
――三井物産の鉄鋼製品ビジネスは、中国事業の基盤を築いた。
「中国では上海宝山製鉄所の第1高炉が火入れされた85年から熱延鋼板、冷延鋼板の輸出を担い、92年には総合合作協定を結んでいた。02年には両社のコイルセンター事業を統合し、中国国内の物流・加工網を整備。その後、急拡大する中国の鉄鋼需要を捕捉する事業基盤を整えた」
――金属資源ビジネスは事業投資にシフトした。
「鉄鋼原料の安定供給を目的とするトレードビジネスから、原料安定供給の担い手へと転換し、事業利益拡大に注力し始めた。鉄鉱石は96年にインドのセサゴア、97年にブラジルのカエミに出資し、チリのコジャワシ銅山にも投資をした。商社金属資源ビジネスの転換点となった。競争力ある価格で購入したセサゴアは10年後に約1000億円で売却し、カエミへの投資は、その後のCVRD、ヴァーレへと続く大規模なビジネスへと成長していく」
(谷藤 真澄)
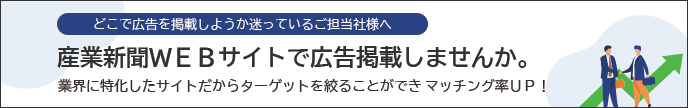
スポンサーリンク




























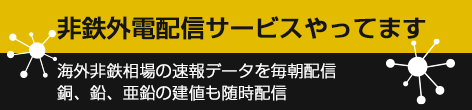




 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ