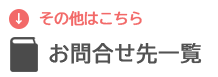2017年7月28日
目指すは日本版静脈メジャー:リサイクル4社共同出資会社 「RUN」の挑戦【上】 売上高1000億円規模へ/メタルリサイクル廃棄物処理 包括的にニーズ捕捉
スズトクホールディングス(本社=東京都千代田区)、マテック(本社=北海道帯広市)、やまたけ(本社=東京都足立区)、青南商事(本社=青森県弘前市)の4社は、2017年7月3日付で東日本エリアをカバーする共同出資会社「株式会社アール・ユー・エヌ(RUN)」を設立した。マテリアルリサイクル分野と廃棄物処理分野でマーケットの垣根が解消されつつある中、RUNは両分野のニーズを捕捉することで循環型社会形成に寄与しながら、欧米に比肩する日本版静脈メジャー実現を目指す。
【RUNの概要】
RUNは資本金2500万円で、4社がそれぞれ25%を出資。本社は東京都墨田区に設置。代表取締役会長には鈴木孝雄・スズトクホールディングス会長が、代表取締役社長は安東元吉・青南商事社長が就任。取締役には杉山博康・マテック社長、山口大介・やまたけ常務取締役が、執行役員には松岡直人・スズトクホールディングス社長がそれぞれ就いた。新会社を構成する4社の従業員数は合計約2000人。事業所数は本社、海外を含めて合計56拠点。設備能力も高く、1000馬力以上の大型シュレッダーは19台、1000トン以上の大型せん断機(ギロチン)は27台を保有する。ASR再資源化事業2事業者、小型家電リサイクル認定3事業者の認定を受けており、認定エリアは53都道府県となる。4社が持つ広範なネットワークで集荷したスクラップや廃棄物を、コストなどメリットのある最適な事業所で処理することが可能になる。
【RUN設立の経緯】
RUNを設立する4社はエンビプロ・ホールディングス、イボキン、中特ホールディングスを含めた7社で15年3月に包括業務提携を締結した。以降、7社は成長戦略研究会と称する経営トップの勉強会とトップ会談を四半期に1度開催するとともに、6つの分科会で営業やシステムなどの担当者が情報交換などを行っている。分科会の会場は7社持ち回りで、互いの工場や設備を見学することで技術レベル向上などに繋がっている。
この2年4カ月に及ぶ包括業務提携で培った信頼関係をベースに4社が共同出資会社の設立を決定したもの。欧米ではリサイクル企業の大規模化やグローバル化が進む一方、日本国内は人口減少等で長期的にリサイクル資源の発生・消費が漸減すると予想されており、今回、4社は新会社を設立して共同事業を推進することで、東日本から100年先を見据えた日本型リサイクルメジャーの礎を築くとともに、持続可能で主要な社会インフラとしての静脈産業の基盤を確立していく。
【経営方針】
RUNは、8月をめどに共同仕入れと共同販売を本格的にスタートする。同社設立後は営業部、販売部、管理部、経営企画部を立ち上げ、各部で事業スキームの構築を図っており、現在、事業スキームや社内規定等を策定中で、共同事業に向けて準備を進めている。
共同仕入れは4社の仕入れ先リストを共有するとともに、新規ターゲット企業もリストアップし、役割分担を決めた上で、実績の無い企業への飛び込み営業を含めて営業を推進する。例えば、国内に複数拠点を有する製造業に対するアプローチでは4社のネットワークを生かすことで、各拠点で発生するスクラップを一括して集荷することなどが可能。国内では市中の鉄スクラップ発生量が漸減傾向にある中、4社が連携することで集荷シェア拡大を図っていく方針。
一方、国内販売及び輸出などの共同販売では、遠方輸出等でスケールメリットを発揮する。また月間ベースで4社それぞれ一定の出荷責任数量を設定することで、1社当たりの市況や為替変動リスクを軽減できる。国内外顧客リストを4社内で共有し、「4社の販売方法なども精査しながら、国内商社経由や海外バイヤー経由、海外エージェント経由、現地メーカー直接取り引きを含めた幅広い形態の中から、最適な方法を選択する」(安東社長)。
共同仕入れ、共同販売の次ステップとして、業務の標準化を進める計画。特に品質管理を重要視しており、4社のノウハウを共有することで、仕入れからヤード保管、維持管理、出荷までの一貫プロセスで高品質を確保。システムを含めた事務業務部門、ヤードオペレーション部門も業務標準化のターゲットに入れる。「明瞭なコンプライアンスに基づいた企業活動を行うことで、静脈産業の社会的信用を高めていく」(鈴木会長)という。
【思い描く将来像】
RUNは、「日本の静脈産業を急速に発展させ、欧米の静脈メジャーと遜色ない日本型メジャーを作る」(鈴木会長)とし、メタルリサイクルと廃棄物処理に関する広範・多岐にわたるニーズを包括的に捕捉し、売上高で1000億円規模に引き上げるのが目標だ。
「我々は生き残るために覚悟を決めて、ありとあらゆる対策を練り、全方位で展開することがRUNの戦略になる。環境は決して追い風ではないが、悲観的になりすぎず、初めての取組みでもあるし、わくわく感をもって進めていきたい一」(安東社長)と壮大な夢を描く、RUNの挑戦が始まった。
(濱坂 浩司)

【RUNの概要】
RUNは資本金2500万円で、4社がそれぞれ25%を出資。本社は東京都墨田区に設置。代表取締役会長には鈴木孝雄・スズトクホールディングス会長が、代表取締役社長は安東元吉・青南商事社長が就任。取締役には杉山博康・マテック社長、山口大介・やまたけ常務取締役が、執行役員には松岡直人・スズトクホールディングス社長がそれぞれ就いた。新会社を構成する4社の従業員数は合計約2000人。事業所数は本社、海外を含めて合計56拠点。設備能力も高く、1000馬力以上の大型シュレッダーは19台、1000トン以上の大型せん断機(ギロチン)は27台を保有する。ASR再資源化事業2事業者、小型家電リサイクル認定3事業者の認定を受けており、認定エリアは53都道府県となる。4社が持つ広範なネットワークで集荷したスクラップや廃棄物を、コストなどメリットのある最適な事業所で処理することが可能になる。
【RUN設立の経緯】
RUNを設立する4社はエンビプロ・ホールディングス、イボキン、中特ホールディングスを含めた7社で15年3月に包括業務提携を締結した。以降、7社は成長戦略研究会と称する経営トップの勉強会とトップ会談を四半期に1度開催するとともに、6つの分科会で営業やシステムなどの担当者が情報交換などを行っている。分科会の会場は7社持ち回りで、互いの工場や設備を見学することで技術レベル向上などに繋がっている。
この2年4カ月に及ぶ包括業務提携で培った信頼関係をベースに4社が共同出資会社の設立を決定したもの。欧米ではリサイクル企業の大規模化やグローバル化が進む一方、日本国内は人口減少等で長期的にリサイクル資源の発生・消費が漸減すると予想されており、今回、4社は新会社を設立して共同事業を推進することで、東日本から100年先を見据えた日本型リサイクルメジャーの礎を築くとともに、持続可能で主要な社会インフラとしての静脈産業の基盤を確立していく。
【経営方針】
RUNは、8月をめどに共同仕入れと共同販売を本格的にスタートする。同社設立後は営業部、販売部、管理部、経営企画部を立ち上げ、各部で事業スキームの構築を図っており、現在、事業スキームや社内規定等を策定中で、共同事業に向けて準備を進めている。
共同仕入れは4社の仕入れ先リストを共有するとともに、新規ターゲット企業もリストアップし、役割分担を決めた上で、実績の無い企業への飛び込み営業を含めて営業を推進する。例えば、国内に複数拠点を有する製造業に対するアプローチでは4社のネットワークを生かすことで、各拠点で発生するスクラップを一括して集荷することなどが可能。国内では市中の鉄スクラップ発生量が漸減傾向にある中、4社が連携することで集荷シェア拡大を図っていく方針。
一方、国内販売及び輸出などの共同販売では、遠方輸出等でスケールメリットを発揮する。また月間ベースで4社それぞれ一定の出荷責任数量を設定することで、1社当たりの市況や為替変動リスクを軽減できる。国内外顧客リストを4社内で共有し、「4社の販売方法なども精査しながら、国内商社経由や海外バイヤー経由、海外エージェント経由、現地メーカー直接取り引きを含めた幅広い形態の中から、最適な方法を選択する」(安東社長)。
共同仕入れ、共同販売の次ステップとして、業務の標準化を進める計画。特に品質管理を重要視しており、4社のノウハウを共有することで、仕入れからヤード保管、維持管理、出荷までの一貫プロセスで高品質を確保。システムを含めた事務業務部門、ヤードオペレーション部門も業務標準化のターゲットに入れる。「明瞭なコンプライアンスに基づいた企業活動を行うことで、静脈産業の社会的信用を高めていく」(鈴木会長)という。
【思い描く将来像】
RUNは、「日本の静脈産業を急速に発展させ、欧米の静脈メジャーと遜色ない日本型メジャーを作る」(鈴木会長)とし、メタルリサイクルと廃棄物処理に関する広範・多岐にわたるニーズを包括的に捕捉し、売上高で1000億円規模に引き上げるのが目標だ。
「我々は生き残るために覚悟を決めて、ありとあらゆる対策を練り、全方位で展開することがRUNの戦略になる。環境は決して追い風ではないが、悲観的になりすぎず、初めての取組みでもあるし、わくわく感をもって進めていきたい一」(安東社長)と壮大な夢を描く、RUNの挑戦が始まった。
(濱坂 浩司)

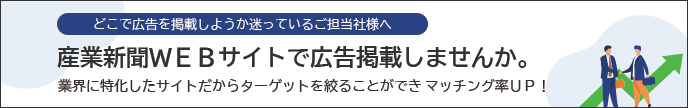













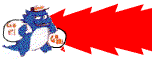












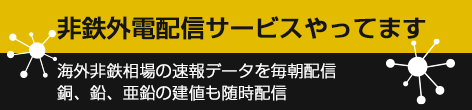




 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ