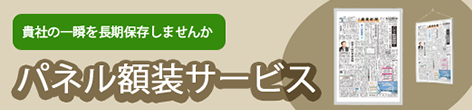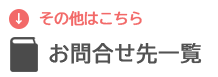1
2024.1.15
2017年2月3日
構造解析技術と金属材料開発 ■今野豊彦・東北大教授に聞く ナノの世界に進化の余地
金属をはじめとする先端材料の研究開発においてナノテクノロジーの重要性が高まってきており、さまざまな分野でナノ技術の活用が進んでいる。それに伴い、ナノレベルでの構造解析技術の重要性が日増しに高まり、高性能な電子顕微鏡の存在が金属材料の技術革新を左右する時代になってきている。電子顕微鏡を用いた構造解析技術が専門で東北大学金属材料研究所の副所長を務める今野豊彦教授に、構造解析技術の進化と金属材料開発の関連性について聞いた。
――金属材料の構造解析はいつから始まったのか。
「金属材料における結晶回析はX線から始まった。X線は1895年、レントゲンによって発見されたが、当初は医療分野での使用にとどまっていた。その当時の材料業界は、金属に原子があることを推測してはいたものの、存在を証明するまでには至っていなかった。1906年に時効硬化の現象を発見し、ジュラルミンが開発されたが、それは原子が発見される前の話であり、セレンディピティ(発明の偶然性)的な発見の典型例であったと言える。14年になりX線の電磁波の波長をもとに結晶を回析したことで、原子が規則的に並んでいることが初めて分かった」
――なぜ電子顕微鏡が必要となったのか。
「顕微鏡の分解能(解像度)は波長の長さで決まる。光の波長は6000オングストローム(1オングストロームは1億分の1センチ)なため光学顕微鏡では、どんなに頑張っても原子を見ることはできない。だが、X線の波長は1・5オングストロームで、BCC鉄の1辺の長さが2・78オングストロームであるため、X線で構造をだいたい解析できるようになった。だが、X線では干渉パターンを見るにとどまるため、35年にルスカが電子線を用いた電子顕微鏡を発明した。これにより実空間で原子を見ることが可能になった」
――電子顕微鏡の進化と金属材料学の歩みは、どのように関連してきたのか。
「光学顕微鏡では析出物や転位による歪みなどは見ることができなかったが、電子顕微鏡の登場により50年代には転位を実際に確認できるようになり、金属組織のレベルで構造を見られるようになった。また、70年代以降には高分解能電子顕微鏡が登場し、電子ビームを原子レベルにまで絞れるようになり、鉄やアルミ、銅といった金属材料のさらなる進化につながった。金属材料と電子顕微鏡は相補的に進歩してきたと言える」
――電子顕微鏡の進化はそろそろ限界に達しているのか。
「いやいや、まだまだだ。近年ではイオンのメスを用いて、ピンポイントで抽出する技術が開発された。この設備は半導体メーカーなどが有しており、ここ20年ほどで一般的になってきている。また、今まさに反応が起こっているところを観察可能な顕微鏡も開発されている」
――世界における日本製電子顕微鏡のレベルは。
「日本製電子顕微鏡の分析レベルは1970年代以降、世界トップレベルにある。優秀なメーカーが存在しており、超高圧電子顕微鏡を製造できるのは世界で日本だけだ。一方、収差補正顕微鏡についてはドイツが開発で先行して日本は出遅れた時期もあったが、現在はキャッチアップしている」
――中国の状況について。
「中国では平均的な大学でも科学予算がここ10年で以前の3倍ほどに増加している。そのため中国の大学や研究機関のどこを訪れても、高価な収差補正顕微鏡が置いてある印象がある。ただ、問題はまだ完全に使いこなしていないと感じられることだ」
――電子顕微鏡は高価なイメージがあるが。
「収差補正電子顕微鏡は1990年ごろからパソコンの発達で飛躍的に性能を向上させたが、当時はまだ価格が高く一般にはなかなか広がらなかった。だが、2010年以降になって一般の企業が使用できるレベルに価格が下がってきた。また、東北大学には文部科学省の装置共有事業として、学内にナノテクリサーチセンターを設置している。大学にある電子顕微鏡を多くの人が活用できるようにしている」
――超高圧電子顕微鏡連携ステーションについて。
「通常の電子顕微鏡の加速電圧は20万ボルトほどだが、超高圧電子顕微鏡は100万ボルトに達する。国内では大阪大学、九州大学、名古屋大学、北海道大学に設備がある。特に大阪大にあるものは加速電圧が300万ボルトで世界一だ。東北大学にもあったのだが東日本大震災で壊れてしまった。1台当たり20億―30億円することもあり、残念ながら撤退してしまった」
――電子顕微鏡の活用で金属材料にさらなる進化の余地はあるのか。
「先人たちは原子が見えない時代でも金属材料の開発を進めてきたが、現在はナノレベルまで見られるようになり、電子顕微鏡で解析しながら開発を進めることができる。そのため鉄やアルミといった構造材料についても、まだまだ進化の余地があるだろう」
(服部 友裕)
――金属材料の構造解析はいつから始まったのか。
「金属材料における結晶回析はX線から始まった。X線は1895年、レントゲンによって発見されたが、当初は医療分野での使用にとどまっていた。その当時の材料業界は、金属に原子があることを推測してはいたものの、存在を証明するまでには至っていなかった。1906年に時効硬化の現象を発見し、ジュラルミンが開発されたが、それは原子が発見される前の話であり、セレンディピティ(発明の偶然性)的な発見の典型例であったと言える。14年になりX線の電磁波の波長をもとに結晶を回析したことで、原子が規則的に並んでいることが初めて分かった」
――なぜ電子顕微鏡が必要となったのか。
「顕微鏡の分解能(解像度)は波長の長さで決まる。光の波長は6000オングストローム(1オングストロームは1億分の1センチ)なため光学顕微鏡では、どんなに頑張っても原子を見ることはできない。だが、X線の波長は1・5オングストロームで、BCC鉄の1辺の長さが2・78オングストロームであるため、X線で構造をだいたい解析できるようになった。だが、X線では干渉パターンを見るにとどまるため、35年にルスカが電子線を用いた電子顕微鏡を発明した。これにより実空間で原子を見ることが可能になった」
――電子顕微鏡の進化と金属材料学の歩みは、どのように関連してきたのか。
「光学顕微鏡では析出物や転位による歪みなどは見ることができなかったが、電子顕微鏡の登場により50年代には転位を実際に確認できるようになり、金属組織のレベルで構造を見られるようになった。また、70年代以降には高分解能電子顕微鏡が登場し、電子ビームを原子レベルにまで絞れるようになり、鉄やアルミ、銅といった金属材料のさらなる進化につながった。金属材料と電子顕微鏡は相補的に進歩してきたと言える」
――電子顕微鏡の進化はそろそろ限界に達しているのか。
「いやいや、まだまだだ。近年ではイオンのメスを用いて、ピンポイントで抽出する技術が開発された。この設備は半導体メーカーなどが有しており、ここ20年ほどで一般的になってきている。また、今まさに反応が起こっているところを観察可能な顕微鏡も開発されている」
――世界における日本製電子顕微鏡のレベルは。
「日本製電子顕微鏡の分析レベルは1970年代以降、世界トップレベルにある。優秀なメーカーが存在しており、超高圧電子顕微鏡を製造できるのは世界で日本だけだ。一方、収差補正顕微鏡についてはドイツが開発で先行して日本は出遅れた時期もあったが、現在はキャッチアップしている」
――中国の状況について。
「中国では平均的な大学でも科学予算がここ10年で以前の3倍ほどに増加している。そのため中国の大学や研究機関のどこを訪れても、高価な収差補正顕微鏡が置いてある印象がある。ただ、問題はまだ完全に使いこなしていないと感じられることだ」
――電子顕微鏡は高価なイメージがあるが。
「収差補正電子顕微鏡は1990年ごろからパソコンの発達で飛躍的に性能を向上させたが、当時はまだ価格が高く一般にはなかなか広がらなかった。だが、2010年以降になって一般の企業が使用できるレベルに価格が下がってきた。また、東北大学には文部科学省の装置共有事業として、学内にナノテクリサーチセンターを設置している。大学にある電子顕微鏡を多くの人が活用できるようにしている」
――超高圧電子顕微鏡連携ステーションについて。
「通常の電子顕微鏡の加速電圧は20万ボルトほどだが、超高圧電子顕微鏡は100万ボルトに達する。国内では大阪大学、九州大学、名古屋大学、北海道大学に設備がある。特に大阪大にあるものは加速電圧が300万ボルトで世界一だ。東北大学にもあったのだが東日本大震災で壊れてしまった。1台当たり20億―30億円することもあり、残念ながら撤退してしまった」
――電子顕微鏡の活用で金属材料にさらなる進化の余地はあるのか。
「先人たちは原子が見えない時代でも金属材料の開発を進めてきたが、現在はナノレベルまで見られるようになり、電子顕微鏡で解析しながら開発を進めることができる。そのため鉄やアルミといった構造材料についても、まだまだ進化の余地があるだろう」
(服部 友裕)
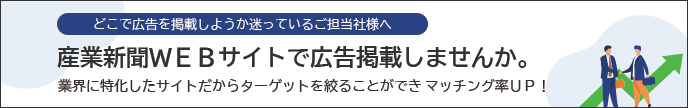
スポンサーリンク














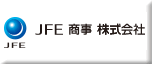

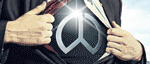











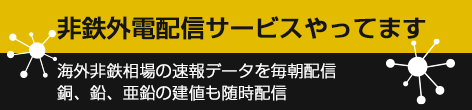




 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ