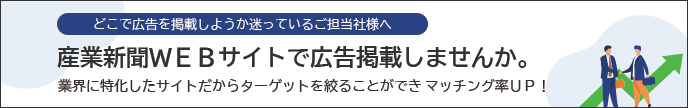司会「日本の鉄鋼・非鉄業界が、欧米の基礎技術を改良することで、世界の製造プロセス技術開発をリードしてきたことがよく分かりました」
家守「日本人は、ゼロからのイノベーションというか、新しい技術を創りだす力は弱いが、これだという技術があれば、実用プロセスまで持っていく力は強い」
友野「日本はエンジニアのモチベーションが高かったし、日本鉄鋼協会などアカデミアのバックアップも大きかった。慢心していると、米国の鉄鋼業界のように成功体験が次の成功を阻む『成功の復讐』に陥る。プロセス改良・開発に挑戦し続ける意欲を低下させてはならないし、産官学による環境整備も重要だ」
家守「米国は1980年まで世界最大の銅生産国でもあった。当時としては最新鋭の反射炉を持ち、銅鉱山など資源も豊富だった。米国の非鉄大手は反射炉の次世代製錬技術開発で後れを取ったが、鉱山事業で稼ぐことができた。現在、米国に銅鉱山は残っているが、製錬ビジネスにかつての勢いはない。米国企業は、捨てる勇気を持つという見方もできる。当社が別子銅山の採掘を止めたのは、地表1000メートルから、海面下1000メートルまで掘り続けたところ岩盤の圧力が上がり、坑道を保持できなくなったためで、諦めざるを得なかった。ビジネス環境は大きく変動しており、事業やプロセス技術をどのタイミングで見限るか、その判断や勇気がより重要になっている」
司会「次のキーワードは『技術先進性の維持』です」
友野「社会に役立つ鉄鋼材料を開発し、リーズナブルなコストで製品化し、世界のどこでも供給可能な体制を整える。日本の鉄鋼業が技術先進性を維持し、存在感を高めていくための重要なポイントであるが、これらを実現するためには、生産効率の飛躍的な革新、革新的プロセスの開発、ローカルコンディションに応じたプロセスの開発の3つのイノベーションが必要となる。高炉の概念は変わっていないが、内容積が1000立方メートルから2000立方メートルの中型になり、5000立方メートル超の大型に発展してきた。このイノベーションを私は『効率革新型』と定義づけている。一方、転炉は平炉とまったく異なるプロセスになり、インゴットメーキングも連続鋳造に効率化されており、これらを『抜本革新型』と私は呼んでいる。製鉄事業が新しい時代に適合していくには、この2つの『革新』をどちらかではなく、同時に組み合わせていくアプローチが有効だろう。設備はリプレースの時期が来るし、高炉のように改修期が見えているものもある。設備の寿命には『老朽化』と『陳腐化』がある。老朽化であれば、メンテナンスをしながら最新技術を盛り込んでいく。陳腐化はリプレースする必要がある。家守会長の指摘通り、陳腐化の見極めは重要で、誤ると米国の二の舞となる。抜本革新が無理と見切ったものについては『整数倍』がキーワードになる。生産効率を1・2倍や1・3倍ではなく、2倍、3倍を目指すということだ。例えば2倍になれば、二つの設備を一つに集約できる」
家守「銅やニッケルのビジネスは、鉱山と製錬所を一体運営する考え方が主流だ。しかし、現在国内に金以外の金属鉱山を持たない日本では、製錬技術の先進性を維持することで、海外原料を確保してきた。銅では、自溶炉技術をひたすら磨いて今でも世界トップクラスの技術を維持しており、ニッケルでは外部環境の大きな変化に革新的なプロセス開発で対応してきた。当社におけるメタルニッケルの生産は、メタルアノード電解精製法により1939年に始まった。エネルギーを多く消費するこの製錬法は、原油価格の高騰に堪えられなくなり、中間原料であるニッケルマットを直接電気分解するマットアノード電解精製法の開発(1969年)により競争力を維持した。しかし、更に20年後には円高となったため、第三世代の技術であるMCLE(マット塩素浸出電解採取)法を開発(1989年)し、今日に至っている。2000年に入ってからは、自前の中間原料を確保するために、HPAL(高圧硫酸浸出)プロセスを世界で初めて大規模商業生産させることに成功し、ニッケル製錬技術でも世界最先端を走っている」
司会「非鉄はビジネスモデルの転換が進んでいます。ちなみに銅製錬所の規模と建設コストは」
家守「品位20―40%の銅精鉱を調達し、自溶炉―転炉―精製炉―電解精製の一貫製造プロセスで99・99%以上の電気銅と硫酸を製造する。1ユニットが年産能力20万トン程度で、製錬所の建設コストは1000億―1500億円。東予、佐賀関は1系列の45万トン設備で競争力がある。中国には100万トン超の製錬所もあるが、3系列で構成している。韓国大手は自溶炉プロセスと三菱プロセスのセットで60万トン能力。佐賀関も昔は2系列だったが、いまは1系列の設備となり、競争力を大幅にアップした」