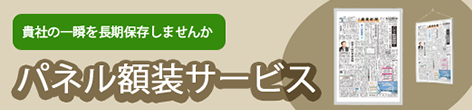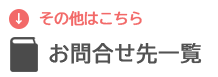2016年11月11日
産学官連携イノベーションの中核へ ■産業技術総合研究所理事長 中鉢良治氏 橋渡し機能を強化 「三位一体型」確立に貢献
今年10月1日付で特定国立研究開発法人に指定された産業技術総合研究所(AIST)は、世界トップクラスの国立研究機関として、日本の産学官の連携によるイノベーションにおける中枢的としての役割を期待されている。自らもエンジニアであり企業の経営者としての経歴を持つ中鉢良治理事長に方針と今後の展望を聞いた。
――特定国立研究法人に指定された。産総研に求められている役割とは。
「特定化が決まる経緯として、特に「橋渡し」機能の強化が求められていると考えている。我々の役割の一丁目一番地として橋渡し機能と、それを生み出す目的基礎研究、すなわちイノベーションを産む研究に力を入れて行く。さらにイノベーションを担う人材の育成と合わせて三位一体で事業を進め、世界水準で社会の期待に応えていきたいと思っている。大学を中心としたアカデミアと産業界の中間にある産業技術を担う研究所として、イノベーションのエコシステム、『ナショナルイノベーションシステム」の確立に貢献し、その中核的な役割を果たしていきたい」
――今年は2030年を見据えた研究戦略を打ち出した。
「21世紀の中間年に当たる2050年には、低炭素社会、資源循環型社会、そして自然と共生する社会を実現することが求められる。それを目標として4つの研究領域について現在の研究ポテンシャルから推し測って2030年までにどういうことができるかをまとめている。1つは、膨大な情報データからの新たな価値創造を創出する情報技術。第2に低炭素・資源循環を実現するための創エネルギー、蓄エネルギー、省エネルギーの取り組みをさらに進めること。3つは物質・生命。そして産業と社会の安心安全を確保する技術だ。2030年の研究戦略は、現在の取り組みと2050年のあるべき社会を前提にしたバックキャスト的な考え方で策定した。産総研は現在、原子力や宇宙工学などを除いて、いわゆる産業分野はほぼカバーしている。加えて知的基盤技術と呼んでいるが、国立研究機関として計量計測や地質などの社会や産業の基盤を支える研究成果や豊富なデータも有しており、産総研が社会や産業に貢献していく上で重要な役割を担っている」
――他の研究機関との連携について。
「元々、日本企業は、戦後に創業された企業も含め、社会的価値と経済的価値を同時に高めようという志を持っていた。ところが、モノ不足が解消され、その過程で日本企業が世界的なポジションを確立していくにつれて、経済的価値に傾斜していき、社会的価値が後回しにされてきた感がある。企業は経済的価値創出を担い、社会的価値の部分は別の主体が担うべきだという分業的な考え方が強まってきたように思う。その端的な例が公害などの社会問題につながったと思うが、最近になって再びそうしたソーシャルインパクトが顕在化している。このような状況では、課題に対して個別の機関や企業でなく、社会全体で対応しようという姿勢が必要になる。その視点に立つとまず、産総研も含めた国立の研究開発機関同士の連携は確実に不足していると考えている。また、大学や企業との連携、さらに社会科学分野との連携もまだ十分ではない」
「先日発表した一橋大学との包括連携協定は、社会科学分野との連携の事例だと考えていただきたい。社会的な合意を形成するとか、事業をするためのビジネスモデルを構築していくというプロセスは、研究開発の枠を超えたところにある。こうした部分について一橋大学の有するポテンシャル、人材と経験を活用させていただきたい。まずは一橋大学の方に産総研のイノベーションコーディネータとして、産総研の人間と一緒になって現場で活躍していただくことを期待している。自然科学と社会科学の融合の必要性についてはこれまでも指摘されて来たが、この事例が成果を上げ、ロールモデルになって波及すればよいと思う」
――産官学連携の考え方について。
「産学連携というのは私が学生だった50年ほど前にも、多くの大学が実施していた。今でもさまざまな大学で企業との連携が模索されている。基礎研究・科学から、技術、そしてイノベーションにつながるというエコシステムを考えると、サイエンスを担うアカデミアとそれを社会に実装する企業との間にリレーゾーンが存在する。そのリレーゾーンにあたるのが橋渡し技術であり、それを担うのが産総研だと考えている。産学官の知的集団が社会的成果を求めて協働し合う、それがナショナルイノベーションシステムだ」
「産総研は、大学との連携について『AIST イン キャンパス』という取り組みを実施している。具体的に例を挙げると、ノーベル賞を受賞された名古屋大学の天野浩教授を中心とした窒化ガリウム(GaN)の研究については、名大のポテンシャルを最大限に生かして産総研の成果を最大化するために、名大の中に産総研のオープンイノベーションラボラトリー(OIL)を作った。東大とは先端オペランド計測技術、東北大とは材料開発、早稲田大学とは生命情報解析技術というように、それぞれの分野で連携強化を図っている」
「一方で、企業との融合については産総研のポテンシャルを最大限に活用して企業に社会実装を実現してもらうために、産総研の中に企業名を冠した『冠ラボ』を置いている。また企業とのマッチングの確立を高めるためにそれを担う人材を拡充して橋渡しを進めている。イノベーションコーディネータと呼んでいるが、現在は全国150人体制で企業とのマッチングに努めている。こうした連携を強めることがナショナルイノベーションシステムの根底だと考えている」
「一つの研究成果を見出したとしても、それがそのまま事業になり、企業の成果に結びつくということは極めてまれだ。コストや信頼性、あるいは量産性を確立するための努力も必要だし、さらにその先にはビジネスモデルの構築や社会的な調和といった社会科学的なプロセスを経てイノベーションが完結する。ソニー創業者の井深大さんがおっしゃっていたが、1:10:100の法則と言って、最初の研究開発成果を1とすると量産化には10倍の努力が必要で、さらに事業として成立させるにはさらに100倍の知恵と力が要る。そうしたことを理解した上で我々のミッションを遂行していくことが大切だと考えている」
―――産業立国日本としての在り方をどう考えるか。
「これは世界共通の課題だが、21世紀に最終的に目指すべきは地球規模で持続可能な社会を構築することだ。日本は資源に乏しく、少子高齢化など今現在もさまざまな問題にさらされている。課題大国と揶揄されることもあるが、これに対する着手という点では、リーディングポジションにあるという考え方ができる。低炭素、資源循環に対する取り組み、自然との共生についても、世界に先駆けて取り組んでいると思う。そのポジションを維持しながら世界に貢献することができるし、その貢献のご褒美として日本に利益というものが積まれ、経済的価値も生まれてくるだろう。先行して優位に立てれば、日本の技術は注目され、世界中から投資も集めることになり、その価値も上がる」
――産官学連携の課題と海外との連携について。
「現在は資金の流れや人材の流れに問題がある。日本の年間15兆円を超える研究開発費の中で、民間資金の方が過半を占めており、公的資金はGDPの1%弱となっている。少し民間に偏っている印象はあるが、この水準自体は諸外国と比べても問題はない。問題は民間資金と公的資金の混じり合いが圧倒的に少ないことだ。このことが日本のイノベーションの効率を致命的に下げている。ここを活性化させれば、もっと大きな相乗効果を生む。産学官連携という謳い文句だけではなく、日本の勝ちのスタイルに持っていく必要がある」
「アカデミアと産業界を水平軸としたときに、縦軸には国際的な関係と地方との関係がある。地方との連携としては、工業技術院時代から全国7カ所に研究所があり、地域の産業活性化にも取り組んできた。今後も地域センターの機能をさらに強化していく。同時に、国際的な視点も欠かせない。日本だけで閉じている時代ではない。日本の研究水準を世界のトップレベルとして維持し発展させていくために国際化は非常に重要だ。現在、欧米やアジアの国立研究機関と連携活動を進めている」
――材料分野における直近の成果や取り組みについて。
「産総研では非鉄金属と化学系材料に強みを持っている。例えばマグネシウムはアルミより軽く、軽い素材だ。加工の難しさや燃焼しやすいといったことが課題だったが、分子原子レベルで材料の特性を向上させ、押出加工できるところまで来ている。将来的には軽量構造部材として自動車や電車の車体などに適用することで、より少ないエネルギーで人や物を輸送することが可能になる」
「磁石も省エネ材料として欠かせない。ハイブリッド自動車や電気自動車、エアコンなどの家電に搭載されるモーターは、少ない電気を駆動力に変換する性能が非常に重要。現在はネオジム磁石が主流だが、高温で磁力を維持する保磁力を高めるためにジスプロシウムなどのレアアースを添加している。産総研で開発した異方性サマリウム―鉄―窒素焼結磁石は、ジスプロシウムを添加しなくても高温で保磁力が落ちない特徴を持っている。今年度、磁性粉末冶金研究センターという新しい研究センターを設立し、ニーズに対して必要な材料を供給する体制を構築している」
「また、金属ではないが、産総研が強みを持つものとして単層カーボンナノチューブ(CNT)がある。CNTは電気や熱の伝導性に優れ、機械的強度が高く半導体特性もあるということは分かっていたが、なかなかコスト面では難しい部分があった。比表面積の大きさを生かしたキャパシタ材料や服などにプリントできる半導体デバイスなどに適用できる。また、ゴムや樹脂、金属などと組み合わせることで耐熱性や導電性を持つ新しい部材の可能性が広がる。日本ゼオンと協力してスーパーグロース法というロールツーロールで大量に生産できるプロセスを確立した。これはコスト競争に勝つための重要な要素で、日本ゼオンがプラントを作って、昨年から量産を開始している。まさにイノベーションのモデルとして展開しているところだ。ようやく産業化への入り口に立った」
「材料の分野で重要なのは開発のスピードアップだ。スピードイコールコストでもある。マテリアルデザインと呼んでいるが、計算科学とコンピューターを駆使した機能性の高い材料を素早く設計するという取り組みを産業界、特に化学メーカーとともに重点的に進めている。現在の国内外でのトレンドでもあるが、産総研では昨年11月に機能材料コンピューテーショナルデザイン研究センターを立ち上げ、計算科学のプロフェッショナル研究者が30人ほど在籍している。さらに東北大との連携では計算科学と幾何学を融合させた研究開発に取り組んでいる。従来はトライ&エラーでやってきた部分に、もう少し科学的手法、アプローチを導入していこうという試みだ」
――素材産業へメッセージを。
「材料関係の企業からは産総研との連携について敷居が高いといった声も聞く。だから今はこちらからアプローチをかけて業界団体や企業を訪問して、技術を使っていただきたいとアプローチをかけている。職員にも敷居は低く、間口は広く、奥行きは深くということを意識するようにと話している。これまでは契約の際の規約や制限などで提携をしり込みされる企業もあったかと思うが、もっと身近に、自社の社外研究所というくらいに捉えていただければよい。産総研で賄いきれない部分は理研やNIMSに協力を仰ぐこともできる。企業の研究効率はより向上すると思う。まずはご相談いただきたい」
「これまではノウハウを自社で独占的に蓄えてどこよりも性能の良いものを安く、大量に作ることが競争の源泉だったのかもしれないが、今はそういう時代ではない。ノウハウについてはアジア諸国などにキャッチアップされてきている。お金があり人材がいても、では何(What)をすべきか、ということが研究開発のポイントになってきている。そのフォーカスが出来ずに困っている企業が散見される。おそらく求めるものは現在の事業内容の延長線上にはない、非連続なwhatの追求になってくると思う。こういうものを追求するには多様性を持つ研究環境が一番良いのだろうと個人的には考えている。社員が頭を寄せ合って、良いアイデアが出るケースもあるだろうが、多様性を求めて、様々な領域の異業種や大学や研究機関などから意見を求めるのも一つの手法だ。我々は営利団体ではないので、気軽にご相談いただければと思う。産総研には世界トップクラスの研究者が多く在籍している。直に接し、意見交換をしていただくことで将来のイメージがわいてくることもあるはずだ」
中鉢良治(ちゅうばち・りょうじ)1977年東北大学大学院工学研究科博士課程修了。ソニー入社。04年執行役副社長COO。05年代表執行役社長兼エレクトロニクスCEO。09年代表執行役副会長などを歴任。13年独立行政法人(現・特定国立研究開発法人)産業技術総合研究所理事長に就任。

――特定国立研究法人に指定された。産総研に求められている役割とは。
「特定化が決まる経緯として、特に「橋渡し」機能の強化が求められていると考えている。我々の役割の一丁目一番地として橋渡し機能と、それを生み出す目的基礎研究、すなわちイノベーションを産む研究に力を入れて行く。さらにイノベーションを担う人材の育成と合わせて三位一体で事業を進め、世界水準で社会の期待に応えていきたいと思っている。大学を中心としたアカデミアと産業界の中間にある産業技術を担う研究所として、イノベーションのエコシステム、『ナショナルイノベーションシステム」の確立に貢献し、その中核的な役割を果たしていきたい」
――今年は2030年を見据えた研究戦略を打ち出した。
「21世紀の中間年に当たる2050年には、低炭素社会、資源循環型社会、そして自然と共生する社会を実現することが求められる。それを目標として4つの研究領域について現在の研究ポテンシャルから推し測って2030年までにどういうことができるかをまとめている。1つは、膨大な情報データからの新たな価値創造を創出する情報技術。第2に低炭素・資源循環を実現するための創エネルギー、蓄エネルギー、省エネルギーの取り組みをさらに進めること。3つは物質・生命。そして産業と社会の安心安全を確保する技術だ。2030年の研究戦略は、現在の取り組みと2050年のあるべき社会を前提にしたバックキャスト的な考え方で策定した。産総研は現在、原子力や宇宙工学などを除いて、いわゆる産業分野はほぼカバーしている。加えて知的基盤技術と呼んでいるが、国立研究機関として計量計測や地質などの社会や産業の基盤を支える研究成果や豊富なデータも有しており、産総研が社会や産業に貢献していく上で重要な役割を担っている」
――他の研究機関との連携について。
「元々、日本企業は、戦後に創業された企業も含め、社会的価値と経済的価値を同時に高めようという志を持っていた。ところが、モノ不足が解消され、その過程で日本企業が世界的なポジションを確立していくにつれて、経済的価値に傾斜していき、社会的価値が後回しにされてきた感がある。企業は経済的価値創出を担い、社会的価値の部分は別の主体が担うべきだという分業的な考え方が強まってきたように思う。その端的な例が公害などの社会問題につながったと思うが、最近になって再びそうしたソーシャルインパクトが顕在化している。このような状況では、課題に対して個別の機関や企業でなく、社会全体で対応しようという姿勢が必要になる。その視点に立つとまず、産総研も含めた国立の研究開発機関同士の連携は確実に不足していると考えている。また、大学や企業との連携、さらに社会科学分野との連携もまだ十分ではない」
「先日発表した一橋大学との包括連携協定は、社会科学分野との連携の事例だと考えていただきたい。社会的な合意を形成するとか、事業をするためのビジネスモデルを構築していくというプロセスは、研究開発の枠を超えたところにある。こうした部分について一橋大学の有するポテンシャル、人材と経験を活用させていただきたい。まずは一橋大学の方に産総研のイノベーションコーディネータとして、産総研の人間と一緒になって現場で活躍していただくことを期待している。自然科学と社会科学の融合の必要性についてはこれまでも指摘されて来たが、この事例が成果を上げ、ロールモデルになって波及すればよいと思う」
――産官学連携の考え方について。
「産学連携というのは私が学生だった50年ほど前にも、多くの大学が実施していた。今でもさまざまな大学で企業との連携が模索されている。基礎研究・科学から、技術、そしてイノベーションにつながるというエコシステムを考えると、サイエンスを担うアカデミアとそれを社会に実装する企業との間にリレーゾーンが存在する。そのリレーゾーンにあたるのが橋渡し技術であり、それを担うのが産総研だと考えている。産学官の知的集団が社会的成果を求めて協働し合う、それがナショナルイノベーションシステムだ」
「産総研は、大学との連携について『AIST イン キャンパス』という取り組みを実施している。具体的に例を挙げると、ノーベル賞を受賞された名古屋大学の天野浩教授を中心とした窒化ガリウム(GaN)の研究については、名大のポテンシャルを最大限に生かして産総研の成果を最大化するために、名大の中に産総研のオープンイノベーションラボラトリー(OIL)を作った。東大とは先端オペランド計測技術、東北大とは材料開発、早稲田大学とは生命情報解析技術というように、それぞれの分野で連携強化を図っている」
「一方で、企業との融合については産総研のポテンシャルを最大限に活用して企業に社会実装を実現してもらうために、産総研の中に企業名を冠した『冠ラボ』を置いている。また企業とのマッチングの確立を高めるためにそれを担う人材を拡充して橋渡しを進めている。イノベーションコーディネータと呼んでいるが、現在は全国150人体制で企業とのマッチングに努めている。こうした連携を強めることがナショナルイノベーションシステムの根底だと考えている」
「一つの研究成果を見出したとしても、それがそのまま事業になり、企業の成果に結びつくということは極めてまれだ。コストや信頼性、あるいは量産性を確立するための努力も必要だし、さらにその先にはビジネスモデルの構築や社会的な調和といった社会科学的なプロセスを経てイノベーションが完結する。ソニー創業者の井深大さんがおっしゃっていたが、1:10:100の法則と言って、最初の研究開発成果を1とすると量産化には10倍の努力が必要で、さらに事業として成立させるにはさらに100倍の知恵と力が要る。そうしたことを理解した上で我々のミッションを遂行していくことが大切だと考えている」
―――産業立国日本としての在り方をどう考えるか。
「これは世界共通の課題だが、21世紀に最終的に目指すべきは地球規模で持続可能な社会を構築することだ。日本は資源に乏しく、少子高齢化など今現在もさまざまな問題にさらされている。課題大国と揶揄されることもあるが、これに対する着手という点では、リーディングポジションにあるという考え方ができる。低炭素、資源循環に対する取り組み、自然との共生についても、世界に先駆けて取り組んでいると思う。そのポジションを維持しながら世界に貢献することができるし、その貢献のご褒美として日本に利益というものが積まれ、経済的価値も生まれてくるだろう。先行して優位に立てれば、日本の技術は注目され、世界中から投資も集めることになり、その価値も上がる」
――産官学連携の課題と海外との連携について。
「現在は資金の流れや人材の流れに問題がある。日本の年間15兆円を超える研究開発費の中で、民間資金の方が過半を占めており、公的資金はGDPの1%弱となっている。少し民間に偏っている印象はあるが、この水準自体は諸外国と比べても問題はない。問題は民間資金と公的資金の混じり合いが圧倒的に少ないことだ。このことが日本のイノベーションの効率を致命的に下げている。ここを活性化させれば、もっと大きな相乗効果を生む。産学官連携という謳い文句だけではなく、日本の勝ちのスタイルに持っていく必要がある」
「アカデミアと産業界を水平軸としたときに、縦軸には国際的な関係と地方との関係がある。地方との連携としては、工業技術院時代から全国7カ所に研究所があり、地域の産業活性化にも取り組んできた。今後も地域センターの機能をさらに強化していく。同時に、国際的な視点も欠かせない。日本だけで閉じている時代ではない。日本の研究水準を世界のトップレベルとして維持し発展させていくために国際化は非常に重要だ。現在、欧米やアジアの国立研究機関と連携活動を進めている」
――材料分野における直近の成果や取り組みについて。
「産総研では非鉄金属と化学系材料に強みを持っている。例えばマグネシウムはアルミより軽く、軽い素材だ。加工の難しさや燃焼しやすいといったことが課題だったが、分子原子レベルで材料の特性を向上させ、押出加工できるところまで来ている。将来的には軽量構造部材として自動車や電車の車体などに適用することで、より少ないエネルギーで人や物を輸送することが可能になる」
「磁石も省エネ材料として欠かせない。ハイブリッド自動車や電気自動車、エアコンなどの家電に搭載されるモーターは、少ない電気を駆動力に変換する性能が非常に重要。現在はネオジム磁石が主流だが、高温で磁力を維持する保磁力を高めるためにジスプロシウムなどのレアアースを添加している。産総研で開発した異方性サマリウム―鉄―窒素焼結磁石は、ジスプロシウムを添加しなくても高温で保磁力が落ちない特徴を持っている。今年度、磁性粉末冶金研究センターという新しい研究センターを設立し、ニーズに対して必要な材料を供給する体制を構築している」
「また、金属ではないが、産総研が強みを持つものとして単層カーボンナノチューブ(CNT)がある。CNTは電気や熱の伝導性に優れ、機械的強度が高く半導体特性もあるということは分かっていたが、なかなかコスト面では難しい部分があった。比表面積の大きさを生かしたキャパシタ材料や服などにプリントできる半導体デバイスなどに適用できる。また、ゴムや樹脂、金属などと組み合わせることで耐熱性や導電性を持つ新しい部材の可能性が広がる。日本ゼオンと協力してスーパーグロース法というロールツーロールで大量に生産できるプロセスを確立した。これはコスト競争に勝つための重要な要素で、日本ゼオンがプラントを作って、昨年から量産を開始している。まさにイノベーションのモデルとして展開しているところだ。ようやく産業化への入り口に立った」
「材料の分野で重要なのは開発のスピードアップだ。スピードイコールコストでもある。マテリアルデザインと呼んでいるが、計算科学とコンピューターを駆使した機能性の高い材料を素早く設計するという取り組みを産業界、特に化学メーカーとともに重点的に進めている。現在の国内外でのトレンドでもあるが、産総研では昨年11月に機能材料コンピューテーショナルデザイン研究センターを立ち上げ、計算科学のプロフェッショナル研究者が30人ほど在籍している。さらに東北大との連携では計算科学と幾何学を融合させた研究開発に取り組んでいる。従来はトライ&エラーでやってきた部分に、もう少し科学的手法、アプローチを導入していこうという試みだ」
――素材産業へメッセージを。
「材料関係の企業からは産総研との連携について敷居が高いといった声も聞く。だから今はこちらからアプローチをかけて業界団体や企業を訪問して、技術を使っていただきたいとアプローチをかけている。職員にも敷居は低く、間口は広く、奥行きは深くということを意識するようにと話している。これまでは契約の際の規約や制限などで提携をしり込みされる企業もあったかと思うが、もっと身近に、自社の社外研究所というくらいに捉えていただければよい。産総研で賄いきれない部分は理研やNIMSに協力を仰ぐこともできる。企業の研究効率はより向上すると思う。まずはご相談いただきたい」
「これまではノウハウを自社で独占的に蓄えてどこよりも性能の良いものを安く、大量に作ることが競争の源泉だったのかもしれないが、今はそういう時代ではない。ノウハウについてはアジア諸国などにキャッチアップされてきている。お金があり人材がいても、では何(What)をすべきか、ということが研究開発のポイントになってきている。そのフォーカスが出来ずに困っている企業が散見される。おそらく求めるものは現在の事業内容の延長線上にはない、非連続なwhatの追求になってくると思う。こういうものを追求するには多様性を持つ研究環境が一番良いのだろうと個人的には考えている。社員が頭を寄せ合って、良いアイデアが出るケースもあるだろうが、多様性を求めて、様々な領域の異業種や大学や研究機関などから意見を求めるのも一つの手法だ。我々は営利団体ではないので、気軽にご相談いただければと思う。産総研には世界トップクラスの研究者が多く在籍している。直に接し、意見交換をしていただくことで将来のイメージがわいてくることもあるはずだ」
中鉢良治(ちゅうばち・りょうじ)1977年東北大学大学院工学研究科博士課程修了。ソニー入社。04年執行役副社長COO。05年代表執行役社長兼エレクトロニクスCEO。09年代表執行役副会長などを歴任。13年独立行政法人(現・特定国立研究開発法人)産業技術総合研究所理事長に就任。

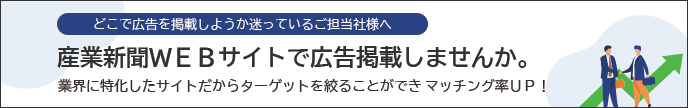













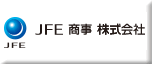


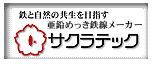











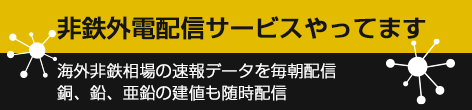



 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ