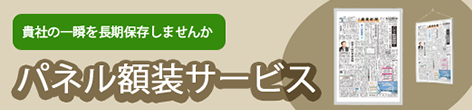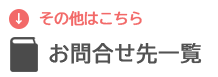2016年4月14日
【第4回】産業新聞80年史 21世紀へ向けての飛躍 ―システム化への取り組み―
1977年(昭和52年)、「赤新聞」の名で親しまれた「日刊金属特報」は、特報版形式からタブロイド版へと変更された。特報版「日刊金属特報」の誕生から28年目の事であったが、これに続き81年には、東京・大阪同時印刷が開始され、全国直配網が確立された。それまでは大阪で印刷され全国に配送されていたが、地域によっては即日配達が難しいところもあった。また、この頃は大阪伊丹空港の夜間飛行が制限され、遠隔地への配送にも支障が出てきていた。このため東京・大阪での同時印刷を開始、配送面のネックを解消し、読者サービスを一段と強化したのである。これによりタブロイド版「日刊金属特報」は、全国で即日配達されることになったが、これを機に次のステップとして、新聞制作工程の合理化、紙面のブランケット版化などが図られていくことになる。
この頃、日本経済は73年の第1次オイルショック、79年の第2次オイルショックを経て低成長期に入っていたが、85年9月には、プラザ合意による急激な円高に見舞われ、円高不況へと突入していった。こうした景気低迷は、否応なく産業界の構造転換を迫り、新聞業界もその例外ではあり得なかった。
それはまず新聞制作システムの技術革新となって表面化してきた。新聞制作の技術革新は、50年代後半、鉛活字を1字ずつ手で拾う文選植字工程が、漢字テレタイプに置き変わることから始まった。漢字テレタイプは、人手による文選植字工程を機械化したもので、鉛活字による凸版印刷というシステムそのものは変わらなかった。しかしその後、全自動写真植字機の登場により、鉛活字や鉛版を使わない全く新しいシステムに移行していった。伝統的な紙型・鉛版方式による印刷は、鉛を溶解する工程を含むため、ホット・タイプ・システムといわれたが、新システムは鉛活字や鉛版を使わず、写真製版印刷によるためコールド・タイプ・システム(CTS)と呼ばれた。当社はこうした新聞制作の技術革新にいち早く注目、「日刊金属特報」のCTS化を進めていったのである。
CTS化の準備段階として、まず83年には普及期に入っていたワードプロセッサを積極的に導入、84年2月から記者のワープロ入力を開始した。新聞記者といえば、鉛筆を舐めながら原稿用紙に記事を書きなぐる姿がトレードマークであったが、その姿が消えることになったのである。現在でこそ記者のワープロ入力は一般化しているが、当時、記者全員による原稿のワープロ入力は、わが国新聞史上初の出来事であった。さらに同年、CTS化へ向け電算写植機、入力校正機、見出写植機などを導入、CTSの部分実施を経て87年3月には「日刊金属特報」の完全CTS化を完了した。
一方、新聞制作のCTS化と並行して進められたのが、紙面のブランケット版化である。77年にタブロイド版化を終え、紙面の質的向上が図られたが、それはあくまで過度的措置で、いずれブランケット版への大判化は避けて通れない課題であった。念願の大判化は「日刊金属特報」のCTS化から8カ月後の、87年11月からであった。
この間、日本経済はプラザ合意後の円高不況に苦しんでいたが、一方では円高メリットによる個人消費の拡大、円高是正のための内需拡大策、金利低下による資産効果などから、金融緩和下の地価高騰を生み、いわゆるバブル経済へと突き進んでいく。「財テク」がもてはやされ「土地転がし」が問題となった時代である。年号も昭和から平成へと変わったが、やがてあっけなくバブル経済は崩壊、1ドル=100円を割り込むという急激な円高の中で、深刻な不況に苦しめられるのである。
鉄鋼業界でも円高不況による「鉄冷え」は、バブル経済により一時的に持ち直したかに見えたが、円高がもたらした内外価格差による国際競争力の低下、輸入鋼材の流入などは、国内鉄鋼業の抜本的改革を迫ることとなった。このため、高炉メーカー各社を始め、事業のリストラクチャリングを実施、要員削減を中心とするコスト合理化を余儀なくされた。
こうした厳しい環境の中で産業新聞は、紙面の抜本的改革に取り組み始めた。その一環として、96年(平成8年)4月「日刊金属特報」から「産業新聞」への題字変更に踏み切った。「産業新聞」への題字変更は、読者ニーズに応えるより質の高い新聞づくりを目指したもので、需要業界ニュースの充実、ニュース解説記事、調査報道取材の充実などを図っている。さらに新聞制作でもCTSをさらに一歩進めた、コンピュータシステムへの移行を図った。新聞制作をすべてコンピュータ化した新聞制作システムは現在、新聞制作の主流となっているが、当社では専門紙業界ではいち早くコンピュータ化に取り組み、2000年4月には住友金属工業(現新日鉄住金)と共同開発した「SSスーパーシステム」の稼働へと結びつくのである。こうした新聞製作システムのコンピュータ化は、IT化時代への先駆けとして、さらなる発展の基盤となったのである。

この頃、日本経済は73年の第1次オイルショック、79年の第2次オイルショックを経て低成長期に入っていたが、85年9月には、プラザ合意による急激な円高に見舞われ、円高不況へと突入していった。こうした景気低迷は、否応なく産業界の構造転換を迫り、新聞業界もその例外ではあり得なかった。
それはまず新聞制作システムの技術革新となって表面化してきた。新聞制作の技術革新は、50年代後半、鉛活字を1字ずつ手で拾う文選植字工程が、漢字テレタイプに置き変わることから始まった。漢字テレタイプは、人手による文選植字工程を機械化したもので、鉛活字による凸版印刷というシステムそのものは変わらなかった。しかしその後、全自動写真植字機の登場により、鉛活字や鉛版を使わない全く新しいシステムに移行していった。伝統的な紙型・鉛版方式による印刷は、鉛を溶解する工程を含むため、ホット・タイプ・システムといわれたが、新システムは鉛活字や鉛版を使わず、写真製版印刷によるためコールド・タイプ・システム(CTS)と呼ばれた。当社はこうした新聞制作の技術革新にいち早く注目、「日刊金属特報」のCTS化を進めていったのである。
CTS化の準備段階として、まず83年には普及期に入っていたワードプロセッサを積極的に導入、84年2月から記者のワープロ入力を開始した。新聞記者といえば、鉛筆を舐めながら原稿用紙に記事を書きなぐる姿がトレードマークであったが、その姿が消えることになったのである。現在でこそ記者のワープロ入力は一般化しているが、当時、記者全員による原稿のワープロ入力は、わが国新聞史上初の出来事であった。さらに同年、CTS化へ向け電算写植機、入力校正機、見出写植機などを導入、CTSの部分実施を経て87年3月には「日刊金属特報」の完全CTS化を完了した。
一方、新聞制作のCTS化と並行して進められたのが、紙面のブランケット版化である。77年にタブロイド版化を終え、紙面の質的向上が図られたが、それはあくまで過度的措置で、いずれブランケット版への大判化は避けて通れない課題であった。念願の大判化は「日刊金属特報」のCTS化から8カ月後の、87年11月からであった。
この間、日本経済はプラザ合意後の円高不況に苦しんでいたが、一方では円高メリットによる個人消費の拡大、円高是正のための内需拡大策、金利低下による資産効果などから、金融緩和下の地価高騰を生み、いわゆるバブル経済へと突き進んでいく。「財テク」がもてはやされ「土地転がし」が問題となった時代である。年号も昭和から平成へと変わったが、やがてあっけなくバブル経済は崩壊、1ドル=100円を割り込むという急激な円高の中で、深刻な不況に苦しめられるのである。
鉄鋼業界でも円高不況による「鉄冷え」は、バブル経済により一時的に持ち直したかに見えたが、円高がもたらした内外価格差による国際競争力の低下、輸入鋼材の流入などは、国内鉄鋼業の抜本的改革を迫ることとなった。このため、高炉メーカー各社を始め、事業のリストラクチャリングを実施、要員削減を中心とするコスト合理化を余儀なくされた。
こうした厳しい環境の中で産業新聞は、紙面の抜本的改革に取り組み始めた。その一環として、96年(平成8年)4月「日刊金属特報」から「産業新聞」への題字変更に踏み切った。「産業新聞」への題字変更は、読者ニーズに応えるより質の高い新聞づくりを目指したもので、需要業界ニュースの充実、ニュース解説記事、調査報道取材の充実などを図っている。さらに新聞制作でもCTSをさらに一歩進めた、コンピュータシステムへの移行を図った。新聞制作をすべてコンピュータ化した新聞制作システムは現在、新聞制作の主流となっているが、当社では専門紙業界ではいち早くコンピュータ化に取り組み、2000年4月には住友金属工業(現新日鉄住金)と共同開発した「SSスーパーシステム」の稼働へと結びつくのである。こうした新聞製作システムのコンピュータ化は、IT化時代への先駆けとして、さらなる発展の基盤となったのである。

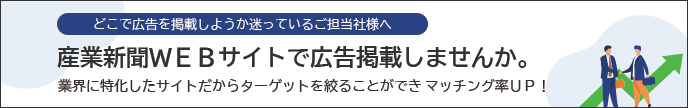















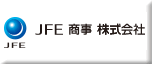












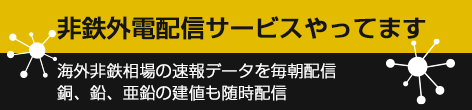



 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ