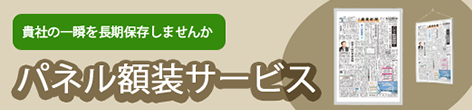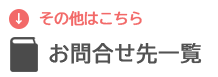2016年4月13日
【第3回】産業新聞80年史 高度成長の光と影 ―拡大期から変革期へ―
1960年(昭和35年)6月、流血の安保闘争で東大生樺美智子さんが死亡、岸内閣は退陣した。その後を受けた池田内閣は、「所得倍増計画」を発表、これを機に日本経済は本格的な高度成長を遂げていく。59年からの岩戸景気に始まり、オリンピック景気、いざなぎ景気と大型景気が続き、73年の第1次オイルショックに至るまでの間、高度成長が続いたのである。世間ではカラーテレビ、クーラー、カーの「3C商品」がもてはやされた時代である。
鉄鋼業界では、65年に粗鋼生産が4000万トン台に乗せたが、70年には9000万トン台とわずか5年の間に2倍以上に急増、73年にはついに1億トンをも突破した。この間に八幡製鐵堺、日本鋼管福山、川崎製鉄水島、八幡製鐵君津、神戸製鋼所加古川、住友金属工業鹿島など大型高炉が続々建設され、70年には八幡、富士合併による新日本製鉄誕生をみるのである。
こうした高度成長の中で、「日刊金属特報」は順調に発行部数を伸ばしていったが、さらに将来を見据え、通信網の整備、海外支局の設置など情報通信基盤の強化へと動いていった。通信網の整備では、すでに60年に東京、大阪、名古屋間の専用電話網を構築していたが、翌年4月には東京―大阪間にテレFAXを導入、ニュース伝送に一大変革をもたらした。この専用電話・テレFAX網は、その後全国に拡大され、62年にはテレFAX網を活用して、非鉄FAXニュースサービスを開始した。当時、非鉄業者は、原料や製品の売り買いに欠かせないLME、NYコメックス相場を知るのに、翌日の新聞を見るしか方法がなかった。ところが非鉄FAXサービスは、朝一番、居ながらにして当日の海外相場の入手を可能にした。このため非鉄原料業界では、「産業のFAXで、海外相場を早く知ったものが勝ち」といわれるほど、日々の商いに影響を与えた。
さらに68年3月には、ニューヨーク支局を開設、海外情報の充実にも力を入れた。現在でもそうだが、専門紙が海外支局を設置するのは異例のことで、まさに大英断であった。ニューヨーク発のニュースは、非鉄FAXサービスの充実はもとより、海外鉄鋼業界の情報提供にも威力を発揮し、産業新聞社の評価を一段と高めたのである。
ところで20年近く続いた高度成長は、一方では様々な歪みを生みつつあった。膨大な国際収支の黒字は、71年8月のドル・ショックをもたらし、さらにこれに続く73年10月の第1次オイルショックは、日本経済に決定的な一撃を加えた。国内では物不足が表面化、トイレットペーパー・パニックが起こったのもこの頃である。その後、第2次オイルショック、円高不況などが続き、75年代から85年代にかけての産業界は安定成長から低成長へと移行するのである。
こうした中で産業新聞も同様に、拡大・発展期を経て、徐々に変貌を遂げていくことになる。
まず、77年、それまでの仙花紙による特報形式の「日刊金属特報」が、新聞用紙によるタブロイド版に変更された。戦後の新聞用紙不足に対応した仙花紙の使用は、この頃には逆に仙花紙の製造メーカーがなくなり、用紙不足に陥るという状況にあった。また、特報形式の紙面は、情報量の増大とともに、紙面が40ページにも及ぶ膨大な量に達し、記事の収容不足も生じていた。このためタブロイド版への切り替えにより用紙不足、記事収容量の不足を解消するとともに、紙面の一層の充実を図ったのだ。
タブロイド版への変更は、「日刊金属特報」のさらなる飛躍を予感させるものであったが、こうした飛躍への胎動の中で、創業社長の亀尾芳雄は78年10月、その生涯を静かに閉じた。「鉄鋼金物新聞」の創刊から廃刊、戦後の復刊、「産業新聞」への社名変更、「日刊金属特報」の発刊と続く「産業新聞」の歴史は、亀尾の歴史そのものでもあり、その生涯は波乱に富んだ激動の一生であったといえる。
亀尾創業社長の亡くなった78年は、戦後最大の不況といわれたオイル・ショック不況から立ち直り、本格的景気回復が期待された年であった。しかし、早くも翌79年にはイラン政変をきっかけにした、第2次オイルショックに見舞われ、本格回復を見ないまま下降曲線を描いていった。この2度のオイルショックを契機に日本経済は低成長に移行し、本格的な構造転換期を迎えたのである。「軽薄短小」という言葉が持てはやされ、戦後一貫して続いた重化学工業路線は180度の転換を余儀なくされていった。鉄鋼業界も、73年の粗鋼生産1億200万トンをピークに生産量は低下、83年には1億トン割れをも経験する。
こうした厳しい環境の中で、産業新聞は次の発展へ向けての模索を続けていくが、それが東京・大阪同時印刷、新聞業界初の記者全員のワープロ入力、紙面の大判化、新聞制作のCTS化などに結実していくのである。(文中敬称略)

鉄鋼業界では、65年に粗鋼生産が4000万トン台に乗せたが、70年には9000万トン台とわずか5年の間に2倍以上に急増、73年にはついに1億トンをも突破した。この間に八幡製鐵堺、日本鋼管福山、川崎製鉄水島、八幡製鐵君津、神戸製鋼所加古川、住友金属工業鹿島など大型高炉が続々建設され、70年には八幡、富士合併による新日本製鉄誕生をみるのである。
こうした高度成長の中で、「日刊金属特報」は順調に発行部数を伸ばしていったが、さらに将来を見据え、通信網の整備、海外支局の設置など情報通信基盤の強化へと動いていった。通信網の整備では、すでに60年に東京、大阪、名古屋間の専用電話網を構築していたが、翌年4月には東京―大阪間にテレFAXを導入、ニュース伝送に一大変革をもたらした。この専用電話・テレFAX網は、その後全国に拡大され、62年にはテレFAX網を活用して、非鉄FAXニュースサービスを開始した。当時、非鉄業者は、原料や製品の売り買いに欠かせないLME、NYコメックス相場を知るのに、翌日の新聞を見るしか方法がなかった。ところが非鉄FAXサービスは、朝一番、居ながらにして当日の海外相場の入手を可能にした。このため非鉄原料業界では、「産業のFAXで、海外相場を早く知ったものが勝ち」といわれるほど、日々の商いに影響を与えた。
さらに68年3月には、ニューヨーク支局を開設、海外情報の充実にも力を入れた。現在でもそうだが、専門紙が海外支局を設置するのは異例のことで、まさに大英断であった。ニューヨーク発のニュースは、非鉄FAXサービスの充実はもとより、海外鉄鋼業界の情報提供にも威力を発揮し、産業新聞社の評価を一段と高めたのである。
ところで20年近く続いた高度成長は、一方では様々な歪みを生みつつあった。膨大な国際収支の黒字は、71年8月のドル・ショックをもたらし、さらにこれに続く73年10月の第1次オイルショックは、日本経済に決定的な一撃を加えた。国内では物不足が表面化、トイレットペーパー・パニックが起こったのもこの頃である。その後、第2次オイルショック、円高不況などが続き、75年代から85年代にかけての産業界は安定成長から低成長へと移行するのである。
こうした中で産業新聞も同様に、拡大・発展期を経て、徐々に変貌を遂げていくことになる。
まず、77年、それまでの仙花紙による特報形式の「日刊金属特報」が、新聞用紙によるタブロイド版に変更された。戦後の新聞用紙不足に対応した仙花紙の使用は、この頃には逆に仙花紙の製造メーカーがなくなり、用紙不足に陥るという状況にあった。また、特報形式の紙面は、情報量の増大とともに、紙面が40ページにも及ぶ膨大な量に達し、記事の収容不足も生じていた。このためタブロイド版への切り替えにより用紙不足、記事収容量の不足を解消するとともに、紙面の一層の充実を図ったのだ。
タブロイド版への変更は、「日刊金属特報」のさらなる飛躍を予感させるものであったが、こうした飛躍への胎動の中で、創業社長の亀尾芳雄は78年10月、その生涯を静かに閉じた。「鉄鋼金物新聞」の創刊から廃刊、戦後の復刊、「産業新聞」への社名変更、「日刊金属特報」の発刊と続く「産業新聞」の歴史は、亀尾の歴史そのものでもあり、その生涯は波乱に富んだ激動の一生であったといえる。
亀尾創業社長の亡くなった78年は、戦後最大の不況といわれたオイル・ショック不況から立ち直り、本格的景気回復が期待された年であった。しかし、早くも翌79年にはイラン政変をきっかけにした、第2次オイルショックに見舞われ、本格回復を見ないまま下降曲線を描いていった。この2度のオイルショックを契機に日本経済は低成長に移行し、本格的な構造転換期を迎えたのである。「軽薄短小」という言葉が持てはやされ、戦後一貫して続いた重化学工業路線は180度の転換を余儀なくされていった。鉄鋼業界も、73年の粗鋼生産1億200万トンをピークに生産量は低下、83年には1億トン割れをも経験する。
こうした厳しい環境の中で、産業新聞は次の発展へ向けての模索を続けていくが、それが東京・大阪同時印刷、新聞業界初の記者全員のワープロ入力、紙面の大判化、新聞制作のCTS化などに結実していくのである。(文中敬称略)

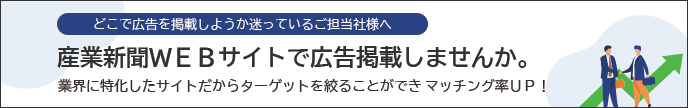













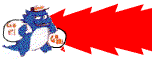


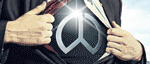











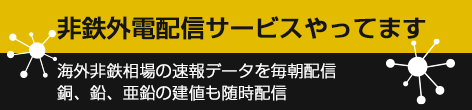



 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ