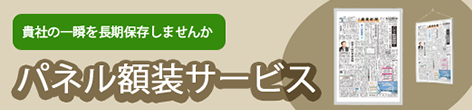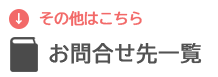2016年4月12日
【第2回】産業新聞80年史 戦後復刊から拡大・発展へ―業界の復興・飛躍とともに―
第二次世界対戦は、日本の産業界に壊滅的打撃を与えた。鉄鋼業界も設備の75%に甚大な被害を受け、終戦翌年の粗鋼生産は55万7000トンと、戦前のピークである765万トン(1943年=昭和18年)の10分の1以下に落ち込んでしまった。前途多難を思わせる終戦直後ではあったが、戦後の鉄鋼業が復興への第一歩を踏み出したのは、1946年12月に閣議決定された「石炭鉄鋼超重点増産計画」である。いわゆる「傾斜生産方式」と呼ばれるもので、石炭、鉄鋼の増産により産業復興を図るというものだ。これをテコに48年の粗鋼生産は171万トンと100万トン台を回復、49年には311万1000トンへと拡大し、50年に勃発した朝鮮動乱により一躍復興へと力強い歩みを始めるのである。
こうした中で「鉄鋼新聞」廃刊以来、新聞発行への愛着が断ち切れなかった亀尾芳雄は、かつての愛読者の熱心な勧めもあり、復刊へ向けて活動を再開する。戦後の混乱期とあって新聞用紙不足など多くの困難はあったが、47年12月、大阪で待望の「鉄鋼新聞」復刊第1号が発行されたのである。とはいえ、すでに戦前の「鉄鋼新聞」時代の先輩記者はおらず、記事の書き手がいない。やむなく自らが鋼材・非鉄問屋をまわって記事を書くという状態であった。ともあれ復刊「鉄鋼新聞」は、戦後復興に歩調を合わせるように力強く歩み始めたかに見えた。
ところがここで、思いも掛けない出来事が持ち上がった。終戦から復刊までの間に、すでに東京でタブロイド版2ページの「鉄鋼新聞」が発行されていたのである。復刊から間もなくのこと、ある読者から「東京にも鉄鋼新聞があるが、どういう関係か」と指摘され、その実物も見せられ社員は「ガク然とした」という。しかし復刊したばかりの「鉄鋼新聞」を止めるわけには行かない。その後1年は発行を続けたが、東京の「鉄鋼新聞」と、大阪の「鉄鋼新聞」があり、「非常に紛らわしい」という声が上がってきた。やむなく題字変更を決断したが、同時にこの頃、社として、「鉄鋼、非鉄だけでなく、全産業にわたる新聞を発行したい」との思いを強くしていた。このため復刊翌年の48年11月、社名、題字とも「産業新聞」への変更に踏み切ったのである。
しかし、この頃はまだ戦後の物資難の時代。新聞用紙の不足から「産業新聞」は、週刊での発行がやっとの状態であった。何とか戦前のような日刊紙をと考えた亀尾は、新聞用紙ではなく仙花紙(せんかし)と呼ばれる再生紙を使い、印刷能力不足に対応して片面印刷による特報通信形式の新聞を考案、題字を「日刊金属特報」に変更した。仙花紙の赤色に特徴がある特報版「日刊金属特報」は、49年12月発行され、その後、「赤新聞」「赤報」の愛称で爆発的な支持を得るのである。「日刊金属特報」は何よりも、編集方針を市場相場重点に置いた。折しも50年6月に勃発した朝鮮動乱は、戦後日本経済を一気に立ち直らせる契機となった。いわゆる朝鮮特需は、戦略物資としての銅、鉛、亜鉛などの相場を急騰させ、国内電気銅相場は、50年6月のトン16万2000円から、12月には22万5000円、翌年8月には32万4000円まで沸騰していったのである。こうした相場激変の中で、市場相場を的確に報道した「日刊金属特報」は、読者の絶大な信頼を得た。鉄鋼業界でも48年、粗鋼生産は300万トン台を回復していたが、51年には660万トンと倍増、56年には1000万トンの大台へと乗せていった。特報形式と市場相場中心の編集方針、朝鮮特需をきっかけとした鉄鋼、非鉄業界の活況、これらが相まって「日刊金属特報」は飛躍的発展を遂げていった。
「日刊金属特報」の成功はその後、繊維、化学など他の産業界を対象にした特報形式の新聞発行を促していった。この時期発行されたものに、50年5月の「日刊油脂特報」、同11月の「日刊繊維特報」、51年9月の「日刊化学特報」がある。さらに53年3月には、英語版「ジャパン・メタルブリテン」を発行するが、これら各紙はその後、業界の支持を得ながら分社独立して、それぞれの道を歩んで行くことになる。そのほかにも「日刊商品投資特報」、「日刊大豆特報」をそれぞれ68年、77年に発行している。
さらにこの時期、特筆すべきことは、専門紙業界をアッと言わせた高速輪転機の導入である。55年以降、日本経済は戦後復興から本格成長への道を歩み始めた。55年から57年にかけての好景気は「神武景気」と呼ばれ、56年の経済白書には「もはや戦後ではない」と書かれた時代である。鉄鋼業界でも57年からの第2次合理化計画により、八幡製鉄戸畑、富士製鉄広畑、日本鋼管水江、神戸製鋼所灘浜、住友金属和歌山など新鋭製鉄所の建設が進められていった。
こうした時代に即応するように、58年、専門紙業界のトップを切って1時間8万部の印刷能力を誇る高速輪転機を導入したのである。すでに発行部数の急速な拡大で印刷能力の不足に陥っていたこともあるが、専門紙としては異例の投資であり、その実力をいかんなく示した出来事であった。
戦後の復刊から、産業新聞社への社名変更、「日刊金属特報」の発行へと続く40―50年代は、日本経済の戦後復興から本格発展と歩調を合わせるように、産業新聞社が拡大・発展を続けた飛躍期ということができるだろう。(文中敬称略)

こうした中で「鉄鋼新聞」廃刊以来、新聞発行への愛着が断ち切れなかった亀尾芳雄は、かつての愛読者の熱心な勧めもあり、復刊へ向けて活動を再開する。戦後の混乱期とあって新聞用紙不足など多くの困難はあったが、47年12月、大阪で待望の「鉄鋼新聞」復刊第1号が発行されたのである。とはいえ、すでに戦前の「鉄鋼新聞」時代の先輩記者はおらず、記事の書き手がいない。やむなく自らが鋼材・非鉄問屋をまわって記事を書くという状態であった。ともあれ復刊「鉄鋼新聞」は、戦後復興に歩調を合わせるように力強く歩み始めたかに見えた。
ところがここで、思いも掛けない出来事が持ち上がった。終戦から復刊までの間に、すでに東京でタブロイド版2ページの「鉄鋼新聞」が発行されていたのである。復刊から間もなくのこと、ある読者から「東京にも鉄鋼新聞があるが、どういう関係か」と指摘され、その実物も見せられ社員は「ガク然とした」という。しかし復刊したばかりの「鉄鋼新聞」を止めるわけには行かない。その後1年は発行を続けたが、東京の「鉄鋼新聞」と、大阪の「鉄鋼新聞」があり、「非常に紛らわしい」という声が上がってきた。やむなく題字変更を決断したが、同時にこの頃、社として、「鉄鋼、非鉄だけでなく、全産業にわたる新聞を発行したい」との思いを強くしていた。このため復刊翌年の48年11月、社名、題字とも「産業新聞」への変更に踏み切ったのである。
しかし、この頃はまだ戦後の物資難の時代。新聞用紙の不足から「産業新聞」は、週刊での発行がやっとの状態であった。何とか戦前のような日刊紙をと考えた亀尾は、新聞用紙ではなく仙花紙(せんかし)と呼ばれる再生紙を使い、印刷能力不足に対応して片面印刷による特報通信形式の新聞を考案、題字を「日刊金属特報」に変更した。仙花紙の赤色に特徴がある特報版「日刊金属特報」は、49年12月発行され、その後、「赤新聞」「赤報」の愛称で爆発的な支持を得るのである。「日刊金属特報」は何よりも、編集方針を市場相場重点に置いた。折しも50年6月に勃発した朝鮮動乱は、戦後日本経済を一気に立ち直らせる契機となった。いわゆる朝鮮特需は、戦略物資としての銅、鉛、亜鉛などの相場を急騰させ、国内電気銅相場は、50年6月のトン16万2000円から、12月には22万5000円、翌年8月には32万4000円まで沸騰していったのである。こうした相場激変の中で、市場相場を的確に報道した「日刊金属特報」は、読者の絶大な信頼を得た。鉄鋼業界でも48年、粗鋼生産は300万トン台を回復していたが、51年には660万トンと倍増、56年には1000万トンの大台へと乗せていった。特報形式と市場相場中心の編集方針、朝鮮特需をきっかけとした鉄鋼、非鉄業界の活況、これらが相まって「日刊金属特報」は飛躍的発展を遂げていった。
「日刊金属特報」の成功はその後、繊維、化学など他の産業界を対象にした特報形式の新聞発行を促していった。この時期発行されたものに、50年5月の「日刊油脂特報」、同11月の「日刊繊維特報」、51年9月の「日刊化学特報」がある。さらに53年3月には、英語版「ジャパン・メタルブリテン」を発行するが、これら各紙はその後、業界の支持を得ながら分社独立して、それぞれの道を歩んで行くことになる。そのほかにも「日刊商品投資特報」、「日刊大豆特報」をそれぞれ68年、77年に発行している。
さらにこの時期、特筆すべきことは、専門紙業界をアッと言わせた高速輪転機の導入である。55年以降、日本経済は戦後復興から本格成長への道を歩み始めた。55年から57年にかけての好景気は「神武景気」と呼ばれ、56年の経済白書には「もはや戦後ではない」と書かれた時代である。鉄鋼業界でも57年からの第2次合理化計画により、八幡製鉄戸畑、富士製鉄広畑、日本鋼管水江、神戸製鋼所灘浜、住友金属和歌山など新鋭製鉄所の建設が進められていった。
こうした時代に即応するように、58年、専門紙業界のトップを切って1時間8万部の印刷能力を誇る高速輪転機を導入したのである。すでに発行部数の急速な拡大で印刷能力の不足に陥っていたこともあるが、専門紙としては異例の投資であり、その実力をいかんなく示した出来事であった。
戦後の復刊から、産業新聞社への社名変更、「日刊金属特報」の発行へと続く40―50年代は、日本経済の戦後復興から本格発展と歩調を合わせるように、産業新聞社が拡大・発展を続けた飛躍期ということができるだろう。(文中敬称略)

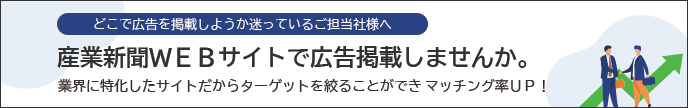















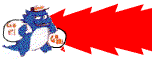












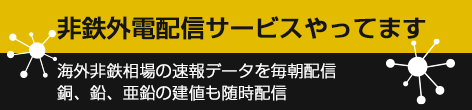



 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ