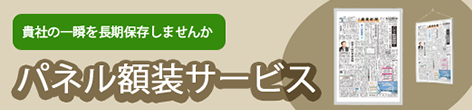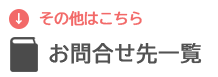2015年3月16日
国内産学連携の課題 東北大学金属材料研究所関西センター長・教授 正橋直哉氏 公的機関設立で持続性を
金属工学で世界をリードする東北大学金属材料研究所(仙台市青葉区)。その付属研究施設である関西センター(大阪オフィス=堺市中区)では、金属加工の中小企業が集積する大阪を拠点に産学連携を目指してきたが、前身の大阪センター時代と合わせると9年の年月がたとうとしている。学術機関が創出する新たな金属材料の価値と、中小企業が長年蓄積してきたノウハウを融合させて、ものづくりの底力を引き出そうと努めてきたが、そうした取り組みから見えてきた日本の産学連携の課題とは何か。関西センター長の正橋直哉教授に聞いた。
――まずは本年度の産学連携活動を振り返って。
「昨年12月末に集計した企業からの相談件数は554件で、過去最多だった一昨年の557件を上回るペースで増えている。その理由は近畿以外からの相談が増えたからだ。以前は50%以上が大阪府内の企業で占められていたが、現在は件数の増加とともに30%に下がっている。大阪府以外の近畿圏内は横ばいで、近畿以外の比率は倍の50%近くに上り、近畿圏内の件数とほぼ並ぶようになった」
――畿外からの技術相談が増えた理由。
「関西センターの認知が広がり、活動が広域化したということもあるが、海外からの相談もある。中には中国や韓国から、日本の技術を買うバイヤーと研究者が一緒になって、当センターに相談に来たこともある」
――技術に対する海外との認識の差も見えてきたということか。
「自社でゼロから技術を一から開発するより買った方が安いという発想は、米アップル社のビジネスモデルだそうで、韓国サムソン社には数百人のバイヤー・研究者がいる研究機関があると言われている。日本は技術の情報管理に甘いが、海外はこうした情報収集にはとてもアグレッシブだ」
――最近の技術相談の内容の傾向について。
「表面の改質・制御に関する相談が増えている気がする。私の研究領域ということもあるが、単体の材料開発では限界、あるいは飽和状態になっているので、表面に機能を付与して材料の価値を上げるというものだ。これまでは小型の民生部品だけのイメージだったが、自動車のボディー材のような大きなものにプラズマ処理を施す技術もあるので、まだまだ可能性を秘めた分野ということの表れかもしれない。新技術に対する問い合わせでは、チタンのインプラントや歯列矯正ワイヤなどの医療材料に対する相談が多い」
――中には応えるのが難しい相談内容もあるのでは。
「関西センターに来た相談の依頼は、コーディネーターがある程度選定してわれわれに届くのだが、実はその中でも専門分野に関連してお役に立てるのは全体の2―3割にすぎない。分野外の依頼については東北大学の産学連携推進本部に振ることもある」
――日本の産学連携活動の現状とは。
「別の大学に企業が相談したところ、たらい回しに遭ったなどという話も聞かれ、そうしたところからもれてきた相談が、関西センターの件数増加にもつながっているのだろう。大学側は得意の専門分野以外の相談には応じたくないという性質もあるし、他の大学にはわれわれのように産学連携を専門にする常駐機関がないので、通常の産学連携は研究や教育の合間に行うしかないのが現状なのだ」
――企業が相談できる常駐機関が関西センターの始まりだったが、実際見えた課題も多かったのでは。
「前身である大阪センターが設立したのは、当時の太田房江・大阪府知事の中小企業支援がきっかけだった。しかし大阪センター時代の5年間は、産学連携を通じて実用例や論文などの成果がほとんど上げられなかった。その理由は、相談する中小企業側に研究資金がなかったためで、結局は大学側からの持ち出し費用が多くなるなど、課題が噴出した。そのため関西センターでは企業規模にこだわらない方針をとり、大企業との契約件数も増えている」
――先生の共同研究の現場はどのようなものか。
「現在は8つの共同研究を持っているが、マンパワー的にもこれ以上抱えるのは難しい。産学連携の研究には学生を使えず、非常勤の実験助手を雇わなければならないのが厳しいところだ。欧米のように腰を据えて研究できる体制づくりが、つくづく必要だと感じる」
――欧米の産学連携とはどのようなものか。
「米国は産業活性化が国是として割り切っており、企業を支援する専門の公的機関がある。特定の企業支援ができない日本とは全く逆だ。日本と海外とでは、産学連携に対する考え方が全く違うのだ」
――その日本の産学連携を取り巻く環境はさらに厳しくなっている。
「文部科学省の関西センターに対する予算は4年間で半分以下になった。これは産学連携だけでなく、既存の学術分野を減らして、新しいプロジェクトに資金を充てるという方針に政府が変わったからだ。そのため、われわれの活動にも持続性がなくなっているのが現状だ」
――関西センターでは企業への教育を重視している。
「大阪センター時代から開催しているものづくり基礎講座は、昨年からプロセス技術編として圧延や鍛造などを取り上げ、参加者からのアンケートなどでは良い評価を頂いている。大学の講演は学会発表の資料を使い回して難しいと言われるので、資料をベーシックに作るように努めている。ものづくり講座をきっかけに技術相談を受けることもあるし、それが共同研究につながった例もあり、われわれにとっても良いチャンネルになっている」
――金属材料研究所では今どのような最新の研究がされているか。
「金属材料研究所は来年100周年を迎えるが、創設者の本多光太郎先生が磁性材料の世界的権威であった伝統から、今もその分野の研究が盛んだ。中でも磁石から発電するスピントロニクスは環境・エネルギー分野からも非常に注目されている。同時にMEMS(メムス)と言われる超微細加工は、デバイス作製において、スピントロニクスの性能を引き出すのに不可欠として研究されている。このように材料と加工は一体であるという考え方は、創設以来一貫している」
――非鉄金属に関する研究にはどのようなものがあるか。
「先ほど申したチタンなどの医療材料に関しては、東北大学に医工学研究科が設立されるなど、活発化している。成熟していたと見られていた銅についても、ここにきて基礎研究に戻る向きも出ている。私たちの研究グループでは、導電材料として強度と導電率の両方を備えた銅合金の開発を、複数の企業と共同で始まっている」
――関西センターの活動予定期間はあと2年だが、今後のために産学連携に対する提言は。
「大学側の環境作りが必要だ。年数を区切るのではなく、欧米のように独立した公的教育機関として、専従の教員をつけなければならない。大学の教員だと、どうしても論文の数などで評価されてしまうので、そうした縛りをなくさなければならないと思う。また、学生が社会のニーズに触れることができれば、社会性に秀でた人格形成にも産学連携は役立つだろう。そうした公的機関があれば、企業からも能力開発や人事担当の方々を講師として招けるだろう」
――大学の知的財産を産業界に生かすに当たっての課題とは。
「大学が持つ特許などを民間に有償譲渡するためにも、大学はそれを見せる努力をしなければならない。しかし大学は特許を取っても、それを維持するには年間で10万円以上の費用がかかり、それだけ研究開発費が削られて負担になっている。特許の数が評価につながるという大学の性質上、特許の中身についても問題は多い。市場調査も行わないので、東北大で年間で取得する数百件の特許のうち、収入につながるのはわずか1割未満だ。戦前の金属材料研究所は特許収入が大きな財源だったが、当時は研究者が世の中をよく見ていたと思う。産学連携を通じて、浮き彫りになった今の大学が抱える問題は実に多い」 (桐山 太志)
1987年東北大学大学院で工学博士を取得、新日本製鉄(現新日鉄住金)入社。チタン・鉄鋼・半導体・ポリシリコンの開発に従事し、93―95年英国ケンブリッジ大学客員研究員、99年東北大金属材料研究所助教授、06年教授。専門は金属組織学。関西センター長として仙台と大阪を往復する生活。単身赴任生活の大阪では、朝に世界最大の古墳の仁徳天皇陵(1周約3キロメートル)をジョギングするのが日課だが、最近は多忙でなかなか走れないのが悩み。58年9月生まれ、東京都出身。
▽東北大学金属材料研究所関西センター=2006年に大阪府の誘致で、企業の技術課題の相談ができる「大阪センター」として発足。11年から活動範囲を広げ「関西センター」に改称・再発足した。現在7人の教授が所属。大阪府立大学や兵庫県立大学などを研究活動拠点とし、クリエイション・コア東大阪(東大阪市)に相談窓口を置く。

――まずは本年度の産学連携活動を振り返って。
「昨年12月末に集計した企業からの相談件数は554件で、過去最多だった一昨年の557件を上回るペースで増えている。その理由は近畿以外からの相談が増えたからだ。以前は50%以上が大阪府内の企業で占められていたが、現在は件数の増加とともに30%に下がっている。大阪府以外の近畿圏内は横ばいで、近畿以外の比率は倍の50%近くに上り、近畿圏内の件数とほぼ並ぶようになった」
――畿外からの技術相談が増えた理由。
「関西センターの認知が広がり、活動が広域化したということもあるが、海外からの相談もある。中には中国や韓国から、日本の技術を買うバイヤーと研究者が一緒になって、当センターに相談に来たこともある」
――技術に対する海外との認識の差も見えてきたということか。
「自社でゼロから技術を一から開発するより買った方が安いという発想は、米アップル社のビジネスモデルだそうで、韓国サムソン社には数百人のバイヤー・研究者がいる研究機関があると言われている。日本は技術の情報管理に甘いが、海外はこうした情報収集にはとてもアグレッシブだ」
――最近の技術相談の内容の傾向について。
「表面の改質・制御に関する相談が増えている気がする。私の研究領域ということもあるが、単体の材料開発では限界、あるいは飽和状態になっているので、表面に機能を付与して材料の価値を上げるというものだ。これまでは小型の民生部品だけのイメージだったが、自動車のボディー材のような大きなものにプラズマ処理を施す技術もあるので、まだまだ可能性を秘めた分野ということの表れかもしれない。新技術に対する問い合わせでは、チタンのインプラントや歯列矯正ワイヤなどの医療材料に対する相談が多い」
――中には応えるのが難しい相談内容もあるのでは。
「関西センターに来た相談の依頼は、コーディネーターがある程度選定してわれわれに届くのだが、実はその中でも専門分野に関連してお役に立てるのは全体の2―3割にすぎない。分野外の依頼については東北大学の産学連携推進本部に振ることもある」
――日本の産学連携活動の現状とは。
「別の大学に企業が相談したところ、たらい回しに遭ったなどという話も聞かれ、そうしたところからもれてきた相談が、関西センターの件数増加にもつながっているのだろう。大学側は得意の専門分野以外の相談には応じたくないという性質もあるし、他の大学にはわれわれのように産学連携を専門にする常駐機関がないので、通常の産学連携は研究や教育の合間に行うしかないのが現状なのだ」
――企業が相談できる常駐機関が関西センターの始まりだったが、実際見えた課題も多かったのでは。
「前身である大阪センターが設立したのは、当時の太田房江・大阪府知事の中小企業支援がきっかけだった。しかし大阪センター時代の5年間は、産学連携を通じて実用例や論文などの成果がほとんど上げられなかった。その理由は、相談する中小企業側に研究資金がなかったためで、結局は大学側からの持ち出し費用が多くなるなど、課題が噴出した。そのため関西センターでは企業規模にこだわらない方針をとり、大企業との契約件数も増えている」
――先生の共同研究の現場はどのようなものか。
「現在は8つの共同研究を持っているが、マンパワー的にもこれ以上抱えるのは難しい。産学連携の研究には学生を使えず、非常勤の実験助手を雇わなければならないのが厳しいところだ。欧米のように腰を据えて研究できる体制づくりが、つくづく必要だと感じる」
――欧米の産学連携とはどのようなものか。
「米国は産業活性化が国是として割り切っており、企業を支援する専門の公的機関がある。特定の企業支援ができない日本とは全く逆だ。日本と海外とでは、産学連携に対する考え方が全く違うのだ」
――その日本の産学連携を取り巻く環境はさらに厳しくなっている。
「文部科学省の関西センターに対する予算は4年間で半分以下になった。これは産学連携だけでなく、既存の学術分野を減らして、新しいプロジェクトに資金を充てるという方針に政府が変わったからだ。そのため、われわれの活動にも持続性がなくなっているのが現状だ」
――関西センターでは企業への教育を重視している。
「大阪センター時代から開催しているものづくり基礎講座は、昨年からプロセス技術編として圧延や鍛造などを取り上げ、参加者からのアンケートなどでは良い評価を頂いている。大学の講演は学会発表の資料を使い回して難しいと言われるので、資料をベーシックに作るように努めている。ものづくり講座をきっかけに技術相談を受けることもあるし、それが共同研究につながった例もあり、われわれにとっても良いチャンネルになっている」
――金属材料研究所では今どのような最新の研究がされているか。
「金属材料研究所は来年100周年を迎えるが、創設者の本多光太郎先生が磁性材料の世界的権威であった伝統から、今もその分野の研究が盛んだ。中でも磁石から発電するスピントロニクスは環境・エネルギー分野からも非常に注目されている。同時にMEMS(メムス)と言われる超微細加工は、デバイス作製において、スピントロニクスの性能を引き出すのに不可欠として研究されている。このように材料と加工は一体であるという考え方は、創設以来一貫している」
――非鉄金属に関する研究にはどのようなものがあるか。
「先ほど申したチタンなどの医療材料に関しては、東北大学に医工学研究科が設立されるなど、活発化している。成熟していたと見られていた銅についても、ここにきて基礎研究に戻る向きも出ている。私たちの研究グループでは、導電材料として強度と導電率の両方を備えた銅合金の開発を、複数の企業と共同で始まっている」
――関西センターの活動予定期間はあと2年だが、今後のために産学連携に対する提言は。
「大学側の環境作りが必要だ。年数を区切るのではなく、欧米のように独立した公的教育機関として、専従の教員をつけなければならない。大学の教員だと、どうしても論文の数などで評価されてしまうので、そうした縛りをなくさなければならないと思う。また、学生が社会のニーズに触れることができれば、社会性に秀でた人格形成にも産学連携は役立つだろう。そうした公的機関があれば、企業からも能力開発や人事担当の方々を講師として招けるだろう」
――大学の知的財産を産業界に生かすに当たっての課題とは。
「大学が持つ特許などを民間に有償譲渡するためにも、大学はそれを見せる努力をしなければならない。しかし大学は特許を取っても、それを維持するには年間で10万円以上の費用がかかり、それだけ研究開発費が削られて負担になっている。特許の数が評価につながるという大学の性質上、特許の中身についても問題は多い。市場調査も行わないので、東北大で年間で取得する数百件の特許のうち、収入につながるのはわずか1割未満だ。戦前の金属材料研究所は特許収入が大きな財源だったが、当時は研究者が世の中をよく見ていたと思う。産学連携を通じて、浮き彫りになった今の大学が抱える問題は実に多い」 (桐山 太志)
1987年東北大学大学院で工学博士を取得、新日本製鉄(現新日鉄住金)入社。チタン・鉄鋼・半導体・ポリシリコンの開発に従事し、93―95年英国ケンブリッジ大学客員研究員、99年東北大金属材料研究所助教授、06年教授。専門は金属組織学。関西センター長として仙台と大阪を往復する生活。単身赴任生活の大阪では、朝に世界最大の古墳の仁徳天皇陵(1周約3キロメートル)をジョギングするのが日課だが、最近は多忙でなかなか走れないのが悩み。58年9月生まれ、東京都出身。
▽東北大学金属材料研究所関西センター=2006年に大阪府の誘致で、企業の技術課題の相談ができる「大阪センター」として発足。11年から活動範囲を広げ「関西センター」に改称・再発足した。現在7人の教授が所属。大阪府立大学や兵庫県立大学などを研究活動拠点とし、クリエイション・コア東大阪(東大阪市)に相談窓口を置く。

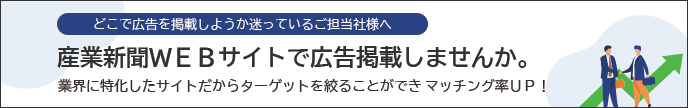
















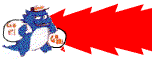











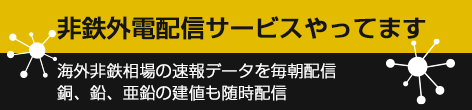



 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ