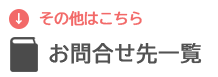2021年11月10日

鉄鋼業界で働く/女性社長編/インタビュー(上)/社員は目標共有する仲間

鉄鋼業界の女性の活躍は営業や取締役などにとどまらない。1927年の創業から90年以上の歴史を持つオーナー系鋼材特約店、三木工業材料(本社=兵庫県三木市)では、代表取締役社長の三宅真紀子さんが日々業務に当たっている。祖父の英夫さん、父親の哲正さんらが代々社長を務めたのち、2018年に9代目社長に就任。鉄鋼業界に入るまでの経緯や入社後の業務内容などを聞いた。
――鉄鋼業界に入るまでは。
「中学から神戸の私立女子校に通い、何不自由なく過ごしていました。ただ心のどこかで、このまま安全なレールの上を歩むのではなく、一度くらいは私のことを誰も知らない土地で生きてみたいと思っていました。今になって思うと、そこまで特別な人間ではないのですが(笑)。選んだ場所は、家族旅行で以前訪れ、活気あふれる人や街並みに憧れた香港です。短大卒業後に2年間留学し広東語を習得。いったん帰国し、在日中国人向けの旅行会社のカウンター営業に従事。再び香港に渡り、日系プリント基盤メーカーの営業と日系音響コイルメーカーの経理マネージャーを経験しました」
――現在の会社で働くきっかけを。
「うまく表現できていないかもしれませんが“三宅家の血"を感じたんです(笑)。ようやくつかみ取った香港の職場で、自分の能力や体力、気力を目の当たりにし、祖父や父が携わる仕事はどんなものだったのか何度も考えるようになりました。いつしか、『三木工業材料を手伝いたい。お父さんの跡を継ぎたい』との思いが強くなり、05年5月、三木工業材料に入社しました」
――鉄鋼業界へ飛び込むことに不安はなかった。
「香港には現地に住む日本人のコミュニティーがあって、その中に鉄鋼業界の方が複数いらしたんです。話していて『この方の勤務先はたぶん父の会社と取引をしているな』と感じることもあったりして。身の振り方を相談するうち、帰国して父の会社に入ることが選択肢になりました。なのでこの業界独特の雰囲気に戸惑うことはありませんでした。香港で、今もお付き合いのある複数の方と知り合ったことで、鉄鋼業界に引き寄せられたのかもしれません。大きなご縁をいただいたと思っています」
――入社後は。
「最初は営業部のアシスタントで先輩社員と一緒にお客さまの会社を回っていました。その後、経理や仕入れなど一通りの業務を経験しましたね。当時は地に足がついていない状態でした。未経験なので、何もできない。分からない。生業について理解しきれていない。それなのに頭でっかちで、格好ばかり気にしていて。『社長の娘だから何でもできないとだめ』『社員に仕事で勝たないとあかん』『勝たないと尊敬してもらえない』とばかり思っていました」
――社長になることへのプレッシャーがあったのかもしれません。
「18年に社長に就任するまで、そんな葛藤をずっと抱えていました。自分の足りない部分を素直に認めることで、気持ちが楽になった気がします。冷静に考えると、私には相談できる父、業界の物知り博士のような常務、いつも冷静に物事を判断する課長、ともに目標に向かって頑張ってくれる社員が周りにいました。彼らは勝負の相手ではなく目標を共有する仲間なんだと遅ればせながら気付きました。今になってようやく歯車が回りだした気がします」
――社内で心掛けていることは。
「社員と同じ目線に立ち、できるだけ多く話しかけるよう心掛けています。フレンドリーに接しているつもりです」
――現在の業務を。
「社長業はもちろん、仕入れや特殊鋼のひも付きの営業担当をしていて、三木市内を回っています。値段交渉も自分で行っているんですよ。昔ながらの取引やお付き合いなど歴史の上に成り立つ仕入れ先、お客さまとの信頼関係を大切に、感謝の気持ちを忘れないよう心掛けています」
――働く中で気になったことは。
「商流が独特だなと。私が担当している特殊鋼のひも付きの場合、何十年も前にお客さまと鉄鋼メーカーが協議し、品質やサイズを決めた鋼材を出荷しています。大きな問題がない限り、メーカーの方に同行していただいてお客さまのもとを訪問する機会は少ないです。値上げと値下げ、年末年始のあいさつくらいでしょうか。世の中が変化していく中、このような関係性に意味があるのだろうか? と感じていました。でも、先代社長で現会長の父に相談すると、これには意味があると断言されました。『信頼のもと三木工業材料で材料を買ってくださるお客さまがいる。信頼のもと、材料を売ってくださる仕入れ先がある。そこに存在意義はある』と」
――父の教えで考えが変わった。
「先日お伺いした取引先の社長さんからもご意見をいただきました。ずっと安定供給できることに安心を覚えて、不良がなくクレームが出ないことを良しとしていては、私たちは満足できませんよ、と。価格や納期、品質とは別に、さらなる顧客満足につながる何かを提案するのが営業のお仕事ですよとも。基本中の基本を指摘され、大変恥ずかしい気持ちになると同時に“ハッ"としました」(芦田 彩)

――鉄鋼業界に入るまでは。
「中学から神戸の私立女子校に通い、何不自由なく過ごしていました。ただ心のどこかで、このまま安全なレールの上を歩むのではなく、一度くらいは私のことを誰も知らない土地で生きてみたいと思っていました。今になって思うと、そこまで特別な人間ではないのですが(笑)。選んだ場所は、家族旅行で以前訪れ、活気あふれる人や街並みに憧れた香港です。短大卒業後に2年間留学し広東語を習得。いったん帰国し、在日中国人向けの旅行会社のカウンター営業に従事。再び香港に渡り、日系プリント基盤メーカーの営業と日系音響コイルメーカーの経理マネージャーを経験しました」
――現在の会社で働くきっかけを。
「うまく表現できていないかもしれませんが“三宅家の血"を感じたんです(笑)。ようやくつかみ取った香港の職場で、自分の能力や体力、気力を目の当たりにし、祖父や父が携わる仕事はどんなものだったのか何度も考えるようになりました。いつしか、『三木工業材料を手伝いたい。お父さんの跡を継ぎたい』との思いが強くなり、05年5月、三木工業材料に入社しました」
――鉄鋼業界へ飛び込むことに不安はなかった。
「香港には現地に住む日本人のコミュニティーがあって、その中に鉄鋼業界の方が複数いらしたんです。話していて『この方の勤務先はたぶん父の会社と取引をしているな』と感じることもあったりして。身の振り方を相談するうち、帰国して父の会社に入ることが選択肢になりました。なのでこの業界独特の雰囲気に戸惑うことはありませんでした。香港で、今もお付き合いのある複数の方と知り合ったことで、鉄鋼業界に引き寄せられたのかもしれません。大きなご縁をいただいたと思っています」
――入社後は。
「最初は営業部のアシスタントで先輩社員と一緒にお客さまの会社を回っていました。その後、経理や仕入れなど一通りの業務を経験しましたね。当時は地に足がついていない状態でした。未経験なので、何もできない。分からない。生業について理解しきれていない。それなのに頭でっかちで、格好ばかり気にしていて。『社長の娘だから何でもできないとだめ』『社員に仕事で勝たないとあかん』『勝たないと尊敬してもらえない』とばかり思っていました」
――社長になることへのプレッシャーがあったのかもしれません。
「18年に社長に就任するまで、そんな葛藤をずっと抱えていました。自分の足りない部分を素直に認めることで、気持ちが楽になった気がします。冷静に考えると、私には相談できる父、業界の物知り博士のような常務、いつも冷静に物事を判断する課長、ともに目標に向かって頑張ってくれる社員が周りにいました。彼らは勝負の相手ではなく目標を共有する仲間なんだと遅ればせながら気付きました。今になってようやく歯車が回りだした気がします」
――社内で心掛けていることは。
「社員と同じ目線に立ち、できるだけ多く話しかけるよう心掛けています。フレンドリーに接しているつもりです」
――現在の業務を。
「社長業はもちろん、仕入れや特殊鋼のひも付きの営業担当をしていて、三木市内を回っています。値段交渉も自分で行っているんですよ。昔ながらの取引やお付き合いなど歴史の上に成り立つ仕入れ先、お客さまとの信頼関係を大切に、感謝の気持ちを忘れないよう心掛けています」
――働く中で気になったことは。
「商流が独特だなと。私が担当している特殊鋼のひも付きの場合、何十年も前にお客さまと鉄鋼メーカーが協議し、品質やサイズを決めた鋼材を出荷しています。大きな問題がない限り、メーカーの方に同行していただいてお客さまのもとを訪問する機会は少ないです。値上げと値下げ、年末年始のあいさつくらいでしょうか。世の中が変化していく中、このような関係性に意味があるのだろうか? と感じていました。でも、先代社長で現会長の父に相談すると、これには意味があると断言されました。『信頼のもと三木工業材料で材料を買ってくださるお客さまがいる。信頼のもと、材料を売ってくださる仕入れ先がある。そこに存在意義はある』と」
――父の教えで考えが変わった。
「先日お伺いした取引先の社長さんからもご意見をいただきました。ずっと安定供給できることに安心を覚えて、不良がなくクレームが出ないことを良しとしていては、私たちは満足できませんよ、と。価格や納期、品質とは別に、さらなる顧客満足につながる何かを提案するのが営業のお仕事ですよとも。基本中の基本を指摘され、大変恥ずかしい気持ちになると同時に“ハッ"としました」(芦田 彩)

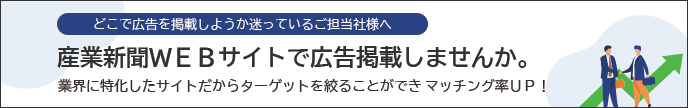












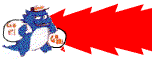

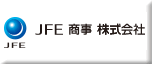
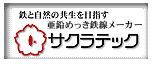










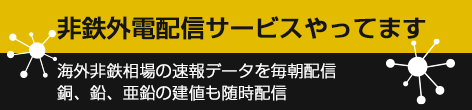




 産業新聞の特長とラインナップ
産業新聞の特長とラインナップ